おはようございます。今朝コロちゃんがワンコと散歩に出かけましたら、お空に「ぼんやりと光った太陽」がのぼっていました。
へー、珍しいな。コロちゃんは「おぼろ月」って言うのはよく見たことがありましたけれど、これって「おぼろ太陽だよね」と呟いてしまいましたよ。
( ¯ㅿ¯)へー
この「おぼろ月」というのは、霧や靄などに包まれ、柔らかくほのかにかすんで見える「春の夜の月」のことを言うそうですね。
ただ「おぼろ太陽」という言葉はありませんから、これは単に「薄い雲にさえぎられた太陽」なんでしょうね。
コロちゃんがポチポチ調べてみると「おぼろ雲(高層雲)」という気象用語はありましたから、上記の「おぼろ太陽」は、「高層雲(おぼろ雲)越しの太陽」となるみたいですね。
だけど「おぼろ月」だと風情がありますが、「おぼろ太陽」じゃ「俳句」にも使えそうもないですね。「季語」にもなりませんよ。下記のフォトをご覧くださいね。
そんな「おぼろ太陽を見たコロちゃん」が、今日は「大往生が増えているよ」をカキコキしますね。

0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「老衰死が増えているよと、大往生と人生の満足度」
☆「自宅で大往生はできるかな?と、コロちゃんと今は亡き妻との会話」

1.「老衰死が増えているよ」
コロちゃんが、朝新聞をバサバサ読み終わり、その後に「電子版」を読んでいると「老衰死8人に1人...増える『大往生』」との見出しが目に入りました。
コロちゃんは「大往生」なんて久しぶりに聞く言葉だなと思いましたよ。
この「大往生」とは、「苦しみや心の乱れがなく、安らかに天寿を全うして亡くなること」を指していますが、一般的には、「老衰」や「自然死」のことを言います。
コロちゃんの年代ですと、「永六輔著の大往生」という本が頭に浮かびますね。この本は「1994年」に「岩波新書」から出版され、200万部を超えるベストセラーとなっていました。
当時は騒がれましたが、コロちゃんは読んでいませんでしたよ。
「永六輔さん」はもうお亡くなりになっていますが、この方のお父さんが「元浅草の最尊寺の住職」だったようですよ。
おっと、話しがそれちゃいましたね。
\(-\)(/-)/ ソレハコッチニオイトイテ…
冒頭の「電子版の記事」によると、最近は「大往生(老衰死)」が増えているというのですよ。下記でしたよ。
◎「老衰の死因別順位」
●「1995年」
➀「がん :28%」
②「脳血管疾患:15%」
③「心疾患 :15%」
④「肺炎 :8%」
⑤「不慮の事故 :4%」
⑥「老衰 :2%」
●「2010年」
➀「がん :29%」
②「心疾患 :15%」
③「脳血管疾患:10%」
④「肺炎 : 9%」
⑤「老衰 :3%」
⑥「不慮の事故 :3%」
●「2024年」
➀「がん :24%」
②「心疾患 :14%」
③「老衰 :12%」
④「脳血管疾患:6%」
⑤「 肺炎 :4%」
⑥「誤飲性肺炎:3%」
(出典:厚生労働省 人口動態統計:1995年・2010年・2024年より:7月9日利用)
おー、上記の「1995年から2024年の30年間」に、「老衰死」は「2%から12%」の6倍に増えていますよ。
(o゚Д゚)オー
「死亡順位」も「6位から3位」へと上昇してきていますね。コロちゃんもこの「死に方」がいいかな?
( ◍´罒`◍)エヘヘ
この記事では、「看取りを行なう医師の言葉」として以下を紹介しています。
「高齢者が食べられなくなるのが老衰死のサイン」
「年をとって飲み込む機能や消化する能力が低下すると、口から食べるのが苦労するようになる。体力が低下し眠っている時間が長くなり、延命治療をしないと1~2週間で亡くなるというのがよくあるパターン」
このような「死に方」をすると、「家族からは大往生だったと受け止められることが多い」というのですよ。
そして記事では、「治療で苦しい思いをするより安らかに死にたいと考える高齢者は今後も増えそうだ」と締めています。
コロちゃんは、これがいいなー。
( ´∀`)bイイナー
この記事の「大往生=老衰死」は、なかなか「魅力的な死に方」ですよ。だけど、いつ訪れてくれるのかなー?
ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?
事前にいつ来るのかがわかっていれば、心構えも準備も出来るんですけどねー。
なお、この「日経新聞」の「老衰死8人に1人...増える『大往生』」の記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
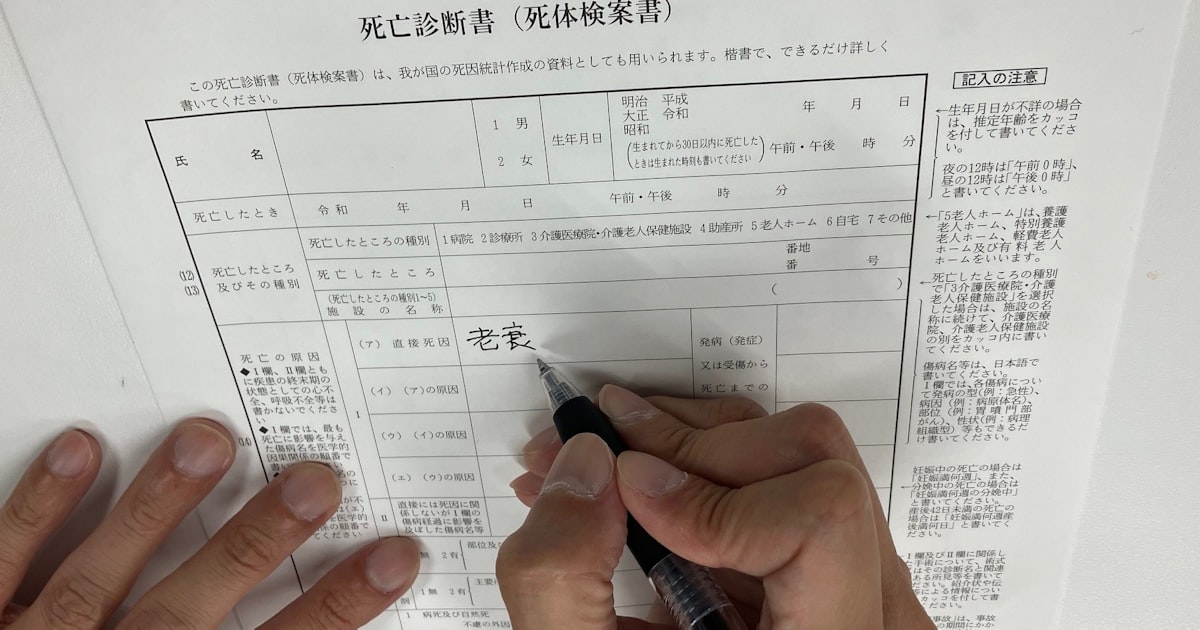
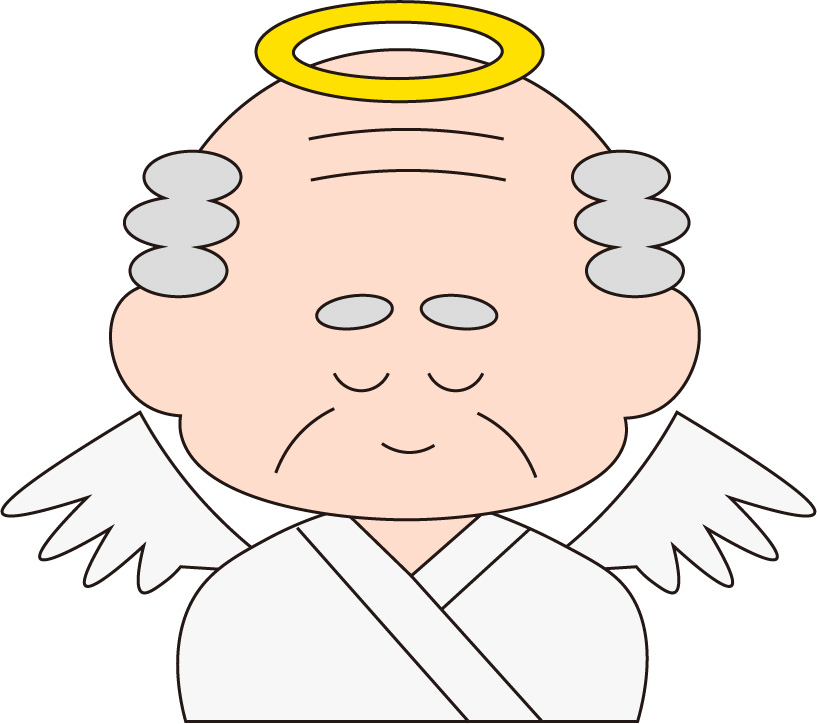
2.「大往生と人生の満足度」
上記の記事では「大往生」という言葉について、「家族や親族」が語る言葉として取り上げています。つまり「穏やかな高齢者の最後について家族が大往生だと受け止めている」というわけですね。
ただ「高齢者本人」もまた「延命よりも自然な死を迎えたい」との死生観が拡がって来ていると書いていますね。
コロちゃんは、この「大往生」という言葉の中には「長い人生を充分満足して走り抜けた」との価値観が入っていると思っていますね。
つまり「人生に悔いを残さず」「全てやり切った」との思いですよ。
誰しもが「人生の中」で、その時々の「目標」を設定して生きていますよね。それには「高校受験」も「大学受験」もあるでしょうし、「就職」や「結婚」もあるでしょう。
その後は「家族と子どものこと」や、人によっては「転職」や「スキルアップ」もあるかも知れません。
もちろん、全て「うまく行った・成功した」という事ばかりではありませんよね。全部が成功した人間ならば「歴史」に残ります世。そんなのはごく一握りしか居ませんよ。
現実には「失敗や後退ばかり」なのが人生の常なのですよ。
それらを全て「人生の最終段階」で振り返ってみた時に、「失敗も多かったけれど充実していたな」と思えることが、本人が感じる「大往生」なのではないかとコロちゃんは考えているのですよ。
なおこの「充実感」というものは、「目標に社会性があるほど強く感じられる」というのがコロちゃんの持論ですね。
つまり「自分自身のために頑張る」よりは、「誰かのために汗をかく」「社会のために力を尽くす」ことの方が頑張れるし、充実感も高いのですよ。
わかりやすく言うと、「個人の金儲け」よりは「社会と歴史に爪痕を残す」方が「心」が燃えますよ。その結果が「失敗」でも最後の「大往生」は間違いなしとコロちゃんは考えていますよ。

3.「自宅で大往生はできるかな?」
さてコロちゃんは、出来れば「自宅で大往生したい」と考えています。それも直前まで「現在の生活」を続けていて、いきなりポックリが理想ですね。
「PPK(ピンピンコロリ)」の確率は7~8割あるとされています(※)。
(※ピンピンコロリの確率:健常~要介護1までで亡くなる可能性)
「健常の高齢者」がいきなりポックリ逝く割合は5%程度らしいですが、「健常~要介護1」にまで広げると7~8割の高齢者が「PPK(ピンピンコロリ)」で亡くなっているそうなのですよ。
これならコロちゃんでも手が届くかも知れませんね。コロちゃんの希望は「自宅で大往生」ですよ。
冒頭の新聞記事では、「死ぬ場所と老衰死の場所」のグラフも記載されていましたよ。参考までに見てみましょう。下記でしたよ。
◎「死ぬ場所」(少数点以下切り捨て)
➀「病院・診療所:65%」
②「介護施設 :15%」
③「自宅 :17%」
◎「老衰死の場所」
➀「病院・診療所:31%」
②「介護施設 :49%」
③「自宅 :16%」
(出典:日経新聞:老衰死8人に1人...増える『大往生』より:7月9日利用)
うーむ、これを見ると「死ぬ場所は病院65%」が一番多く、「老衰死は介護施設49%」が多いですよね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
コロちゃんが希望する「自宅死」も「自宅老衰死」も、2割弱ですから少ないですが「不可能」とまでは言えないと受け止めましたよ。
こればっかりは「頑張って」もかなえられるとは限らないからなー。「努力」よりも「運」の要素がほとんどのような気がしますよ。
まあ、それでももちろん「頑張り」ますよ。
ガン!!o(゚Д゚ )o≡o( ゚Д゚)oバル!!

4.「コロちゃんと今は亡き妻との会話」
さて今日は「大往生が増えているよ」との「人の死」をテーマとしてみました。
コロちゃんには「哲学的な素養・教養がない」ですから、このような「形而上学的なテーマ」はホントは苦手なのですよ。
そこで具体的なエピソードとして、コロちゃんが3年前に妻と交わした会話をご紹介しますね。
コロちゃんの妻は、3年前に「肺がんでもう治療は出来ません」と「大学病院の医師」から「宣告」されました。その時には「余命は3~6ヶ月」と伝えられました。
その後の「大学病院」からの帰りの車の中で、妻は泣きながら「先に逝くけどごめんね」と言ったのです。
コロちゃんもまた涙を流しながら妻に次の言葉を返したのです。
「子どもたちも立派に独り立ちしたし、私たちはよくやったよ。2人だからここまで来れたんだよ」
そうと言うと、妻は「そだよね」と泣きながらうなずいていましたよ。
その言葉をしゃべりながらコロちゃんの頭の中を去来したのは「2つの光景」でした。
1つ目は、1970年代前半に妻と一緒に暮らし始めた時の「アパート」の光景です。「台所・トイレは共同で風呂なしの8畳間+2畳の板張り」の「貧しい暮らし」でしたよ。
そして2つ目は、この時点の前年の秋に行なわれた「次男の結婚式」の光景です。その場でコロちゃんと妻は「新郎の両親」として参列したのです。
この時妻は、「肺がん」の進行で立つのがやっとの身体となっていましたが、「留め袖の和服」でしっかりと「新郎の母」を務めていましたよ。
この2つの光景は、コロちゃんと妻の2人の「出発点」と「到達点」です。
コロちゃんと妻は、2人とも1970年前後に単身で上京し、裸一貫から「家族」をつくり、2人の子どもたちを育て、巣立ちさせてきたのです。
その「2人の長い歩み」の「到達点」が、「次男の結婚式」だったのですよ。
この「出発点」と「到達点」の思いは、決してコロちゃんだけのものではありませんでした。
「私たちはよくやったよ。2人だからここまで来れたんだよ」という言葉は、その時の「コロちゃんと妻ふたりに通じる思い」だったのです。
ふたりとも泣きましたね。
๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐
この6ヶ月後に「妻」は旅立ちましたが、心残りはなかったと思いますよ。病名は「肺がん」でしたが、死にざまは「大往生」だったとコロちゃんは思っていますよ。
さて、後に残されたコロちゃんですが、「子どもたちを1人前に育てる事業」には20年以上かかりましたが、これは妻と一緒に無事成果を上げた上で終了しています。
妻も「大往生」出来たのですから、コロちゃんもあとは続いて「大往生」するだけですよ。
今日は「大往生」をテーマに取り上げた機会に、最後はちょっとコロちゃんの内面を掘り下げて書いてみましたよ。
こんな「おじいちゃん」もいるんだと、気楽に読み流していただければ嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に触りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。

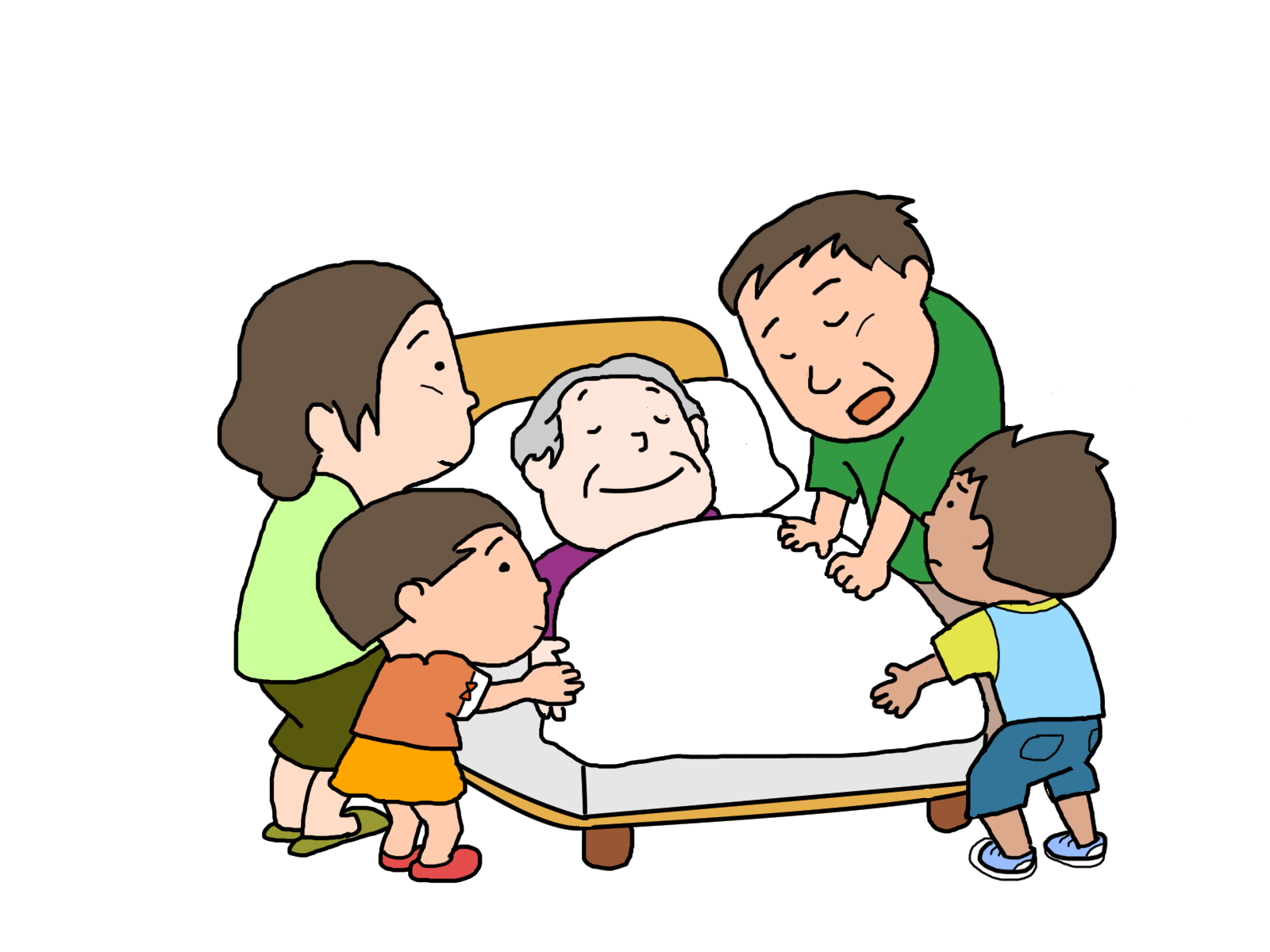




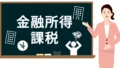

コメント