おはようございます。今朝もコロちゃんは、ワンコ散歩に出たとたんに「ハーハー、ハークション!」とくしゃみが出ましたよ。
ハ・・・ハ・・ (o>Д<)o・”.::・ハックショォンッ!!
このくしゃみは、最近毎朝の行事みたいになっていますよ。
家の中にいる時には平気なのですが、外に出るとたちまち「花粉症の洗礼」を受けてしまいます。そして、その影響は日中は1日中続くのですよね。
そりゃ、今のコロちゃんの生活で「家に閉じこもっている」なんてことは出来ませんよ。
だって「1日3回のワンコ散歩」がありますし、「洗濯物干し」も「お買い物」もありますからね。
ただ、昨夜の様子を見ると「夜はあまりくしゃみ・鼻づまり」はでなかったですね。やはり「家の中」では「花粉」がそんなに飛んでいないのかも知れませんね。
そんな「引きこもり願望」が強いコロちゃんが、今日は「新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたことを読んで」の【読書考】をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと:著:斉藤友彦:2025年:集英社新書と、新聞記者は文章が上手くないのか?」
☆「新聞記事は逆三角形だよと、バズる記事とは何か?」
☆「Z世代は文章をどう感じているのかと、デジタル記事の書き方指南は・・・本書を読んでね」
☆「コロちゃんの清貧ライフと読者様の数と、コロちゃんとガリ版印刷」

1.「新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと:著:斉藤友彦:2025年:集英社新書」
コロちゃんは、昨日の記事の「【生活考】あなたは「新聞」を取っていますか?」で、新聞購読者数が激減していることをお伝えしました。
ちょうどこの記事を書いている合間に、コロちゃんは「本書」の「新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと」を読んでいたのですよ。
そして「この本」を読んで、「新聞購読者数が激減している理由」の一端がわかったように思いましたよ。
皆さん、本書の「タイトル」を見て違和感を感じませんか?
(*´・д・)はて?
コロちゃんは最初見て「長いタイトルだな?」と思いましたよ。
普通の「新書のタイトルは10字程度」とされていますが、本書は「24文字」もあります。これを見てコロちゃんは、これって「ネット記事のタイトル方式なの?」と思ったのですよ。
確か「ネット記事は検索に引っかかるためにより多くの情報をタイトル詰め込むために長くなる」って聞いたことがありましたよ。
「本書のタイトル」は、その「ネット記事のやり方」を踏襲しているとコロちゃんは感じましたよ。
本書の著者は「共同通信社」の新聞記者です。1972年生まれの方ですから「団塊ジュニア世代」ですね。
コロちゃんよりは20歳以上年下の方ですよ。若っかいなー、50代の「バリバリの中堅世代」ですね。
本書の著者は、第1線の「共同通信社の新聞記者」から「編集デスク」を経て、「デジタルコンテンツ部長」として「ネット記事の配信」を担当なさっている方です。
出世なさっている優秀な方なのでしょう。ですから、「新聞記事とネット記事の違い」をその両方を知る「専門家の立場」から解析していますよ。
その「新聞記事とネット記事の違い」の1つが、本書の「長いタイトル」からも伺えますね。
コロちゃんは、「新聞」はもう60年間近く読み続けている「読者」です。
しかし、「記事作成の技術的側面」などは考えたこともありませんでしたから、本書を読むうちにグイグイ引き付けられて一気読みしちゃいましたよ。
さて、それでは「新聞記事とネット記事」とではどこが違うのでしょうか、簡単に本書の内容をご紹介してみますね。

2.「新聞記者は文章が上手くないのか?」
本書は冒頭から「新聞記者は文章が上手くない」とのエピソードから書き出しています。
これにはコロちゃんも驚きましたよ。だって「新聞記者」って毎日記事を書いている「プロ(専門家)」じゃないですか。
「新聞記者出身の人気小説家」も沢山いますよね。
コロちゃんがちょっと思い浮かべただけでも、「司馬遼太郎(サンケイ新聞)」「山崎豊子(毎日新聞)」「井上靖(毎日新聞社)」などがいらっしゃいますね。
それが著者は「新聞記者は文章が上手くない」と言うのですよ。
その理由として「新聞記者」は、「要点を簡潔に、コンパクトに、無駄なく書くように訓練されている」が、そのスタイルが「ネット配信」では読まれないというのですよ。
要するに「新聞記事で正しいとされている文章形式」と、「ネットで読まれる記事の文章形式」は違うというのですよ。
だから「新聞記者は文章が上手くない」となるのですね。
これって「新聞記事に特殊化した文章技術」になっているから、「長い文章(ネット記事)では必ずしもうまくない」という事なのでしょうね。
コロちゃんが「文章をカキコキ」し始めたのは2年前からですし、「訓練」などは全く受けていませんよね。
完全な「自己流」で、読み手のことなどまるで考えていない素人ですから、この「文章の書き方の指摘」は、実に新鮮に頭に沁みとおるように読みましたよ。
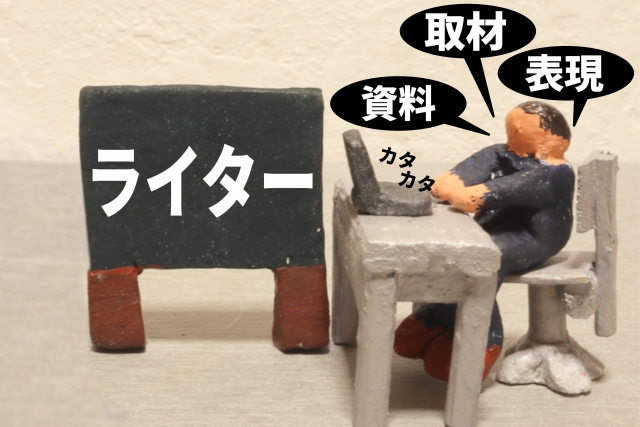
3.「新聞記事は逆三角形だよ」
まず「新聞記事」は「共同通信」の場合は、「長文で1200字がマックス」であるとしています。その点「ネット記事(著者担当の47NEWS)の1500~4000字」とボリュームが違います。
そして「新聞記事の書き方には1つのパターンがある」と言うのです。コロちゃんは新聞を読んでいて、そんなことを意識したことはありませんでしたよ。
つまり「最初の10~20行(1行11文字で100~200文字):リード」に「ニュースのエッセンスを詰め込む」書き方になっているというんですよ。
だから「忙しい時」は、この「リードだけを読んでも大体のことは理解できる」と書いていますね。
コロちゃんは、本書を読み終わった翌朝に「日経新聞」をざっと読みましたが、確かに「ほとんどの記事に10~20行のリードらしき項目」が記載されていましたよ。
そして、そのリードを改めてその目で見ると「記事全体のエッセンスが詰め込まれている」ことに気が付きましたよ。
(*。_。)⁾⁾ゥンゥン
だから「長い記事」は、最初の「出だし(リード)」に内容がギッシリ詰まっていて、その後は「説明・解説」になる「逆三角形(共同通信用語)」になるというのですよ。
しかし、その「新聞の書き方のパターン」が、「ネット記事」になると「通用しない(読まれない)」ということが本書が一番訴えているところですね。

4.「バズる記事とは何か?」
コロちゃんは書いていて、これは「ネタバレ」になるのかとちょっと不安になりましたよ。
だって「著者」が実際に「47NEWS」のネット記事を配信していて、「バズった記事」の特徴を懇切丁寧に紹介しているのですよ。
これって「著者が苦労しながら経験で得た職人芸の技術」じゃないの?
( ̄へ ̄|||) ウーム
こんなのを本に書いて広く知らせるのは・・・、目的は「読まれる良質なネット記事を拡げること」なのかなー?
σ( ̄^ ̄)はて?
もともと「新聞などマスコミのお仕事」は、「社会の木鐸※」って言われますよね。
(※社会の木鐸:世の中を教導し正すこと)
ただ最近では「マスゴミ」とも言われちゃったりすることもありますけれど、どんな在り方でも「読んでもらえなければ役割は果たせません」ね。
そして「新聞購読者数」は、年々減少の一途とたどっています。その中で「ネット記事化」を進めても、「新聞記事」のような良質の記事は、現実には読まれていない。
だから「著者」はあえて、「ネット記事をどのように書いたらならば読んでもらえるのかの技術」を公開したという事なのかも知れないと、コロちゃんは思いましたよ。
(゚∀゚ノノ”☆オーパチパチパチ
著者は「読まれる記事(バズった記事)」の要素を、下記の5つに分類しています。
◎「読まれる記事」
➀「共感や感動」
➁「ストーリー性」
➂「最新ニュースの関連記事」
④「見出しとサムネイルの結びつきの強さ」
⑤「コメントの盛り上がり」
うーむ、専門家はこんな風に分析するのですね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
もちろん、本書では上記の要素を一つ一つ具体的に指摘していますから、コロちゃんのような素人でも理解できますが、理解は出来ても実際に自分で書けるかというと・・・難しいですよ。
(*゚Д゚)φ))ナルホド
ただ、コロちゃんが文章を書き終えた後に、上記の点を頭に置いてチェックするようにして数年後まで続けることができたら、いくらかは文章が読まれやすくなるかもしれないと思いましたよ。

5.「Z世代は、文章をどう感じているのか?」
コロちゃんは、毎日ブログを書いていて、「読者」の事を考えたことはありません。というか、「読者」のことを考えている余裕がないというのが正直なところですね。
とにかく「毎日7000~9000字の原稿を書くこと」で精いっぱいで、余裕は全くありませんよ。だって「原稿カキコキ時間」を6~8時間を投入していますからね。
だけど、確かに「読者」がいないと「発信の意味」がないのも事実ですから、本書で「Z世代のネット記事の読み方」を興味深く読みましたよ。
「Z世代」というのは、「1992年から2013年頃」に生まれた世代です。2025年の現在では「12~33歳くらいの若者世代」ですね。
コロちゃんの子どもたちよりも、大分年下の若者世代ですね。
本書では、この「Z世代の方たち」に「ネット記事」を読んだ感想を書いています。以下でしたよ。
◎「Z世代がネット記事を読んだ感想」
➀「リードが情報量が多すぎて疲れる」
➁「最初から難しいと読まない」
➂「長い文章は読まない、読みたくない」
④「ニュースを他人ごととしか思えないから見ない、読まない」
著者は、この「感想」を聞いて「新聞記事の作り方」を全否定していると捉えて、「ネット記事」は「新聞記事」とは全く別の作り方をしなければ「読者」から見放されると考えていますね。
まあコロちゃんのブログ記事は、そもそも「硬い話題」ばかりですから、間違いなく「Z世代(12~33歳」には読まれないでしょう。
ん、誰ですか?「全世代に読まれていないよ」って聞こえましたよ。
(ノ°0°)ノ言わないでー!

6.「デジタル記事の書き方指南は・・・本書を読んでね」
さて、「新聞記事」と「ネット記事」との違いと、「Z世代の受け止め方」を読んだ後は、いよいよ「デジタル記事はどう書けば読まれるか」です。
これが「本書」で一番需要な部分でしょうね。だからコロちゃんは書きませんよ。そこをお知りになりたい方は、どうか本書をお読みください。
コロちゃんは、シッカリ読んで受け止めて、自分のブログ記事に生かせるところは受け入れてみますよ。
いやー、本書はおもしろかったですよ。
特に「新聞記事」がどのような構成で書かれているのかは、まったく知らない知識でしたし、今朝の新聞を読んでいても違った目で記事を読むことが出来ましたよ。
なお、本書「新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと」をお読みになりたい方は、下記のリンクからも購入できますよ。
もちろん、コロちゃんみたいに図書館からお借りするのも「あり」ですよ。
7.「コロちゃんの清貧ライフと読者様の数」
コロちゃんが、上記の本の著者の「斉藤智彦氏」の思いを拝察すると、やっぱり「若い方たちに世の中のことを知って欲しい」と考えていると思うんですよね。
だから「斉藤氏」は、ご自分が編集する「ネット記事」のページビューをどうやったら増やせるかを、深くお考えになったのだと思われますよ。
そうなると「コロちゃんのブログ」はどうでしょうね。最初は「読者数」を考えるような余裕はまったくありませんでしたよ。
そもそも最初は、「自分が発表出来るレベルの原稿が書ける」とは考えていませんでしたよ。
ただ、毎日新聞を読んでいて、いろいろ思うことはありましたから、それなりの「発信程度」ならできるかもと考えて書き始めたのですよ。
それが、もう最初のブログ投稿から「2年5ヵ月」ですね。「毎日更新」がよく続いたものだとわれながら思いますよ。
そこでちょっと「読者様の数」を見てみましょう。いくら気にしないといっても、ちょっとは気になりますよ。そこは、コロちゃんも「凡人」なのですよ。
コロちゃんは、現在「wordpress」と「note」の二つの媒体で「ブログ」を発表しています。その「読者様の数」は以下でしたよ。
◎「wordpress(コロちゃんの清貧ライフ)」
➀「表示回数※」
➁「過去1年間:1万2000回」
➂「過去1ヵ月: 900回」
④「いいね :1170回」
(※ページビュー数+スクリーンビュー数=表示回数)
◎「note」
➀「ビュー※」
➁「過去9ヶ月間: 1万回」
➂「過去1ヵ月間:1000回」
④「スキ :960回」
(※ビュー=ページビュー+タイムラインに投稿が表示された数)
おー、意外と読んでいただいていますね。
(o゚Д゚)オー
1日平均すると、「wordpress」で30回と「note」で30回程度と、合計すると60回の読者様のご訪問がありますよ。
それに「wordpress」での「いいね」が1170回、「note」での「スキ」が960回もいただいていますよ。
いやいや、この拙いブログがこんなに読まれているとは、ありがとうございます。今後も、これを励みにして、出来れば「毎日更新」を続けたいと思いますよ。

8.「コロちゃんとガリ版印刷」
コロちゃんが「原稿を書く」なんてことをしたことは、20代の頃に1度だけありましたよ。それは1970年代の頃でしたね。
当時のコロちゃんは、会社の労働組合の役員の方から「日刊紙」の作成を頼まれたことがあったのです。
もちろん当時は「コピー機」などありませんから、「ガリ版印刷」という機器を使用していました。今の若い方は絶対に見たこともない機器でしょうね。
この「ガリ版印刷」というのは、ロウが塗られた原紙をヤスリ版の上に置き、鉄筆で文字を「ガリガリ」と削り取るものです。
その音から通称「ガリ版印刷」と呼ばれていましたが、正式名称は「謄写版印刷」でしたね。
そのガリガリと「削られた文字痕」からインクが染みだして印刷となるものですが、作成には「鉄筆で字を削り取る作業」が必要となるのですよ。
それなりの「特殊な技術」が必要となるものでした。
当時のコロちゃんは、その当時「日刊紙」に初めて自分で書いた原稿を、ガリガリと書き込んで印刷したことを思い出しましたよ。
もう50年程前のことですから、原稿の内容は全く記憶に残っていません。どんなことを書いていたんだっけなー?
(。・_・?)ハテ?
しかし、当時のコロちゃんは「教育宣伝のセミナー」に参加したこともありましたから、たぶんそこで「原稿の書き方」なども学んでいたのでしょうね。
当時の「ガリ版印刷」というものは、ガリガリと原稿を書き終えたら、その後は「右手にローラー、左手は印刷する紙をめくる」という印刷作業を行なっていました。
「右手のローラー」には、印刷インクがべったりとついています。だから、印刷作業が終わると、あちこちがインクだらけになるような作業だったのですよ。
考えてみれば、コロちゃんがこのブログの原稿をカキコキする以前に原稿を書いたことがあったのは、この1970年代の20代の頃だけでしたよ。
あー、あと50代の頃に「ボーイスカウトのボランティアリーダー」を務めた時にも、少し原稿は書きましたね。
( ¯ O¯)アー
だから今回コロちゃんが「原稿」を書いたのはひさしぶりですね。現在のコロちゃんは、新鮮な気分で毎日「原稿」を書いていますよ。
今後は「テーマ」も、新鮮なものにチャレンジしたいと思いますので、どうかまたご訪問くださいね。
今日は「新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと」をコロちゃんが読んだ【読書考】をご紹介しました。
その後にこのブログの「読者様の数」と、気恥しい「コロちゃんの20代の思い出」まで書いてしまいましたよ。
コロちゃんは、いつもついつい「余計な道」に迷い込むことが多いのですよね。まあ、これも「原稿の彩り」とお考え下さいね。








コメント