おはようございます。昨日朝に「コロちゃんの歯が1本グラグラになった」とお伝えしましたが、午後に「歯科医院」へ急遽診察に行ってきました。
まったく困ったことに、「コロちゃんの左下の犬歯」がいきなり「グラグラ」と動くようになってしまったのですよ。
コロちゃんの歯は、ほとんど残っていて「現在も26本」が健在です。親知らずを除いた「歯の数は28本」ですから、抜いた歯は2本しかないのですよ。
「70代の平均残存歯は約20本」と言われていますから、「コロちゃんの歯」は成績が良いのですよ。
しかし、今回はいよいよ「もう1~2本」は抜くことになりそうだなと、コロちゃんは戦々恐々で「歯科医院」を訪ねましたよ。
そうしましたら「歯科医院の先生」は、「この歯(犬歯)が自然に抜けるのを待ちましょう。抜けたら隣の歯にブリッジをかけますから入れ歯になることはないですよ」とおっしゃったのです。
コロちゃんは、右下の歯の「歯周ポケット」が深くなっていて、ここがダメになったら「次は入れ歯です」と言われていたのですよ。
だから、今回の「抜けた犬歯の後はブリッジで」との歯科医先生の言葉には、嬉しくなりましたよ。
取り敢えず、歯根に薬を注入して「抗生物質の飲み薬」を1週間分受け取って帰ってきましたよ。
この歯は、もう「抜けること」は前提ですが、取り敢えず「入れ歯」にならずにすみましたから、コロちゃんはホッとしましたよ。
ε-(´∀`*)ホッ
そんな「安心コロちゃん」が、今日は「地方都市の物価が上昇しているよ」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「地方都市の方が物価が上がっているの?と、インフレ率は、大都市よりも小都市ほど高いよ」
☆「物価上昇率は小都市が高いが、物価水準は東京都が高いと、暮らし向きの生活意識を見てみよう」
☆「地方都市から不満が爆発するかも?と、コロちゃんと本屋さん」

1.「地方都市の方が物価が上がっているの?」
コロちゃんが、朝新聞をバサバサ読んでいると「最賃賃上げ 地方発のうねり/100万未満都市 インフレ率高く」との見出しが目に入りました。
これって「最低賃金の記事」ですよね。コロちゃんは「最低賃金」には、普段から注目していましたが、この見出しで気になったのは、後段の「100万都市以外インフレ率高く」の方ですよ。
コロちゃんは、何となく「全国で一番物価が高いのは東京都」とのイメージが頭にありましたので、「地方都市」ではそれよりも「物価上昇率は低い」との思い込みがあったのです。
ところがこの記事を読むと、何と「消費者物価の総合指数」を7月について地域別にみると、以下だったというのですよ。
◎「消費者物価指数:地域別上昇率:7月:5年前比」
①「東京都区部」
・「10.8%上昇」
②「人口15万人以上100万人未満の中都市」
・「11.6%」
③「人口5万人未満の小都市B・町村」
・「12.8%上昇」
えー、一番「物価が上昇」しているのは「③人口5万人未満の小都市B・町村の12.8%上昇」なのー!
Σ٩(๑⊙Δ⊙๑)۶え〜〜っ
コロちゃんは、ビックリしましたよ。コロちゃんが住んでいるのは「埼玉県の地方都市」ですが、上記の記事の枠(①~③)には入っていませんでした。
だってコロちゃんの住む自治体は、「③人口5万人未満の小都市B・町村」よりは、ギリで上回っている人口ですから、たぶん「小都市A」に分類されているのでしょう。
これは、ちょっと後で調べてみますね。
どうやら今回の「物価上昇率」は、「東京都」より「地方都市」の方が高い実態が生じているみたいですね。
この記事では、「過去最高の伸びの最低賃金(1121円)の背景」に、「地方で働く人が物価上昇が直面」し、「都市部との賃金格差に人材流出」が起きていることがあると記載していますよ。
そこでコロちゃんは、この「地方都市の物価上昇率の実態」をちょっと調べてみようと思いましたよ。次にその様子を書いてみますね。
なお、この「日経新聞」の「最賃賃上げ 地方発のうねり/100万未満都市 インフレ率高く」の見出しの記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
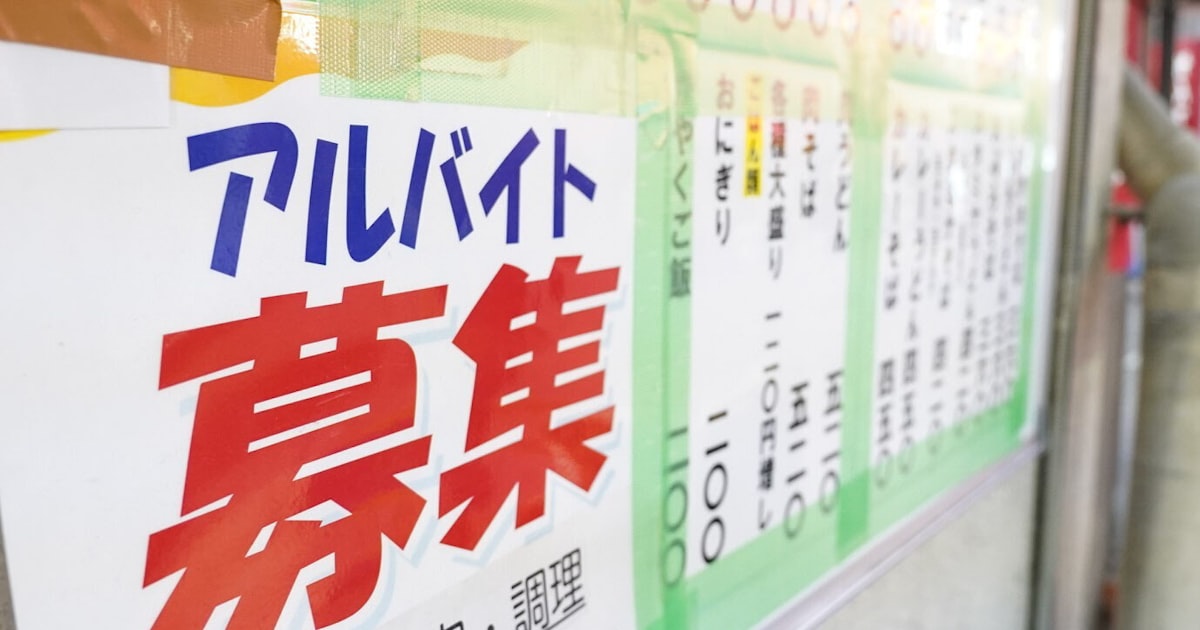

2.「インフレ率は、大都市よりも小都市ほど高いよ」
さて、上記の記事の中で「消費者物価上昇率」が、「人口5万人未満の小都市B・町村の12.8%増」と「東京都区部の10.8%増」よりも高いのに驚いたコロちゃんでしたが、さっそく調べてみましたよ。
このデータは、政府の「e‐Stat統計で見る日本」の中に記録されていました。
ただこれは、「対前年同月比」ですね。記事の「5年前対比」とは違っていますよ。以下でしたよ。
◎「消費者物価指数:2025年7月:2020年基準」
①「大都市」
(政令指定都市〈人口50万人以上〉及び東京都区部)
・「総合指数 : 111.9」
・「前年同月比:3.1%増」
②「中都市」
(人口15万人以上100万人未満)
・「総合指数 : 111.6」
・「前年同月比:3.0%増」
③「小都市A」(コロちゃんはここ)
(人口5万人以上15万人未満)
・「総合指数 : 112.3」
・「前年同月比:3.2%増」
④「小都市B・町村」
(人口5万人未満)
・「総合指数 : 112.7」
・「前年同月比:3.2%増」
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003427113
(出典:e‐Stat統計で見る日本より:9月13日利用)
ふーむ、冒頭の記事で「消費者物価指数を5年前と対比した」のは、その方が「③小都市B・町村」の「物価上昇率の高さ」が際立って見えてくるように工夫したのでしょうね。
( ̄へ ̄|||) フーム
ただ、上記を見ても「①大都市の111.9」よりも、規模が小さい都市ほど「物価上昇率の総合指数」は高く出ていますよ。
一番小さい規模の「④小都市B・町村(人口15万人以上100万人未満)」は、「総合指数が112.7」と一番高くなっています。
コロちゃんの住んでいる「③小都市A(人口5万人以上15万人未満)」は、「総合指数が112.3」と真ん中でしたよ。
どうやら、今回の「インフレ率」は「小都市」ほど高いという実態があるようですよ。これにはコロちゃんもビックリしましたよ。
o(゚Д゚)っホント?

3.「物価上昇率は小都市が高いが、物価水準は東京都が高い」
わっかりにくいなー。
上記の「都市分類」では「小都市ほど物価上昇率が高かった」のですが、「都道府県別の物価水準」だと「東京都の物価水準」が一番高いのですよ。
この違いは「物価上昇率」と「物価水準」の違いですよ。
全国の「都道府県の物価水準」の「高い都道府県と低い都道府県」を書き出しますね。下記でしたよ。
◎「2024年:都道府県別(物価水準):平均消費者物価地域差指数:総合」
(全国平均=100:小数点以下切り捨て)
〇「物価水準が高い都道府県」
①「東京都 :104」
②「神奈川県:103」
●「物価水準が低い都道府県」
❶「鹿児島県:96」
❷「群馬県 :96」
https://www.stat.go.jp/data/kouri/kouzou/pdf/g_2024.pdf
(出典:総務省統計局 消費者物価地域差指数より:9月13日利用)
うーん、やっぱり「東京都区部(23区)」は「物価水準が全国1高い」ですよね。一番「暮しにくい都市」みたいですよね。
(´ヘ`;)ウーン
それでも「所得が高い」のも、また「東京都」なのでしょうから一概に「暮しにくい」とは言えないかも知れませんよ。
ただ、この「消費者物価地域差指数」をよく見ると、以下のこともわかりましたよ。
◎「10大品目別の物価水準が高い都道府県」
①「食料」
・「沖縄県が最も高い」
②「光熱・水道」
・「北海道が最も高い」
③「家具・家事用品」
・「福井県が最も高い」
➃「被服・履物」
・「石川県が最も高い」
⑤「保険医療」
・「宮城県が最も高い」
⑥「教育」
・「大阪府が最も高い」
https://www.stat.go.jp/data/kouri/kouzou/pdf/g_2024.pdf
(出典:総務省統計局 消費者物価地域差指数より:9月13日利用)
ふーん、「②北海道が光熱費が高い」のはわかりますよね。寒い地方ですからね。
( ̄へ ̄|||) フーン
だけど、それ以外の「①食料の沖縄県」や「③家事・家具洋品の福井県など」は、ちょっと理由が分かりませんよね。
ただ、この記載には「これらの背景には、本土からの輸送コストの高さや、地理的条件による流通効率の違いなどが考えられる」と書いていますよ。
そして「結論」としては、下記の記載がありましたよ。
「地方は生活コストが安いという通説については、確かに東京都では住宅コストが突出して高(い)・・・、地方でも地理的条件などによって必ずしも物価水準が低いとは限らない」
なるほど、「物価水準」は「品目」によって「地域差もある」というのですよね。そして「地方」が「物価水準が低いとは限らない」と確かに書いていますよ。
コロちゃんが、「前項」と「この項」の結果をまとめると、「物価水準も所得水準も高い都市部」があり、また一方に「急激に物価が上がっている小都市群」があると思いましたよ。

4.「暮し向きの生活意識を見てみよう」
2022年の後半以降の、ここ3年間で「物価が上昇している日本」ですが、皆さんの「暮し向きの生活意識」を見てみましょう。
「日本銀行」では、毎年、年に4回「生活意識に関するアンケート調査」を行なっています。
直近の調査は、7月14日に発表されています。ここから「物価」と「生活防衛」を頭において「国民の声」を聴いてみましょう。
◎「Q.現在の暮らし向きは?」(小数点以下切り捨て)
①「ゆとりが出てきた : 3%」
②「どちらとも言えない :34%」
③「ゆとりがなくなって来た:61%」
https://www.boj.or.jp/research/o_survey/data/ishiki2507.pdf
(出典:日本銀行 生活意識に関するアンケート調査より:9月13日利用)
あー、「③ゆとりがなくなって来たが61%」ですよ。
( ̄Д ̄*)アー
コロちゃんもこの中の1人に入りますね。だんだんこれらの人が増えてくるような気がしますよ。
次にこの「暮し向きのゆとり」が過去にどのように推移してきたのかを見ておきましょう。
この「過去の暮し向きのゆとりの推移」をみるには「暮し向きD.I」というのを使います。この「計算方式」は、「①ゆとりが出てきた」から「③ゆとりがなくなって来た」を引いた数値です。
わかりやすいように、下記にこの「方程式」を書きますね。以下ですよ。
◎「暮し向きD.Iの計算式」
「①ゆとりが出てきた 」ー
「③ゆとりがなくなって来た」=
「暮し向きD.I」
上記の「暮し向きD.I」では、「数値のマイナスが大きい」ほど「ゆとりがない」となります。
この数値を「物価が上がり始めた2022年の10月から現在までの変化」を見てみましょう。
もう皆さんはお忘れになっているかも知れませんが、「日本の物価」は「1990年代の後半から四半世紀(25年間)」にわたってほぼ横ばいに進んでいたのです。
「物価の上がらないニッポン」だったのですよ。
ところが、その後「2021年11月以降」に急激に上昇しているのですよ。
つまり下記の、「➀の2021年9月が物価が上がり始めた時点」なのです。
◎「暮し向きD.I」
(マイナスが大きい方がゆとりがない)
①「2021年9月:ー29.5」(物価上昇開始)
②「2022年9月:ー46.7」
③「2023年9月:-54.3」
➃「2024年9月:ー47.4」
⑤「2025年6月:ー57.2」
(出典:日本銀行 生活意識に関するアンケート調査より:9月13日利用)
おー、やっぱり「物価上昇が始まる直前の2021年9月」の「暮し向きD.I」が、一番「マイナスが小さい(暮らしやすい)」ですよ。
( ̄o ̄)oオー
それ以降の「物価上昇」が始まってからは、毎年「暮し向きD.I」が悪化していますね。コロちゃんには、年々「ゆとりがなくなっていく家庭」が増えて言っていく様子が見えるようですよ。
どうやら、この「丸3年間を超える物価上昇」は、今後もずっと続きそうですよ。誰かが止めてくれると嬉しいとコロちゃんは願っていますよ。

5.「地方都市から不満が爆発するかも?」
ここで、ちょっとコロちゃんの考えを書いて見ますね。
今日のテーマは、「地方都市の方が物価が上昇しているって」を調べながら考察してみました。
データによると、「物価水準は大都市部が高い」ですけれど、「物価上昇率(インフレ率)」は「小規模都市」になるほど「高くなる」と分かりましたよ。
これって「生活が苦しくなる」のは「小都市部に住む方たち」の方ですよね。
(コロちゃんが住んでいる地域は小都市Aです)
「大都市部」では「物価水準も高い」ですけど「所得も高い」となっているのでしょう。
それに何よりも「生活が苦しい」と感じるのは、「物価の水準」よりも「前年比で物価が上がること」です。
ここまで見てきたところでは、「小都市部」ほど「物価上昇率(インフレ率)が高い」でした。
この傾向は、おそらく「構造的なもの」でしょうから、今後も「同じ傾向」を進むと思われます。
そうなると、上記の「日銀アンケート」で見てきたように、「ゆとりがなくなって来た世帯」が最初は「小都市群」で激増するのではないでしょうか。
つまり「田舎の都市部」から、「不満が爆発する」のではないかと思ったのですよ。
コロちゃんは、今後の「日本社会」で「ゆとりがなくなって来た世帯の増加」が「政治の安定性を掘り崩す」と思いましたよ。
コロちゃんは、「かつての記憶」が頭をよぎりましたよ。かつて「総理大臣1年程度で使い捨て」と言われた時代があったのです。下記ですよ。
◎「総理大臣の任期が1年程度だった時代」
①「2006年:安倍第1次内閣」
・「在任日数:366日」
②「2007年:福田康夫内閣」
・「在任日数:365日」
③「2008年:麻生太郎内閣」
・「在任日数:358日」
④「2009年:鳩山由紀夫内閣」
・「在任日数:266日」
⑤「2010年:菅直人内閣」
・「在任日数:452日」
⑥「2011年:野田佳彦内閣」
・「在任日数:482日」
へー、あらためて数えたら「在任1年程度の総理大臣が、2006年から2011年にかけて続けて6人」もいらっしゃいましたよ。
( ¯ㅿ¯)へー
コロちゃんも、実際に1人ひとり数えたことなかったのですが、どんな「優秀な政治家」であっても「1年間」じゃ、大したことは出来ませんよ。
それに、上記の方々はとても「優秀な政治家」とは・・・・ごにょごにょ・・・。
ゴニョゴニョ…(ノ゚д゚(; ̄Д ̄)
ゲフンゲフン、・・・とにかく、今後の「政治は混乱する」とコロちゃんは思いましたよ。この予測が外れてくれることを祈りますけれどね。

6.「コロちゃんと本屋さん」
さて、後は最後の「コロちゃん話」ですよ。今日は「本屋さんの話」です。
上記で「総理大臣の任期が1年程度」だった、「総理1年で使い捨て」が起きたのは2000年代のことでした。
この最中の「2003年」に、コロちゃんにとってちょっとショックな話を聞いたことがありました。それは「池袋西口」にあった「芳林堂書店の閉店」です。
この「芳林堂書店」は、「池袋駅西口」から歩いて5分ぐらいのところにあり、確か8~9階建てぐらいのビルで、全館が書店だったのです。
コロちゃんは、1970年代の20代の頃からこの「芳林堂書店」を愛用しており、毎月1回は必ず覗いて「新刊書」を漁っていましたよ。
いつもこの書店に行くと、まず1階の「新刊書籍売り場」を一通り見て回り、その後は2階から順に上へと昇っていったのですが、毎回ここの書籍売り場には2~3時間は入り浸っていましたよ。
確か「5階の奥にいつも探していた書籍売り場」がありましたよね。あそこは「何売り場」だったかなー? 「歴史や社会学」だったかも知れませんね。
σ( ̄^ ̄)はて?
今でも覚えているのは、毎回「立ち読み」で「腰が痛くなった」ことです。何しろ「貧乏青年のコロちゃん」でしたから、いつも買うのは「1冊か2冊」がせいぜいでした。
そこであとは「全部立ち読みしていた」のですよ。「斜め読みの技術」を習得したのもこの時代でしあね。
当時のコロちゃんは、「新刊は立ち読み」で、「出版年が古い本や小説は図書館で借りる」ことにしていましたよ。
そして「気に入った本」を厳選して購入していましたね。
コロちゃんは、一時は「豊島区の千早町のアパート」に住んでいた時期もあったのですが、このアパートまでの交通手段は、この「芳林堂裏のバス停」から出発するバスだったのです。
そんなこともあり「本屋さんの思い出」となると、この「池袋の芳林堂」が最初に頭によぎりますよ。また若かった青年コロちゃんの姿も懐かしく思い出しましたよ。
ここが「閉店する」と聞いたのは2003年でしたが、コロちゃんにはちょっとショックでしたよ。
コロちゃんにとって「芳林堂書店」は、「青年コロちゃんの時代の象徴的記憶」ですよね。
当時の青年コロちゃんは、お金こそ持ってはいませんでしたが、「野心と未来への希望」は満々と溢れるほど持っていましたよ。また「読書と知識」への渇望もありましたよ。
えっ、「今のコロちゃんが当時の青年コロちゃんに会えたならば、何て声をかけるのか?」ですか?
(o゚Д゚)エッ
うーむ、そうですね・・・「野心は捨てて、石橋をたたいて渡れ?」、いやいや、そんなことは絶対に言いいませんよ。
( ̄へ ̄|||) ウーム
むしろ、「悪くても清貧コロちゃん程度にはなれるよ」。だから、「もっと徹底的に悔いが残らないようにやりたいことをやれ」と言ってやりたいですね。
何と言っても「人生は一度しかありません」からね。コロちゃんは、「やらずに後悔する」よりも「やって後悔する」方を選びたいと常々思っていましたよ。
皆さんはいかがお考えでしょうか。若かった青年コロちゃんの上記の生き方を、笑いながら読んでいただければ嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします。
(^_^.)
おしまい。








コメント