おはようございます。昨日コロちゃんが「近所のスーパー」にお買い物に行くと、入り口を入ってすぐの「野菜コーナー」に「レタス198円」とありました。
やすっ!
∑(⊙∀⊙)ファッ
確か「レタス」は、1月には400円ぐらいで、2月には300円ぐらいでしたから、ようやく100円台の198円に下がってきましたね。
コロちゃんは、毎食「野菜サラダ」を食べていますから「レタス・キャベツの値段」はよく覚えているのですよ。
しかし、コロちゃんがおやつに食べている「壊れせんべい」なんかも、昨年の初めごろには190円台だったのが、いまでは250円ですからね。
まったく「物価上昇」はコロちゃんの「清貧ライフ」の天敵ですよ。何か、だんだん「主婦」のようになってきたコロちゃんでしたよ。
今日は【読書考】ですよ。「日本経済の死角を読んで」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「日本経済の死角:著:河野龍太郎:2025年:ちくま新書と、失われた30年の戦犯は誰だ?」
☆「やっぱり戦犯は大企業経営者たちだよねと、コロちゃんと夜の新宿歌舞伎町」

1.「日本経済の死角:著:河野龍太郎:2025年:ちくま新書」
コロちゃんは、以前から「日本経済」のあれこれに興味をもっていました。このブログでも【経済考】の記事が多いですね。
それでいつも「一般向けの経済書」などを読んでいるのですが、今日ご紹介する本は「コロちゃんでも理解できる失われた30年の原因究明」の本ですね。
この著者の「河野龍太郎氏」は、「民間エコノミスト1位」を何度も取られている方のようです。コロちゃんも高く評価しており、以前著書の「成長の臨界」を読んだこともあります。
ただ、本書は内容は「一般向け」とは言っても、ところどころに「専門知識」がちりばめられていますから、容易ではありませんね。
コロちゃんは、以前「次男一家家長様」からこの「河野龍太郎氏」の「YouTube動画」の視聴を勧められて見ましたが、なかなかわかりやすい動画でしたよ。
その動画は「河野龍太郎氏と経済ジャーナリストの後藤達也氏の対談動画」です。内容は「本書」の内容と同じ「日本経済の停滞の理由」です。
下記に、その「YouTube」の「日本経済を停滞させた真の元凶とは?」のリンクを貼っておきますので、こちらを視聴の上で本書を読むと、より理解が深まると思いますよ。


2.「失われた30年の戦犯は誰だ?」
最近になって「日本経済の失われた30年の謎を解こうとする経済書」が、次々と出版されています。コロちゃんが最近このブログで取り上げた本には、以下がありましたよ。
◎「失われた30年の謎を解く経済書」
➀「日本の経済政策(失われた30年をいかに克服するか):著:小林慶一郎」
➁「物価を考える:著:渡辺努」
③「日本経済の故障箇所:著:脇田成」
上記の3冊の内容の「失われた30年の戦犯」は、それぞれ「企業の内部留保説」や「海外投資の増加説」など、一部は重なるところもありましたね。
コロちゃんは、それらを読んで「はて?どれが主犯なの?」と思っていましたよ。
だって、どの本も「大学教授」が書くだけあって、それらの理由はどれも説得力があったのですよ。
だからコロちゃんは、「経済学者の説」が時間の経過とともに「収斂して主犯が確定される」のを待っていたのですね。
そんな時に「本書:日本経済の死角(著:河野龍太郎)」を手に取ったというわけですよ。
なお、上記した「失われた30年の謎を解く経済書➀➁➂」の内容を紹介したコロちゃんのブログ記事を読んでみたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

3.「戦犯は大企業なの?」
さて、やっと「本書」の内容に入れますね、ここからが紹介になります。「本書」は、冒頭に「実質賃金の怪?」と書き始めています。
「著者」は、よく「大企業経営者」から、「日本は生産性があがっていないから賃金も上がらないんだよ」と言われるそうなのですよ。
それに対して「著者」は、ハッキリと「それは間違いですよ」と言葉を返しているそうなのですよ。その「理由」は以下ですよ。
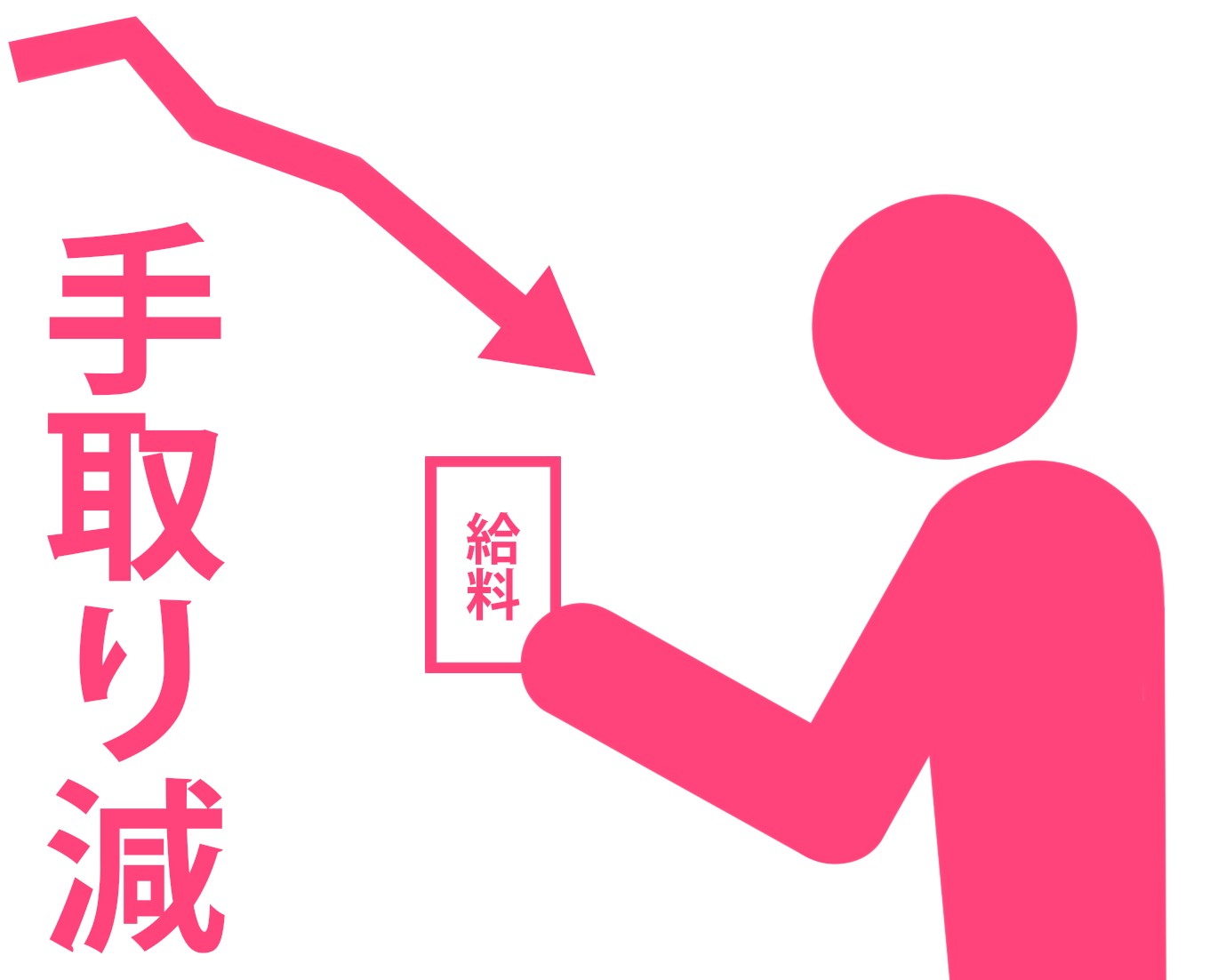
➀「生産性は3割上昇しているのに、実質賃金は3%の下落だよ」
著者の説明は、以下の通りでした。
「日本は1998年~2023年の四半世紀で、時間当たり生産性は3割上昇したが、時間当たり実質賃金は3%下落でした」
この期間(1998年~2023年)の他国との比較は以下です。
◎「時間あたり生産性と実質賃金:1998~2023年」
➀「日本」
・「生産性:30%上昇」
・「実質賃金 :-3%」
➁「アメリカ」
・「生産性 :50%上昇」
・「実質賃金:25%上昇」
③「ドイツ」
・「生産性 : 25%上昇」
・「実質賃金:15%弱上昇」
④「フランス」
・「生産性 : 20%上昇」
・「実質賃金:20%弱上昇」
あー、確かに「実質賃金が下がっているのは日本だけ」ですね。
( ¯ O¯)アー
上記のように「①日本」では「生産性が30%上昇」しているのに「実質賃金は-3%」と低下していますが、「②アメリカ」は「生産性50%上昇」と「実質賃金25%増」となっています。
また「③ドイツ」でも「④フランス」でも、「アメリカ」ほどではありませんが「実質賃金」は上昇していますね。
うーむ、確かにこれを見ると、「日本」だけが「生産性」は上昇しているのに、「実質賃金」は逆にマイナスに落ちていますね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
これを見せられれば「大企業経営者」も言葉を失いますね。
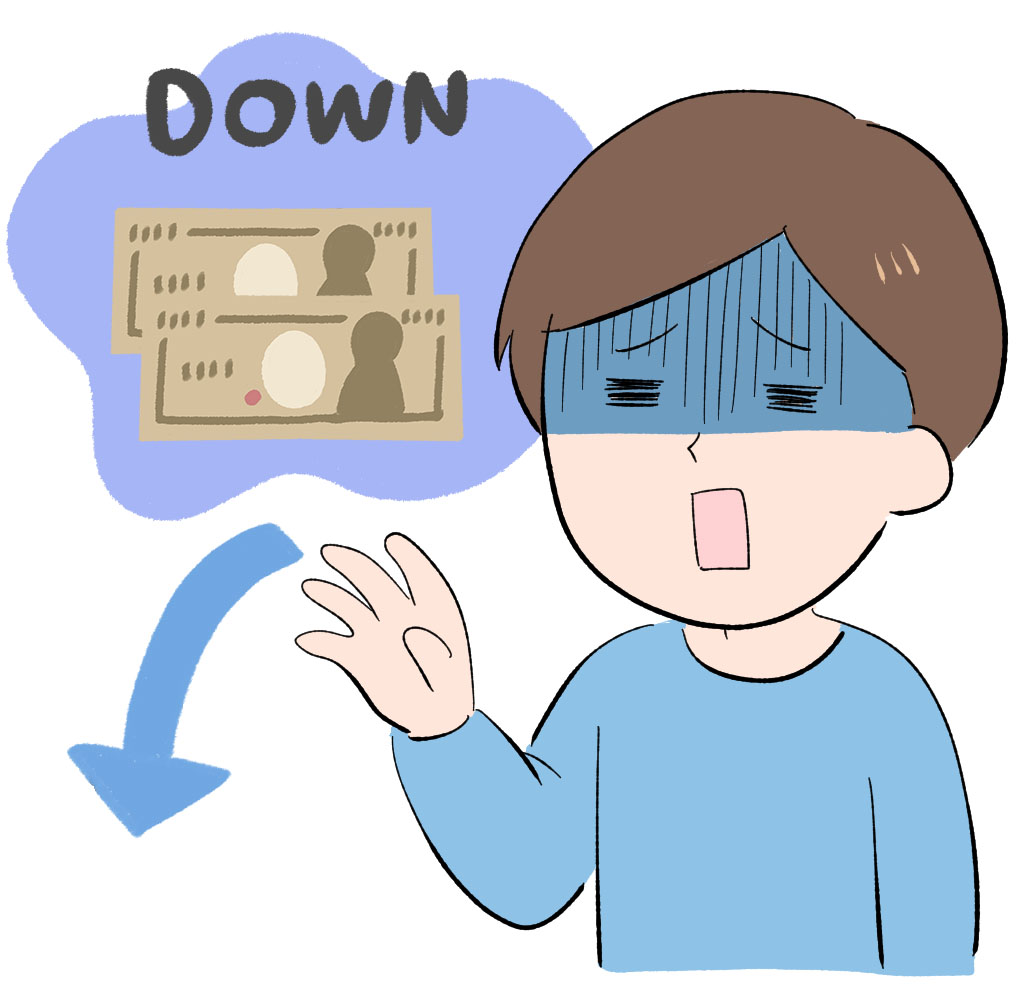
➁「大企業は儲かっても貯めこんでいるよ」
この「日本」だけが、ここ四半世紀の「実質賃金がマイナス」になってしまった理由として、著者は「大企業」が儲かっても賃上げに回さずに「内部留保」として溜め込んだことを指摘しています。
以下ですね。
◎「利益剰余金(内部留保)の推移」
➀「1990年末: 130兆円」
➁「2012年度:300兆円超」
③「2022年度:550兆円超」
④「2023年度:600兆円超」
●「過去10年の利益剰余金(※)は年平均27兆円増加、2023年度は50兆円増加」
●「雇用者報酬は300兆円程度、1%の賃上げ原資は3兆円となる」
●「現在の賃上げのベア3%は、利益剰余金の増加に比べるとまだまだ慎ましい」
(※利益剰余金とは内部留保のことです)
上記の●を読むと、「利益剰余金(内部留保)」は過去10年間の間、年平均27兆円もあったのに、2000年以降は長い間「ベアゼロ」で「1%(3兆円)」も出さなかったのですよ。
その「内部留保が増えた結果」起きてしまったことは、以下です。
❶「生産性が上がっているにもかかわらず、実質賃金を低く抑え込むから個人消費が低迷」
❷「(消費低迷で)企業は国内で売り上げが増えないから、国内の投資が抑えられる」
❸「投資が抑えられて、経済成長率が低迷した」
➍「企業が実質賃金を抑えることが巡り巡って自らの首を絞める合成の誤謬が起きている」
上記の結果、著者は「日本の長期停滞の元凶」を、「儲かっても溜め込んで、賃上げにも人的投資にも消極的な日本の企業(主に大企業)」と見ています。
コロちゃんは、「BNPパリバ証券会社経済本部長の著者」が、ここまで「大企業の内部留保」を糾弾して大丈夫なのかなと、思わず心配してしまいましたよ。
だけど「説得力がある内容だ」とも思いましたね。

③「超低金利政策は正しかったのか?」
本書では「超低金利政策」についても言及しています。この「超低金利政策」というと「アベノミクス」ですよね。
「低金利政策」には、企業がお金を借りやすくする効果がありますが、そもそも「企業部門の内部留保」は上記で見たように潤沢です。
むしろ本来「利上げ」によって避けられたはずの円安を招来し、「実質購買力を大きく損なった」と厳しい評価をしていますね。
そして「ここまで家計を犠牲にしているのだから、個人消費が回復しないのは当たり前」と喝破しているのですよ。
コロちゃんは、ここまで厳しく断言した本は、あまりなかったような・・・?
( ̄へ ̄|||) ウーム
いやいや断言というか「言い方がキツイ?」。だけど、この方がわかりやすいですよね。
そうなんですよ、この本は巻末の言葉で「編集者のアドバイス」で、文末を「ですます調」に変えたと書いていますが、「講演録」みたいで読みやすいのですよ。

④「内部留保を貯めこんだわけは?」
著者は「内部留保を溜め込んだ大企業」を厳しく指摘するだけではなく、その理由もちゃんと書いていますよ。
一応バランスをとっているなとコロちゃんは思いましたよ。下記ですよ。
◎「守りの経営が定着した理由は経済危機の連鎖」
➀「1990年代初頭のバブル崩壊」
➁「1997~1998年の金融危機とアジア通貨危機」
③「2001年のドットコムバブル崩壊」
④「2008年のグローバル金融危機」
⑤「2009年以降の欧州金融危機」
⑥「2011年の東日本大震災」
⑦「2022年のコロナ危機」
ざっと、上記の「日本経済の危機」が続いたことにより「攻めの経営の経営者は損失を出し引責辞任」して、「守りの経営者のみが任期を全うした」としています。
それで、その残った経営者たちの「成功体験」から、すっかり「内部留保を溜め込む経営」になってしまったとしていますね。
また、コロちゃんが本書を読んで「興味深い視点だ」と感じたのは、本書で「コーポレートガバナンスの罠」と書いている内容です。
いわゆる「コーポレートガバナンス」は、「会社は株主のもの」という価値観で語られる場面が多いですが、「本書」では「非正規雇用の拡大」とのつながりを指摘しています。
コロちゃんが勝手に纏めてみます、下記ですね。
◎「メインバンク崩壊による経営の選択」
➀「1990年代の末の金融危機でメインバンク制が崩壊」
➁「危機時に助けてくれるメインバンクを失った企業は。内部留保を増やして危機時に備えた」
③「長期雇用を維持するために非正規雇用を増やした」
本書では「日本を代表する経済学者の故青木正彦氏」が「メインバンク制が日本の安定的な経営と長期雇用を支えており、メインバンク制が崩壊すると長期雇用も崩壊する」と予言していたとしています。
それの予言は、現在外れているわけですよね。
その理由を、著者は「正社員の長期雇用を維持するために、正社員の実質賃金を抑え込むとともに、非正規雇用を生み出した」としているのですよ。
要するに経済学的には「本来ならばメインバンク制が崩壊したならば長期雇用も崩壊するはず」なのですよ。
それが、どうしても「長期雇用を維持したかった経営者」は、「賃金抑制」と「非正規雇用の拡大」で「内部留保を溜め込むこと」で「メインバンク制」の代わりにしたと言っているのですよ。
ここだけ見れば「大企業の内部留保の溜め込み」は、それなりの「存在理由」があることになりますね。ただ「守銭奴だ」とだけは言えませんね。
コロちゃんは、「内部留保」が「強欲資本主義」の表れではなく、「長期雇用を維持したい経営者の意思」から生まれたとは、考えてもいなかったですよ。
だけど、その結果「日本経済」の成長率が上がらなくなってしまったとは、誰も考えなかった結果だと思いますよ。
いわゆる「合成の誤謬による想定外の結果」となるのでしょう。だからと言って「大企業経営者の免罪になる」とはコロちゃんは思いませんけどね。
なお、ちょっと関係のない話ですけれど、コロちゃんはこの「合成の誤謬(ごびゅう)」という言葉を、どういうわけか「合成の誤謬(ごびょう)」と憶えていたのですよ。
だけど何回パソコンで打ち込んでも出てこないので、おかしいなー?となり、やっと気が付きましたよ。コロちゃんは70代で1つ新しい知識を得ましたよ。
( ◍´罒`◍)ゞエヘヘポリポリ

⑤「賃金と物価の好循環と賃金とインフレのスパイラル」
著者は「賃金と物価の好循環」という言葉に「強い違和感を持つ」と言っています。それは「世界的には賃金とインフレのスパイラル」となっているからだそうですね。
コロちゃんは、前者の「賃金と物価の好循環」には何かポジティブなイメージを感じますが、後者は逆ですよね。しかし「経済現象」としては同じものですね。
「賃金とインフレのスパイラル」との言葉には、「インフレに追いつかない賃金」や「インフレに翻弄される低所得者」が思い浮かびますね。
著者は「円安インフレ」が、2022年以降に政権支持率の低下をもたらし岸田政権の退陣となったことや、2024年の衆議院選挙で自民・公明党の連立政権が過半数を失ったことに繋がったと見ていますね。
そして、「危機のマグマは噴出し始めている」と「実質賃金の低迷を放置したままでは、安定していたはずの日本の政治が液状化する恐れがある」と危機感をあらわにしています。
コロちゃんも同意しますよ。とにかく「賃金と物価の好循環の輪」については、日本の社会では「その輪の外にいる方たち」が多すぎますよ。
コロちゃんのような「年金老人」もそうですけれど、多くの「非正規雇用者」も「輪の外」ですよ。
著者は「まず実質賃金を上げろ」とおっしゃっていますが、コロちゃんは「物価を上げないでくれ」と言いたいですよ。

⑥「長期雇用制をどう考えるのか?」
次々と本書の内容をご紹介しましたが、きりがありませんので、あと一つ「長期雇用制」についてを見ておきましょう。
著者は「企業の長期雇用」についてガタが来ているとはしていますが、「欧米のジョブ型雇用が代替え案になるとは思わない」と書いています。
むしろ「アメリカ型のジョブ型雇用」をそのまま導入したら、「一発屋とゴマすり屋が跋扈する」とまで言っているのです。
だから「日本企業は早い選抜をするべき」だと推奨していますね。企業内で課長・部長に昇格する年齢層を下げろというのですよ。
著者は「複数の上司の目で時間をかけて評価できる」と、日本企業の現在の「長期雇用制」を高く評価しているようですよ。

⑦「収奪的な社会へ変貌してしまったのか?」
これで最後です。著者は、「日本社会と日本企業」が「収奪的な社会・企業」に変貌していくのではないかとの懸念を訴えています。
これは「正社員の賃金を低い水準におさえ込んだこと」だけでなく、本来は「増税で賄うべき財源」を「現役世代の社会保険料の引き上げ」で充当していることも含まれています。
また「非正規雇用の低い賃金」もそうでしょうね。これらはまさに「富の収奪」ですね。
著者は「ユヴァル・ノア・ハラリ」が「ホモ・デウス※」で警鐘を鳴らした「ディストピア」が到来するのではないかと懸念を訴えています。
(※ホモ・デウス:未来に大半の人類はアルゴリズムの奴隷となるとした本)
そこで「著者」は「包摂」という概念の社会制度を提起しています。
「野生化している収奪的なイノベーション」は、人間の社会制度を掘りくずしているから、それを変える必要があると最後に語ってますが、そこは皆さんが本書を読んでいろいろお考え下さい。
コロちゃんが、本書の中でちょっと興味を持った点には、次の「アビジット・バナジー(ノーベル経済学賞受賞者)」の言葉がありましたよ。
「経済成長を促すメカニズムはまだよくわかっていない。とりわけ(先進国のような)富裕国で再び成長率が上向きになるのか、どうすれば上向きになるのか、ということはハッキリ言って謎である」
(世界最高峰の経済学教室より)
うーむ、経済学の本を読んでいくと、最後は「哲学」や「人間のあり方」などに進むことが良くあるんですよね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
本書も「副題」は、「収奪的システムを解き明かす」となっていますから、現状はダメよといってはいますが、それではどうするべきかまでは本書ではあまり記載されていませんね。
ただ、確か著者の「成長の臨界」には書いてあったように覚えていますよ。本書では「社会連帯税の導入(2~3年に1度0.5%の増税)」とだけ記載がありましたよ。
ざっと、上記のような内容でしたが、充分なご紹介とはとても言えませんので、ちょっとでもご興味をお持ちの方は本書を是非お読みくださいね。最後に本書のリンクを貼っておきますよ。

4.「やっぱり戦犯は大企業経営者たちだよね」
さて、とても興味深いテーマでしたから、コロちゃんは一気読みしちゃいましたけれど、本書のテーマは「日本企業の収奪的システムを解き明かす(副題)」でした。
コロちゃんは、ただ単に「失われた30年の謎」を知りたかったのですよ。
本書は「日本の大企業」が「賃金を押さえつけてきた」から、社会の全ての企業が「右ならえ」となってしまったとしていますね。
ですから「大企業戦犯説」ですね。
この説は「渡辺努東大教授」や「脇田成東京都立大学教授」も論考で主張されていましたから、まず間違いはないのでしょう。
コロちゃんは、素人のおじいちゃんですが「日本経済の一般書」を読む中で、「群盲象を評す」の説話が頭に浮かびました。下記ですよ。
●「6人の盲人がゾウに触れて、それが何だと思うか問われた」
●「足を触った盲人は「柱のようです」と答えた」
●「尾を触った盲人は「綱のようです」と答えた」
●「鼻を触った盲人は「木の枝のようです」と答えた」
●「耳を触った盲人は「扇のようです」と答えた」
●「腹を触った盲人は「壁のようです」と答えた」
●「牙を触った盲人は「パイプのようです」と答えた」
●「それを聞いた王は答えた」
●「あなた方は皆、正しい。あなた方の話が食い違っているのは、あなた方がゾウの異なる部分を触っているからです。ゾウは、あなた方の言う特徴を、全て備えているのです」
(出典:ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典:群盲増を評す: 2023年9月7日 (木) 20:24:より)
上記は「ウイキペディア」の「群盲象を評す」の中の「ジャイナ教の説話」ですが、世界中にいろいろなバリエーションがあるようです。
コロちゃんは、この「説話」と「経済を知ること」が良く似ている所があると感じているのですよ。
何しろ「経済指標」は数も種類も多いです。そのどれを取り上げてみるのかで、結論も風景もまるで変ってしまうのですよ。
今日のテーマの1つである「大企業の賃金抑制が失われた30年の戦犯である」にしても、経済学者によっては「別の戦犯」を主張している方もいらっしゃいます。
何しろ「経済現象」ですから、「原因」がハッキリしなければ、その「対策」が決まりません。
コロちゃんは本書を読んで、「失われた30年の戦犯」は、「経済学者」の間でも「大企業の内部留保=大企業のベアゼロ」に収れんしてきたように感じていますよ。
ただ、それが現在の春闘の「大企業の賃上げ5%以上」以上程度で、「日本経済」が再び成長できるようになるのかは、わかりませんね。
なにしろ、「アビジット・バナジー(ノーベル経済学賞受賞者)」の言葉がありましたからね。もう一度、以下に書き出しますよ。
「経済成長を促すメカニズムはまだよくわかっていない。とりわけ(先進国のような)富裕国で再び成長率が上向きになるのか、どうすれば上向きになるのか、ということはハッキリ言って謎である」
(世界最高峰の経済学教室より)
何とも「含蓄に富んだ言葉だ」とコロちゃんは感じましたよ。ただ、出来れば「日本の将来は明るい」となればいいなーと願うばかりですよ。

5.「コロちゃんと夜の新宿歌舞伎町」
今日は「経済の話」なので、最後の「コロちゃん話」には「バブル期の夜の新宿の話」をしますね。
コロちゃんは、「バブル経済期(1986年~1991年)」を30代の頃に体験してきました。
その当時は「東京都内の事業所」で働いていましたから、東京の新宿歌舞伎町でお酒を飲むことも何回かありましたよ。
「バブル期の夜の新宿」では、とにかく人出が多いのは当然ですが、コロちゃんが出かけた時の感想は「やくざ屋さん」が多いという事でした。
ごくたまにしか「新宿のお店」にはいかないのに、そのたびにあちこちで、ガラの悪いお兄さんがケンカをしたり、走り回ったりに遭遇していたのですよ。
その時にコロちゃんが耳にした話では、「新宿」では「暴力団の縄張りがない」という事でした。厳密には「店ごとに縄張り」という「早い者勝ちの縄張り」だというのですよ。
だから1つのビルに「10のお店」があるとして、それらの各店に全部別の「暴力団」が縄張りを主張することもあると言われていましたね。
だから「歌舞伎町」では数多くの「暴力団」がそれぞれ「縄張りにした店」を抱えて、しのぎを削っていると聞きましたよ。
「バブル経済当時」は、新宿歌舞伎町の「飲食店・風俗店」は5000軒と言われていましたから、それじゃあ「もめ事」が多いのももっともなことだと、当時のコロちゃんは思いましたよ。
ただ、これはコロちゃんの「バブル期の話(1986~1991年頃)」です。現在ではどうなっているのかは、まったく知りませんよ。
当時のコロちゃんは、現在と同じ「ヘタレ」でしたから、「君子危うきに近寄らず※」でもめ事を見ると、いつもそそくさと逃げていましたよ。
(※中国の孔子の歴史書『春秋』が由来という説がある:徳のある者は危険な所には近づこうとしない)
今日は【読書考】として、「河野龍太郎氏」の「日本経済の死角を読んで」をご紹介しました。
内容がお硬い「経済の話」でしたから、最後の「コロちゃん話」はちょっと柔らかめのエピソードにしてみましたよ。
( ¯▽¯ )ウフフ
今日ご紹介した本の「日本経済の死角」は、著者が「一般向け」とおっしゃっていますから、あまり経済に詳しくない方でもお読みいただけると思います。
よろしければ下記のリンクから、ご購入しお読みいただけますよ。もちろん「図書館」からお借りしても良いと思いますよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。







コメント