おはようございます。今日のコロちゃんは、足の「ふくらはぎ」がちょっと痛んでいます。
昨日の朝には「足がつって」目が覚めたコロちゃんでしたが、今日の「ふくらはぎの痛み」は、また違っています。その理由はハッキリしていますよ。
コロちゃんは、昨日の午前中に「ジム通い」をしてきたのです。
ここでは「リハビリのお兄さん」から許可されている「ウォーキングマシンとエアロバイク」を、それぞれ「30分間」ずつの運動をしてきました。
この「ウォーキングマシンとエアロバイクの運動」は、毎週「木曜日」しかしません。もう1回の「日曜日のジム」では「1時間の太極拳教室」のみを行なっています。
やはり「週1回の運動」では、まだまだ「筋肉は鍛えられない」のでしょうね。
その結果が、今日のコロちゃんの「ふくらはぎの痛み」なんでしょう。この「痛み」はどう考えても「筋肉痛」ですよ。
それに「腰の痛み」も、少し強くなっていますから、「身体に負荷をかけすぎたかな?」と考えているコロちゃんでしたよ。
だけど「何も運動をしない」と、その行き先は「寝たきり老人」ですよ。
コロちゃんは、それはイヤですから、いやいやながらも「ジム」へ通おうと思っていますよ。
そんな「キン肉マンコロちゃん」が、今日は「物価の神様が安いニッポンはいき過ぎだったよと言ってるよ」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「物価の神様=渡辺努東大教授のお話と、高いニッポンから安いニッポンへ」
☆「新時代の日本的経営が賃金ベアゼロの出発点だったよと、経団連と連合は雇用確保と賃金ベアゼロの密約を交わしたのか?」
☆「日本は高いニッポンに向けて動き出したよと、デフレ経済の戦犯はいなかったのか?」
☆「コロちゃんとスクーター」

1.「物価の神様=渡辺努東大教授のお話」
コロちゃんは、ちょっと前にこのブログで「【経済考】インフレ税の大増税(カッパギ)が始まったよ」と言う題名の記事を投稿しています。
この中でコロちゃんは、「物価の神様」と呼ばれている「渡辺努東京大学教授」に言及しています。
この「渡辺教授」は、「内閣府の経済財政諮問会議」にも出席して意見を述べておられますね。今年の3月に行なわれた政府の「財政諮問会議(3月)」で以下の驚くべき試算を発表していますよ。
「これまでの0%から2%のインフレへ移行する中で、日本最大の債務者である政府は180兆円の利得を手にする」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0310/shiryo_05.pdf
(内閣府:第2回経済財政諮問会議:資料5:賃金・物価・金利の正常化より:8月29日利用)
コロちゃんは、この「2%のインフレ」で「政府が180兆円の利得をえる」と言う内容に驚いて、この「渡辺教授の意見」をもっと知りたくてポチポチ調べてみました。
そうしましたら渡辺教授」は、「東京大学金融教育研究センター」のサイトで「賃金・物価・金利の正常化: 2040年までの展望」というレポートを発表されていました。
コロちゃんは、さっそく「興味深々」でこの「レポート」を読んでみましたよ。いやいやビックリしましたよ。
「渡辺教授」は、この「賃金・物価・金利の正常化: 2040年までの展望」の中で、「1990年代末から2022年の日本経済」について、実に興味深い知見を発表されていたのです。
いわゆる「失われた30年の姿」と呼ばれる「1990年代末~2022年の日本経済の姿」を、「掌を指すように」わかりやすい見方でひも解いてくれているのです。
何しろ「物価の神様」がおっしゃることです。
コロちゃんは、まるで「神様」が空の上から下界を見て「世の中の様子」を語っているように感じましたよ。
それでは、次から簡単にその「物価の神様=渡辺教授の話」をご紹介して見ますね。途中にコロちゃんの感想と意見などを交えながら書いてみますよ。
ただ、これはあくまでも「渡辺教授のレポート」を読んだコロちゃんの感想ですからね。「素人のおじいちゃん」の感想ですから、その点は割り引いてお読みくださいね。
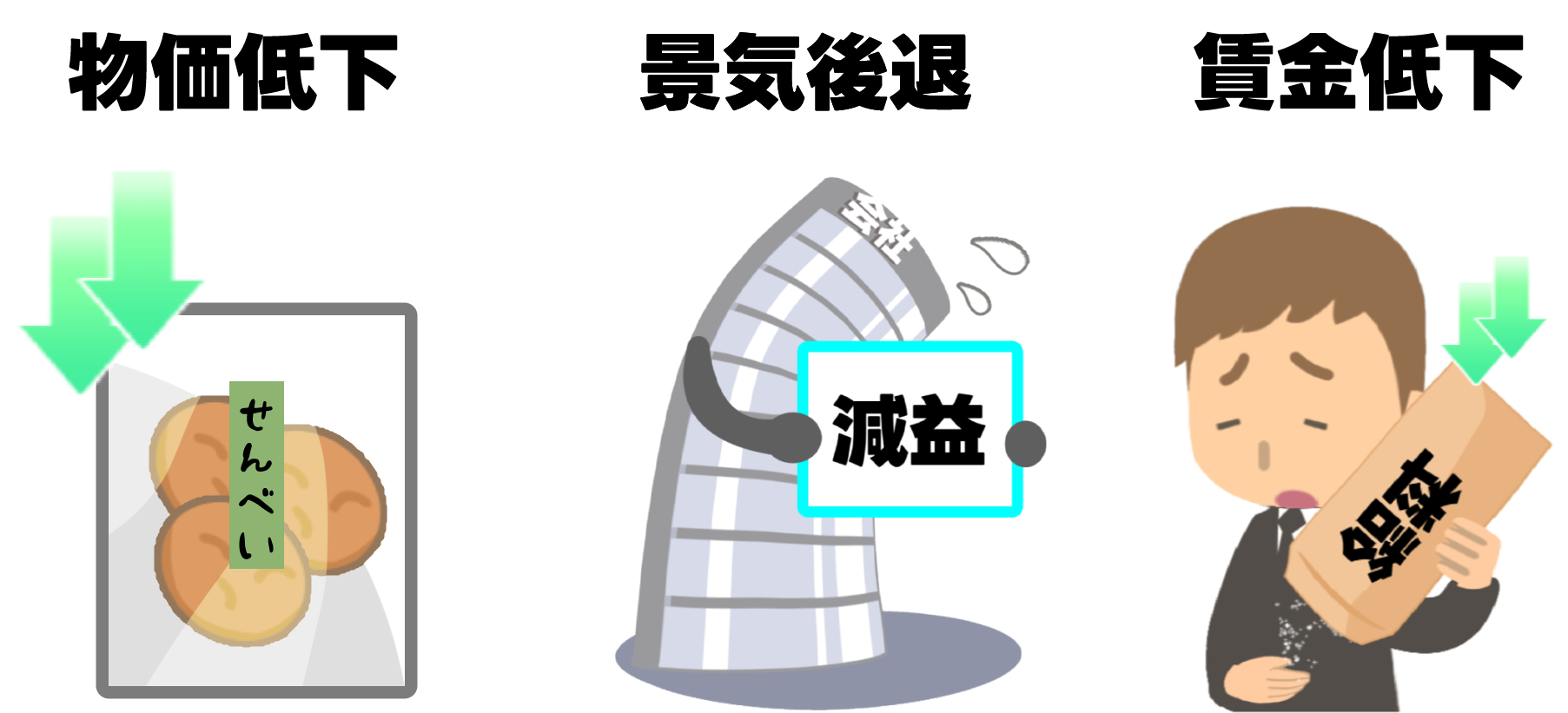
2.「高いニッポンから安いニッポンへ」
「渡辺教授」は、この「賃金・物価・金利の正常化:2040年までの展望」と題したレポートで、以下の2点を考察したと書いています。
◎「賃金・物価・金利の正常化:2040年までの展望」
①「第1ステージ:22年春から25年初までの3年間」
②「第2ステージ:2040年まで」
「渡辺教授」は、上記の「①第1ステージ:2022年春から25年初までの3年間」を「賃金・物価・金利の正常化」の過程だと指摘しているのです。
つまり、それ以前(2022年以前)の「日本経済」は「賃金・物価・金利が異常だった」と示唆しています。
そして、その後の「②第2ステージで2040年までの日本」を考察していますが、かなり専門的な緻密な考察ですから、コロちゃんはここには踏み込みません。
コロちゃんが注目したのは、このレポートの中の「高いニッポンから安いニッポンへ」の項目です。
「渡辺教授」は、「慢性デフレ(物価と賃金が上がらない)」の原因を、「1990年代の高いニッポンがある」と指摘しているのです。
この「物価と賃金が上がらない日本」は、1990年代末から2022年までの「四半世紀」続きました。
この「出発点」に何があったのかと言うと「渡辺教授」は「1990年代の財界の認識」をあげています。
つまり1990年代後半に「円高(1995年:1㌦=79円75銭)」に悲鳴を上げた「日本の経済界のお偉方たち」が、「賃金を引き下げる努力」を始めたことが「慢性デフレ」の始まりだったというのです。
この詳しい経過については、後で触れますね。
いずれにしろ、その当時の「日本経済に危機を持った財界のお偉方」の努力は、無事に実を結んで「賃金を上げないこと」が実現しました。
そこで起こった「日本の風景」は以下だと「渡辺教授」は書くのです。
◎「日本版:賃金と物価のスパイラル」
①「各企業は毎年商品価格を据え置き」⇒
②「消費者の生計費は毎年変わらず」⇒
③「労働者は賃上げなしでも生活を維持できる。労組は生計費不変の下で賃上げを言い出しにくいので賃上げを要請せず」⇒
④「人件費は毎年不変なので企業は価格転嫁の必要なし」⇒
⑤「①に戻る」
上記の「企業の商品価格据え置き・消費者の生計費変わらず・労働者の賃上げ要請なし・企業の価格転嫁なし」のグルグル回りの「サイクル」が95年以降の四半世紀続いたというのです。
そしれから四半世紀を過ぎてみれば、かつての1990年代にあった「高いニッポン」は一変しました。
要するに「高いニッポン」を変えようとしたことを、年々(25年間も)続け、それが行き過ぎた結果今度は「安いニッポン」に転落してしまったというのですよ。
なにごとも「ほどほど」が良いんですよね。やっぱり「やり過ぎは良くない」のですよ。
1990年代の「財界のお偉方」も、最初の時点で「世界的にも高かった賃金」が、その25年間後に今度は「世界的にも安い賃金」に落ち込むとは夢にも思わなかったでしょうね。

3.「新時代の日本的経営が賃金ベアゼロの出発点だったよ」
次に、それでは上記の「物価と賃金が上がらない日本」の出発点の1990年代後半に何があったのかを見ておきましょう。
「渡辺教授」は、過去の1990年代の末に「労働者の賃金を上げる春闘の変質」があったと指摘しています。
「賃上げを毎年要求する普通の春闘から、賃上げを求めない弱腰の春闘へと変わってしまった可能性」があるというのです。
この「春闘の変質の理由」として挙げたのが「高いニッポン」です。
「世界的にも高い日本の賃金(1995年、日本は世界第2位〈1位はスイス〉)」に、これでは「安い人件費の中国と戦えない」と、「企業経営者」たちは悲鳴をあげたというのです。
そして1995年に「日経連(その後経団連と統合)」が「新時代の『日本的経営』――挑戦すべき方向とその具体策」と言うレポートを発表しています。
そのレポートの内容は、今後の「日本の経営形態」を以下のように分けなければならないというものでした。
①「長期蓄積能力活用型グループ」
②「高度専門能力活用型グループ」
③「雇用柔軟型グループ」
当時は、何を言っているのかよくわからない方がほとんどだったのです。
だって当時の「日本社会」には、「非正規雇用者」はほとんどいませんでした。みんな「正社員」だったのですよ。
そこで、旧来の「日本的経営(正社員中心)」を転換させて、雇用者を「正社員」と「非正規社員」に分けることを、経済界が最初に提起したのがこの1995年の「新時代の日本的経営」だったのです。
今ならその意味が良くわかりますよね。
これは、日本企業の「家族主義的経営」から雇用者を「非正規雇用」に追い出して「賃金を下げるプラン」だったのですよ。
その1995年の日経連の「新時代の日本的経営」の発表から、30年が経過し、1995年に1001万人(20.9%)だった「非正規雇用」は、2025年7月現在で2128万人(36.4%)と倍増しました。
当時「日経連」で常務理事を務めた「成瀬健生さん(89)※」は、昨年2023年に東京新聞のインタビューで、「非正規雇用」が4割を占めている現状に対し、以下のように証言したと報じられています。
「今ほど増えるとは思わなかった」
「(経営者は)人間を育てることを忘れてしまった」
(※成瀬氏は1995年の「新時代の日本的経営」を執筆した方だとされています)
(※東京新聞:2023年2月27日記事:非正規雇用の活用を30年前に提言したら…より)
この方にしても、当時は真剣に「日本の将来」を憂いて提起したのだと思います。
1995年といえば、バブル崩壊が1991年で、その後も日本経済は「バランスシート不況」が長く続いていました。そのただ中で、日本の将来を憂いての提案だったのでしょう。
しかしその結果は、当時ではだれも考えなかった「非正規雇用」が4割近くを占める社会が出現したのです。
コロちゃんは、「渡辺教授のレポート」を読んで「日経連(その後経団連に統合)」はこの時の「高すぎる賃金を下げるやり方」が上手く行き過ぎて、途中で止められなくなったのだと感じましたよ。

4.「経団連と連合は雇用確保と賃金ベアゼロの密約を交わしたのか?」
さて上記で「日経連(経団連)」がいくら「賃金を上げないよ」と考えても、経営者の一声だけで「毎年の賃金水準」を決めることは出来ません。
それは、主要な大手企業には「労働組合」があるからです。
今ではすっかり「牙が抜かれておとなしくなった労働組合」ですが、1980年代にはまだ「年間5000件以上のストライキ」が行なわれていました。
この1995年当時の「ストライキ件数は1200件」でしたから大分沈静化していますが、「賃金を上げない」と言えば、それなりの抵抗があったでしょう。
そこで「渡辺教授」が、書いているのは「密約の存在」です。
「経団連と連合」との間にどんな「密約」があったのかというと、「企業が正社員の雇用を守る代わりに労組は今後賃上げを要求しない」と言うものです。
コロちゃんが、この「密約説」を初めて知ったのは、「渡辺教授」の著書の「物価を考える:著:渡辺努:2024年:日本経済新聞出版」の中に書かれていたのですよ。
この本の中で、著者の「渡辺教授」は経済学者の「早川英男氏」とのレストランでの会話を紹介しています。以下ですよ。
「(1990年代の末に経営者たちが)賃金が高い日本では、このままでは到底中国と戦えない。賃金を抑えるべきだ(と提案し)、1997年頃に労使の密約があったと考えている」by早川英男氏
この後段の「1997年頃に労使の密約があったと考えている」という部分が「経団連と連合幹部のベアゼロ密約」というわけですよ。
この「早川英男氏」は、やはり「経済学者」の方ですね。「日本銀行」の出身で、現在は「東京財団政策研究所主席研究員」をお勤めになられています。
コロちゃんは、この方の「金融政策の誤解※」という本を読んだことがあり、切れ味の良い考察と文章に感嘆したことがありますよ。
(※金融政策の誤解:2016年:著・早川英男:慶応義塾大学出版会)
ここで「レポート」に戻りますが、「渡辺教授」は「2000年代に起きた一連の出来事は『密約』の存在を裏づけている」として以下を記載しています。
◎「密約の存在の裏付け」
①「2002年春闘:トヨタがベアゼロの回答(トヨタ・ショック)」
(この宣告は他企業にも波及し、多くの企業がベアゼロへ)
②「2002年12月:経団連による春闘終焉の宣言」
(もはや賃上げは困難で、ベアなど論外と公式文書で宣言)
③「2003年春闘:連合がベアの統一要求を断念」
うーむ、ホントに「経団連と連合の密約」ってあったのかなー?
( ̄へ ̄|||) ウーム
上記をまとめて見てみると、なんか「計画的」に進んでいるようにも見えますよね。あんまり間が良すぎますよ。とても偶然とは思えないですよ。
だけど恐らく「文書で署名捺印」なんかしていないでしょうし、まさか「経団連・連合の金庫の中」なんかにコッソリ仕舞ってあったりしないよね?
ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?
コロちゃんは、その後の「連合幹部の反省」を読んだことがありますよ。
これは昨年2024年5月21日の「日経新聞」の「労働組合はデフレの共犯だった」との見出しの記事ですね。
この記事とは「安河内賢弘連合副会長・JAM会長の方のインタビュー記事」です。
「連合」は皆さんもご存じの通り、組織人員686万人の「全国の労働組合のナショナル・センター」です。
そして「JAM」は、昔「全国金属機械労働組合」と言っていた機械・金属製造業の中小企業にて働く労働者を組織する「産業別労働組合」ですね。こちらは現在組織人員が約34万人います。
この「JAMの会長さん(連合の副会長でもある)」の安河内賢弘氏が、新聞インタビューで以下のように語ったのです。
「バブルが崩壊し、組合はリストラを選ぶか賃金を我慢するかの二者択一を迫られた。私たち組合は雇用を守る方を選んだ。」
「雇用を守るために非正規雇用・賃下げ・最終的にはリストラも受け入れた。本当に守ろうとしたのは何だったのか?」
「労働組合がデフレに陥った戦犯だったとは思わないが、共犯であることは間違いがない」
「(今振り返れば)デフレの時代においても『自分たちの生活は苦しい』という組合の基本的な主張を忘れるべきではなかった」
コロちゃんが、これを読んだ時には「全国紙の新聞紙上で労組のトップが自己批判したのは初めて見た」とビックリしましたよ。
だけどこの「安河内賢弘連合副会長」は、このインタビューの時に「経団連との密約」は頭にあったのかなー?
(´ヘ`;)ウーム…
だって「組合はリストラを選ぶか賃金を我慢するかの二者択一を迫られた。私たち組合は雇用を守る方を選んだ」ですよ。
これって実際に「経団連会長と連合会長」とが対面で「サシで口約束」したら、それって「密約」ですよね。
まあ「真相」は分かりませんが、結果を見ると「賃金を上げないこと」が1998~2022年の「四半世紀(25年間)」も続いたことだけは事実ですね。
これによって「日本」が「高いニッポン」から「安いニッポン」に転落したことを考えると、上記の「経団連と連合」の「ベアゼロ(密約?)」は「罪深い」と思ったコロちゃんでしたよ。

5.「日本は高いニッポンに向けて動き出したよ」
コロちゃんが読んだところでは、「渡辺教授」は「高いニッポン」を何とかしようとした「経団連」を責めてはいません。
むしろ当時としては「高いニッポンの修正」はやむを得ない行動だったのとニュアンスを感じましたよ。
そして、その後の2022年以降の「日本」が「安いニッポン」から「高いニッポン」へ向けて動き出したとポジティブに見ています。
「渡辺教授」は、「日本の賃金は2000年代初頭まで世界トップレベルだった」としながらも、その後「2014年には20位まで落ち、ここまで下がると世界の中位とすら言えない」と指摘しています。
そしてその中で「社会に醸成された危機感が賃金正常化の原動力となり、2023年、24年の春闘での高い賃上げが実現した」と書いているのです。
この様にして「日本は既に高いニッポンに向けて動き出した」と、「時代は変わった」との認識を「渡辺教授」は宣言しているようにコロちゃんは読みましたよ。
そして「新しく動き出したスパイラル」として以下を提示しています。
◎「賃金と物価の好循環」
①「各企業は毎年商品価格を2%引上げ」⇒
②「消費者の生計費は毎年2%上昇」⇒
③「労働者・労組は毎年、2%の賃上げを要求」⇒
④「企業は人件費の増加分を毎年、商品価格に転嫁」⇒
⑤「①に戻る」⇒
うーん、こんなにうまい事まわるのかなー?
( ̄へ ̄|||) ウーン
なんか「ポジティブ過ぎる」と思ったコロちゃんでしたが、「渡辺教授」も直ぐにこの「好循環」が回るとは考えていないようですよ。以下の記載がありましたよ。
「新サイクルでは、物価と賃金が毎年、安定的に上昇していくことになる。新サイクルの移行が完了したかと言えば、たぶんそうではないだろう」
「日本は旧サイクルを30周繰り返してきた。それに対して新サイクルはまだ3周目に過ぎない」
「旧サイクルの方が生活しやすかったという意見も多く聞かれ、旧サイクルへの『郷愁』は社会に根強い。新サイクルが完全に定着となるにはさらに数年を要すると見ておくべきだろう」
やっぱりそうだよねー。
(⁎•ᴗ‹。)ネー♪
コロちゃんも「旧サイクル方が生活しやすかった」ですよ。だけどこれって「郷愁」なの?
σ( ̄^ ̄)はて?
それに「数年を要する」ですむのかなー?
( ̄へ ̄|||) ウーム
コロちゃんには、あと数年で「物価は上がるけど賃金はそれ以上に上がる社会」が来るとは思えないんだよねー。
今日コロちゃんは、この「レポート」から「経団連と連合の密約」と「安いニッポンと高いニッポン」に焦点をあてましたが、この「レポート」の本旨は、別の所にあるかと思います。
上記の「時代認識」よりも、それを背景とした「2040年までの展望」にあるものと思われますね。
そちらには「インフレがもたらす日本の財政の影響(インフレ税)の考察」が詳細に書かれていますが、そちらには今回は触れませんね。
と言うか、あまりにも「専門的」でコロちゃんでは十分に理解出来ませんでしたよ。
そんな「素人のコロちゃん」でもこのレポートは読んで興味ある点がいくつもありましたよ。皆さんもお読みになりたいと思われましたら、以下のリンクのクリックをお願いしますね。
https://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/J120.pdf
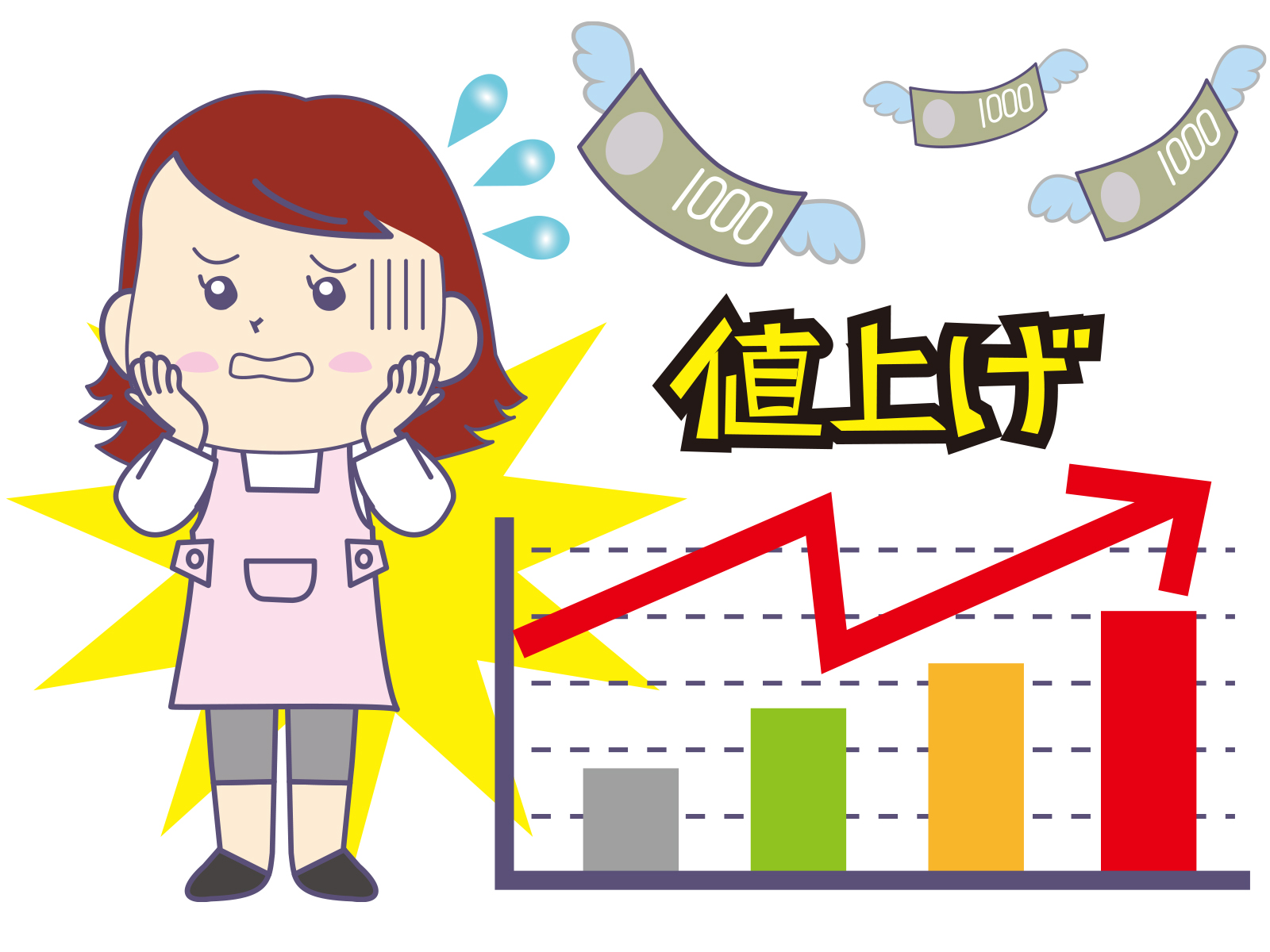
6.「デフレ経済の戦犯はいなかったのか?」
さて、ここでコロちゃんの考え方を書いてみますね。
コロちゃんは、もう「70代のおじいちゃん」ですから、上記の「1990年代~2022年のデフレ経済」はリアルタイムに経験してきました。
そこで振り返ってこの「四半世紀」とそれ以前を俯瞰すると、「1980年代の一億総中流社会」がその後の「1990年代~2022年のデフレ経済」の期間の間にジワジワと蝕まれてきたように感じています。
今では「貧しい・苦しい生活」と感じている世帯が数多く出現しています。
コロちゃんのような「市井のおじいちゃん」から見ると、つい「誰が悪いんだよ!」と愚痴がこぼれ出て来るのですよ。
ついつい「悪者・戦犯」を求めて責めたくなるのです。
しかし、上記の「渡辺教授」の「賃金・物価・金利の正常化: 2040年までの展望」はさすがですよね。コロちゃんのような「品のない犯人探し」はしていません。
1995年の「日経連(後に経団連に統合)」の「新時代の日本的経営」も、その後の「経団連と連合の密約疑惑」も、「高いニッポンに危機感を抱いた財界人の行動」と擁護しています。
これって、「1995年当時の財界人は国士だった」ってことですよね。「日本の将来を本気で憂いての行動だ」とのニュアンスをコロちゃんは感じましたよ。
ただ、その後「同じ行動(ベアゼロ)」を四半世紀も続けちゃったから、当初の意図とは違って今度は「安いニッポン」に転落しちゃったってことですよね。
つまり、これはついつい「行き過ぎちゃった」ことで、そこに「悪気はないんだよ」ってことですよね。
そして今度は、その「安いニッポン」から抜け出すことが「新しい国のための正義」と変わったと言うのですよ。
そうなるとこれからは、「賃金を上げること」が「日本のため(正義だ)との価値観」が広がっていくと思いますよ。
また「賃金を上げない経営者は失格だ」との価値観も、今後は広がっていくだろうともコロちゃんは思いましたよ。
だけどコロちゃんは、もし「2002年に経団連がベアゼロ路線」に突っ込まないでたとえ「2~3%でも賃上げ」していれば、「国民の生活」はもっと楽になっていたように思うのですよ。
いやいや「2002年」じゃなくとも良いんですよ。
もし「2013年にアベノミクスの異次元の金融緩和」なんかじゃなくて、その時から「賃上げ」していれば良かったのになー。
やっぱりコロちゃんは、「デフレの戦犯」は「賃上げをしなかった経団連」が一番悪いと思っていますよ。
その次が「密約」はあったのかどうかは分かりませんけれど、「ベアゼロ」を許した「連合」もその次に「罪深かった(共犯だった)」とコロちゃんは思いましたよ。
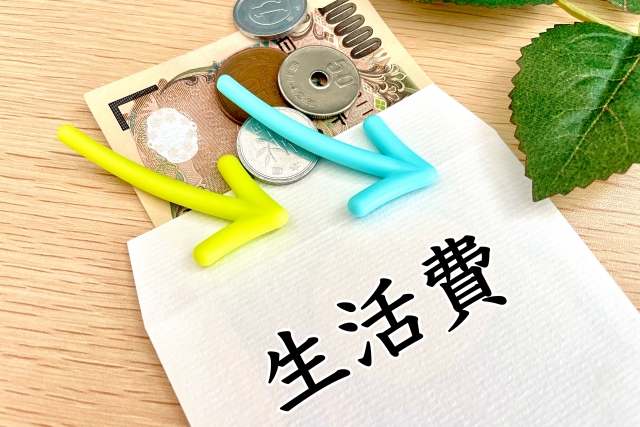
7.「コロちゃんとスクーター」
さて今日は「渡辺東大教授」の「賃金・物価・金利の正常化: 2040年までの展望」とのレポートのごく一部を考察してみましたよ。
最後の「コロちゃん話」は、上記で「経団連と連合がベアゼロの密約」を結んだかもしれない2002年頃の「コロちゃんの生活」について書いてみますね。
コロちゃんちは、駅からバスで10分ほどの所にあります。だけど「バスの本数」ってそんなに多くないんですよね。
それに「買い物」も近くにそうそう「店舗」の数が多いわけではありませんから、2002年当時のコロちゃんちでは、2台のオートバイ(スクーター)に乗っていました。
下記の「ホンダタクト」ですよ。うんうん、これだこれだ。
(*。_。)⁾⁾ゥンゥン

出典:ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典:「雀球」最終更新 2025年2月27日 (木) 03:54
このスクーター2台を妻とコロちゃんと2人で乗っていたのです。色は「妻が赤色」で「コロちゃんが黒色」でしたよ。
当時のコロちゃんは、このスクーターを駅までの「通勤の足」に使っていましたね。妻は「お買い物」とパート先への足に乗っていましたよ。
コロちゃんのこの「スクーターの思い出」は、少し前にまだ小さかった「次男(多分小学校低学年)」を運転するコロちゃんの足の間に立たせて、家の周りを走り回ったことがありました。
(※絶対マネしちゃダメですよ)
コロちゃんは、充分注意して「ゆっくり走ったつもり」でしたが、まだ幼かった「次男」は「こわいこわい」と泣き言を言っていましたよ。
そして「長男」との「スクーターの思い出」は、「学校帰り」で駅にいた長男が、偶然「駅前に駐車していたコロちゃんのスクーター」の窃盗現場に遭遇したことです。
「長男」は警察に直ぐ連絡したようですが、警官が駆け付けた時にはすでに「スクーターの正面のパネル」を盗まれた後でしたね。
当時は駅前に「いわゆるチーマー(不良)」がたむろしていた時代でしたね。この頃は「コンビニの駐車場」でも「チーマ―」がいたるところで見られましたよ。
結局、この犯人は見つかりませんでしたよ。ホント物騒な時代でしたよ。
そして妻のスクーターですが、彼女は「交通事故」が多かったですね。確か3度は「交通事故」にあっています。
その中の1度は「後ろから追突された事故」でしたから、妻に過失は無かったのですが、最後の「交通事故」の時には家族全員が「もう運転は止めろ」と免許証の返納をさせていましたよ。
考えてみれば、20歳ごろから乗り始めた「コロちゃんのオートバイ歴」でしたが、人生で何種類・何台ものオートバイに乗ってきましたが、最後のオートバイは、この「ホンダタクト」でしたよ。
コロちゃんは、車の運転は現在でも「現役」ですが、既にオートバイは卒業してしまいました。ちょっと寂しいことですよね。
コロちゃんは、「オートバイ」で「全身で風を切る感覚」が好きだったのですよ。
しかし「年輪を重ねる」ということは「感覚が変わる」と言う事でもありますよね。今ではもう「爽快感」よりも「怖さ」を感じるようになってしまいましたよ。
そう思うとコロちゃんは、若い時代に「オートバイ」に出会えて「楽しい時間」を過ごすことが出来て幸せだったと思っていますよ。
それに「長男・次男」も18歳を過ぎた後は、コロちゃんに続いて「オートバイ」を乗り始めましたからコロちゃんは嬉しかったですよ。
今日の「コロちゃん話」は、「コロちゃんちのオートバイの話」をしてみましたよ。オートバイの楽しさが少しでも感じてもらえたら嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。








コメント