おはようございます。つい先日にコロちゃんが「内科医院」へ受診に出かけた時に、「マイナンバーカード」をいつものように「顔認証付きカードリーダー」に入れた時のことです。
いきなり「期限が近くなっています」との表示が出てきました。
あれれ? 確か「マイナンバーカード」って「10年間」使えるんじゃないの?
(。・_・?)アレレ?
そこで帰宅後にポチポチ調べてみたら、以下だったんですよ。
「マイナンバーカードには、カード本体と電子証明書の2つの有効期限があります」
「カード本体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日までで、電子証明書の有効期限は5年です」
皆さん知っていました? コロちゃんは知りませんでしたよ。思わず、次のように呟いちゃいましたよ。
ふーん、そうだったんだー?
( ̄へ ̄|||) フーン
コロちゃんはてっきり全部が「10年間」使えるんだと思っていましたよ。なんでこんな面倒くさいことすんのかなー?
どっちかに「統一」しろよ! 間違いやすいだろ?
ヽ(`Д´)ノプンプン
ぶつぶつ文句を言っても事態は変わりませんから、コロちゃんはその内に「市役所」へ行って「マイナンバーカードの電子証明書の更新」をすることにしましたよ。
…( ̄。 ̄;)ブツブツ
そんな「ぶつぶつコロちゃん」が、今日は「消費減税を経済学から見るよ」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「消費税減税の、政治的な見方と経済学の見方と、食品の消費税減税派非効率だって」
☆「国民の声を聴くよと、減税と給付金はいつまでも続けられないよ」
☆「コロちゃんと新しい鏡台」

1.「消費税減税の、政治的な見方と経済学の見方」
さて、今日は現在「参議院選挙」で大きな争点となっている「消費税の食料品の減税」について、ちょっと「専門家の意見」を聞いてみようと思いたちました。
コロちゃんは、この「消費税減税」は「政治的な見方」と「経済学的な見方」と二つに分かれると思っているのですよ。
「経済学的見方」については、先日の5月23日に「日経新聞」が「経済学者47人」に「一時的な消費税減税は適切か?」との質問と回答を紙面で「エコノミクスパネル」として発表していました。
その内容は下記でしたよ。
◎「一時的な消費税減税を行なうのは適切である」
➀「強くそう思う :0%」
②「そう思う :2%」
③「どちらとも言えない:13%」
④「そう思わない :57%」
⑤「全くそう思わない :28%」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD1985C0Z10C25A5000000/
(出典:日経新聞 5月23日:エコノミクスパネルより:7月4日利用)
上記のように「経済学者」で、今回の「消費税減税」に「いいね!」としたのは、「②そう思う:2%」の1名様だけでしたよ。
残りの46人の「経済学者」は、全て「適切ではない」と回答しています。
しかし、現在の全ての政党は、全て「消費税減税か給付金」を主張しています。
コロちゃんは、この違いは「政治家は短期的な視点」で「経済学者は中・長期的視点」で見ているからと思うのですよ。
つまり「経済学者は中長期的には消費税減税には価値がない」と考えるのに対して、「政治家は現在の物価上昇で苦しむ世帯を助けなければならない」と見ている違いですね。
そこでコロちゃんは、今日はその「経済学者の中長期的視点」について、ちょっと見てみようと考えましたよ。次をご覧くださいね。

2.「食品の消費税減税は非効率だって」
さて、今日ご紹介するのは、「日経新聞」の「経済教室」」に掲載された「小峰孝夫大正大学客員教授」の「食品の消費税減税派非効率」との見出しの「論考」です。
この「小峰教授」の著作を、以前にコロちゃんは読んでいたのですよね。以下の本ですよ。
この本は経済企画庁(現在は内閣府に統合)で「内国調査課長」として「経済白書」などを執筆してきた「小峰隆夫氏」が書いたものです。
400ページ近くある分厚い本でしたが、「経済エッセイ」を加筆編集した本なので、素人のコロちゃんが読んでも面白かったですよ。
この様に「小峰教授」をコロちゃんは知っていたものですから、この「新聞論考」も興味深く読んだという訳なのですよ。
この「論考」で、「小峰教授」は現在の日本経済の現状について以下のようにまとめています。

➀「景気が悪いわけではないけれど、良くもないよ」
最初は「日本経済の懸念材料」ですよ。「小峰教授」は「景気が悪いわけではないけれど決して良くもない」というのですよ。
◎「日本経済の懸念材料」
➀「経済の拡大テンポが穏やか過ぎる」
・「景気を上昇・下降で分けると上昇」
・「どちらでもないという区分があればそれに入れたいほどだ」
②「物価の上昇」
・「5月の消費者物価上昇率(総合)は3.5%」
・「名目賃金が上昇しても物価に追いつかない」
③「トランプ関税の影響」
・「大きな負の影響を懸念」
ざっと、上記が「経済の懸念材料だ」としていますね。うんうん、わかりやすいですね。これなら素人のコロちゃんにもわかりますよ。
(*。_。)⁾⁾ゥンゥン
「小峰教授」の書いた本の特徴は「素人にもわかりやすい経済学」なのですよ。この「新聞論考」も読んでわかりやすいですよね。
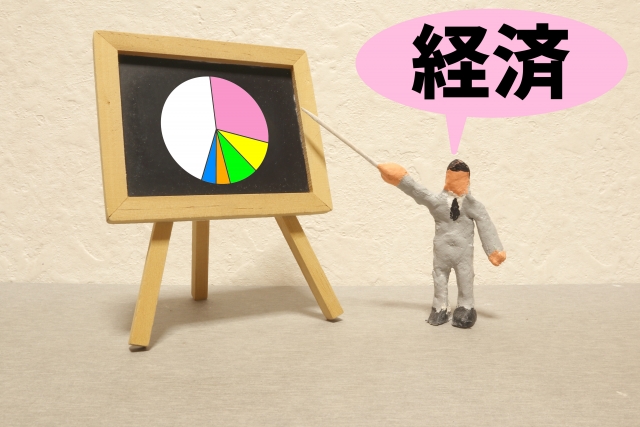
②「もうデフレではないよ」
次に「重要な点」として2つを指摘しています。
◎「上記した諸課題への対応に際しての重要な点」
➀「すでにデフレから脱出してポストデフレに入っている」
・「プラス面 : 税収が増える」
・「マイナス面:利払い費が増える」
あー、「ポストデフレ」って、もう「物価が下がらない」と言う事ですから「インフレの世界」に踏み出したってことですよね。
( ̄Д ̄*)アー
そうなると「名目の物価と賃金が上がる」訳ですから「税収も増える」となりますよね。確か「2024年度の税収の上振れ分は1.8兆円」でしたよね。
しかし、その代わりに「借金の国債の利払い費」も増えますよね。
これを「小峰教授」は、「税収の増える方はほとんどタイムラグなしに現れるが、利払い費はタイムラグが長く、しかも影響が長く続く」と書いていますよ。
これって「朝三暮四※」みたいな話ですよね。
(※餌を「朝に3つ、夕に4つ」と与えることを提案したところ猿が怒ったので「朝に4つ、夕に3つ」と提案したら喜んだという話:目先の違いにこだわって、全体として同じであることに気づかないこと:中国古典:列子より)
ん!、今回の「参院選」の「各政党の公約」では、軒並み「財源」として「税収の上振れ分」をあげていましたよ。
( ´゚д゚)ン?
先に使っちゃダメじゃん!
(゚Д゚)アッラー!
②「受給ギャップが均衡」
・「25年1~3月期はマイナス0.2%」
・「しばらくの間需給ギャップはほぼゼロ近辺で推移するだろう」
この「需給ギャップ」とは、「経済全体の総需要と供給力の差」のことを指しますね。
これが「均衡(ゼロ)」している時に「バラマキ」をすると「物価が上がる(インフレ)」とされていますね。
上記の「➀デフレではない」と「②需給ギャップが均衡」を、「小峰教授」は「現在の日本経済の現状認識」としたうえで、次に「各政党の現金給付と食品の消費税減税の評価」を書いています。

③「食品の消費税減税は、富裕層へ高い給付金を配るのと同じだよ」
さて「小峰教授」は、「現金給付と食品の消費税減税」について「現段階で景気対策として大規模な歳出拡大を伴う政策の必要性は薄い」と、バッサリと切って捨てています。
その理由は、以下でしたよ。
◎「現金給付と食品の消費税減税について」
➀「財政事情の悪化を招く」
②「社会保障の基盤をが揺らぐ」
③「景気刺激策が不確実である」
④「元に戻すのが難しい」
⑤「所得再配分の手段として極めて非効率」
うーん、どれも「反論」出来ないと思いましたよ。実に真っ当な内容ですよ。
( ̄へ ̄|||) ウーン
そして「小峰教授」は、上記の「⑤所得再配分の手段として極めて非効率」の具体的例として、以下を書いているのです。
◎「食品支出にかかる1年間の消費税額」
❶「年収200万円未満の世帯 :5.4万円」
❷「年収1500万円以上の世帯:12.4万円」
(年収の高い世帯ほど高い食品を買うので消費税額も大きい)
上記を見ると、もし「消費税が1年間無くなる」と「❷年収1500万円以上の世帯は12.4万円」の給付金をもらうのと同じとなります。
それに対して「❶年収200万円未満の世帯は5.4万円」の給付金しかもらえません。「❷年収1500万円世帯」の半分以下ですね。
つまり、現在多くの政党が主張する「食品の消費税ゼロ」が実現すると、高い世帯へ「高い給付金」が支給されるのと同じことだと「小峰教授」は主張しているのですよ。
うーん、そう言えば「石破総理」も静岡県沼津市の演説で、「お金持ちほど沢山消費する。減税額が大きい。本当にそれでいいのか」と述べたとされていますね。
( ̄へ ̄|||) ウーン
だけど「自民党」は「1人2万円の給金」を主張していますからね。「貧乏人とお金持ちに同じ2万円を配るよ」では、あんまり他党を批判できないように思いますけどね。
ここまで「小峰教授」の「論考」を見てきましたが、これなら「素人のコロちゃん」でも良くわかりますね。
多くの「経済学者」の皆さんが、そろって「給付金と消費税減税」に反対するのも当然と思いましたよ。
なお、コロちゃんが特に注目したのは、以下の認識でした。
◎「低成長は構造的・長期的な課題である」
・「需給ギャップはゼロであるから需要追加は物価を引き上げる」
・「企業の設備投資を促す政策が重要」
この「需要追加」とは、「減税や給付金」を意味します。つまり「減税も給付金も物価を上げるよ」と言う事ですよ。
コロちゃんは、この「小峰教授の論考」を読んで、ますます「減税や給付金」へ反対する考えに確信を持ちましたよ。
なお、この「日経新聞」の「経済教室」の「食品の消費税減税派非効率」の「論考」をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

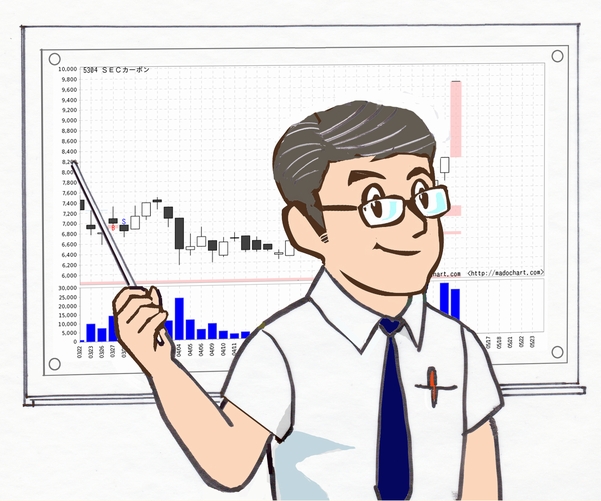
3.「国民の声を聴くよ」
さて、コロちゃんはますます「減税や給付金」に冷たい目を向けるようになりましたが、世の中の方たちのご意見をちょっと見ておきましょう。
新聞の主要各紙は、先日の6月末に「参院選挙の世論調査」を実施しています。
その中で「消費税減税」についての回答を、コロちゃんがポチポチ調べて見ましたら、新聞社によってかなりの差が出ていましたよ。
◎「主要各新聞社の消費税減税についての世論調査」
➀「毎日新聞」
・「消費税減税支持:55%」
・「質問:消費税減税案と給付金案のどちらが良いか?」
②「読売新聞」
・「消費税減税支持:50%」
・「質問:消費税は、社会保障の財源に充てるよう法律で定められています。消費税の税率を維持する方がよいか、引き下げる方が良いか?」
③「日経新聞」
・「消費税減税支持:35%」
・「質問:消費税率を、社会保障の財源を確保するために維持するべきか、赤字国債を発行してでも下げるべきか?」
うーん、各社とも「質問内容」が微妙に違っていますね。
( ̄へ ̄|||) ウーン
「➀毎日新聞」は「給付金案」との2択ですし、「②読売新聞」と「③日経新聞」は、わざわざ質問の前段に「消費税は社会保障の財源」と言う言葉を加えていますよ。
これでは「正面から消費税減税」への国民の声は分かりにくいですよね。だけど「国論を2分している」ことは間違いがないと思われますよ。
「消費税減税」については、「賛成・反対」のどちらかが圧倒的に多いとはなっていないことをうかがわせると、コロちゃんは思いましたよ。
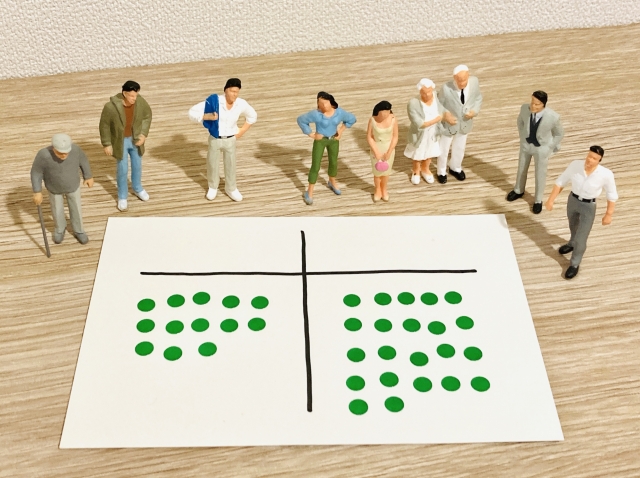
4.「減税と給付金はいつまでも続けられないよ」
さて、ここでコロちゃんの考え方を書きますが、たとえコロちゃんがいくら吠えても、今回の選挙後には「給付金」か「消費税の食品減税」のどちらかが行なわれることになると思われます。
それがどうなるかは、「参院選挙結果」を見てみないとわかりませんが、やはり「政権与党である自民・公明党の主張する給付金(1人2万円)」が実施される可能性が高いのではないでしょうか。
そうなると「3兆円の予算」が必要となってきます。
しかし昨年度2024年度の「税収の上振れ分は1.8兆円」とされていますから、残りの1.2兆円はどっかから調達してくるのでしょう。
コロちゃんのような素人でも「今年の分ぐらい」は何とか出てくると思っていますよ。そうなると「1人2万円」を受け取って、ちょっとホッとする世帯も数多くあるかと思われますね。
しかし、「物価高」で苦しい家計になっている方々に対し、来年以降はどうするんでしょうね。
今年と同じように、毎年「3兆円規模の給付金」を支給することは、とても「財源」が許さないでしょう。
現在の「日本銀行」は「安定的な2%の物価上昇率」を目指しています。今年以降も「物価上昇」を止める気はないのですよ。
現在の「政府」は、未だ公式には「デフレ脱却宣言」をしていませんが、コロちゃんは現在の「日本経済の現状」は「インフレ真っただ中だ」と思っていますよ。
おそらく多くの「経済学者」の方々も、コロちゃんと同じく「インフレだ」と考えていると思いますよ。
ですからコロちゃんは、今の選挙で各党が公約している「減税や給付金」はどうせ毎年できるものではないのですから、もうスッパリとやらない方が良いと考えていますよ。
来年以降を考えると、こんな1回のバラマキはそれこそ「焼け石に水」ですよ。それより「物価上昇」を止めることを考えた方が良いと思いますよ。

5.「コロちゃんと新しい鏡台」
今日のテーマは「消費減税を経済学から見るよ」と、経済学者の「小峰教授の論考」をご紹介してみました。
そこで最後の「コロちゃん話」ですが、「減税=お金の話」ということで、コロちゃんが20代の青年だった1970年代初頭の「耐久消費財=鏡台の話」を書きますね。
皆さんのお宅には「鏡台」はありますか?
結婚なさっているご家庭では一つはあるかも知れませんが、今では場所を取るから、洗面所の鏡で充分と言う方も多いかと思われます。
だけど、女性にとって「鏡台」とは江戸時代からある「家庭の必需品」だったのですよ。少なくともコロちゃんが青年だった1970年代には「嫁入り道具」にも入っていました。
さて、今でもコロちゃんの記憶に残っているのは、20代にコロちゃんと妻が結婚した時のことです。
妻のアパートから新居のアパートに引越しの荷造りをしていた時に、軽トラックの荷台から「鏡台」が落ちて壊れてしまったのです。
ガッシャ―ン!
(゜Д゜*)ああああ
その時の妻は、ショックで口もきけないほどに落ち込んでいましたよ。
ただもう壊れてしまったことはどうしようもありません。引っ越しが終わって落ち着いてから、新しい「鏡台」を購入しましたよ。
当時「結婚した夫婦」の欲しかった家具は「鏡台」だけではありませんよ。整理タンスも欲しかったですし、洋タンスも買いたかったのです。
しかし若きコロちゃん夫婦は貧しかったのですよ。コロちゃん夫婦だけではありませんよ。当時の若い方はほぼ全部同じように貧しかったのですよ。
そこでコロちゃんたち夫婦は、数カ月おきに一つ一つずつ購入していきました。当時気に入っていたのは「太郎&花子※」の家具でした。
(※太郎&花子の家具メーカーはもう無くなっているみたいです)
もちろん最初に「鏡台」と「スツール」を買いましたよ。その後も「整理タンス」と「洋タンス」を購入するまでにはずいぶん月日がかかりましたね。
コロちゃんたち夫婦は、それらの家具が一つ一つ増えていく中で「生活が豊かになってきたこと」を実感していたのです。
それを「自分たちの力だけ」で達成した喜びもありましたよ。
当時の「独身生活」は「4畳半か6畳一間のアパート」が普通だった時代です。家具などはほとんど必要がありませんでした。置く場所もなかったのです。
それが「結婚」することで、住まいも広くなりましたし、家具も増えて「ワンランク豊かになった」ことをみんなが実感していたのですよ。
このような感覚は、当時の若者たちは皆同じように感じていたと思いますね。当時の「独身者」と「結婚した夫婦」とでは、「食生活」も「生活環境」もまるで違っていたのですよ。
「独身者」は「狭いアパート」で、食事も貧しい物しか食べられなかったのですよ。何しろ「コンビニ」も「牛丼屋」もない時代だったのですからね。
当時の「結婚生活」とは、「生活全般」がワンランク上がり「食生活」も改善されて、「人間らしい生活ができるようになる」と認識されていましたね。
そんな「喜び」を皆が感じられるものが「結婚」だった時代でしたよ。良い時代でしたよね。
それが、「結婚時」にコロちゃんは引っ越しで「鏡台」を壊しちゃったのですから、なんとしても最初に「新しい鏡台」を買うのはもう「男の矜持」だったのですよ。
その後に無事「鏡台」を購入できてホッとしたことを憶えていますよ。
今日は「お金の話」を書いていて、この「鏡台を引っ越しで壊してしまったこと」がコロちゃんの頭に真っ先に浮かびましたね。
1970年代時代のコロちゃんの給料は、実に低かったのですよね。だけど、その中で一つでも「大切なもの」を得たいと全身で希求していた「青年時代」でしたよ。
コロちゃんは「鏡台」は壊してしまいましたが、その代わりにその後一つ一つ家具を買う中で「妻と2人で歩く人生」を創ることが出来ましたよ。
めでたし、めでたし。
(*´∇`*)ニコニコ
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします。
(^_^.)
おしまい。








コメント