おはようございます。今朝コロちゃんが、朝ワンコと散歩にでると「3日ぶり」に青空が広がっていましたよ。
昨日も一昨日も、「朝は雨」が降っていてコロちゃんは、傘を差しながらワンコを「ペットカート」に乗せて、ガラガラと「近くの道路の高架下」で散歩がわりに歩かせていたのですよ。
それが今日は、やっと晴れましたよ。コロちゃんは、今朝はちょっと「明るい気持ち」で散歩をしてきましたよ。
そうしましたら、道路のあちこちで「同じようにワンコ連れで歩いている人」が、チラホラと見えましたね。
距離があったので、言葉は交わしませんでしたが、時々出会っていた「ワンコ仲間の方たち」でしたよ。
ワンコを飼っている人は、みなコロちゃんと同じように「雨の続く秋の日」から「やっと晴れた秋の日」になったことを、喜んで出てきたと思いましたよ。
どうやら今日は「一日中晴れの日」となるようですよ。コロちゃんは、今日は「洗濯物が乾くなー」と世帯じみた感想を思いながら、元気に帰宅してきましたよ。
そんな「秋晴れを喜んだコロちゃん」が、今日は「小中高生の半数が読書0分だって?」をカキコキしますね
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「本を読まない子供が増えているよと、高校生が一番本を読まないよ」
☆「読書する子どもが減るのは、もう防げないよと、読書なしだと、多様な知識や教養が得られないよ」
☆「子どもたちに本を読んでもらいたいけど・・・と、コロちゃんと読書の傾向」

1.「本を読まない子どもが増えているよ」
コロちゃんが、朝新聞をバサバサ読んでいると「小中高生の半数『読書0分』/スマホ使用で時間短く」との見出しが目に入りました。
コロちゃんは、自分が「一日中本を読んでいても飽きない人だ」と思っていますから、この見出しを「おー、信じられない!」と感じて、ジックリと読んでみましたよ。
そうしましたら、なんと「読書をしない(0分)小中高生が52.7%と半数を超えている」と言うのですよ。
コロちゃんは、それでは「その時間を何をしているのかな?」と思ったところ、「スマホ使用時間が伸びている」と「さもありそうな理由」が出ていましたよ。
記事では「2015年のデータ」と、今回の「2024年のデータ」を比較して「読書をしない割合」が、「2015年の34.2%」から「2025年の52.7%」と「1.5倍に増えた」と書いていますよ。
さらに「スマホ使用時間」は、「小4~高校生」でそれぞれ「約22~52分増えた」として、「スマホの使用時間が多いほど読書時間が短くなる」と書いていますね。
コロちゃんは、スマホはあんまり見ていないのですが、その代わりに「iPad」を見ていますので、あんまりこの「小中高生」のことをあれこれ言いにくいと思いましたよ。
それでもコロちゃんの場合は「読書」はしていますよ。そうですよ、いくらスマホを見ても「本を読んでいれば良い」と思いますね。
そこで、ちょっとこの上記の「ベネッセの調査」の内容を詳しく見てみようと思い立ちましたよ。次で見てみましょうね。
なお、この「日経新聞」の「小中高生の半数『読書0分』/スマホ使用で時間短く」の見出しの記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

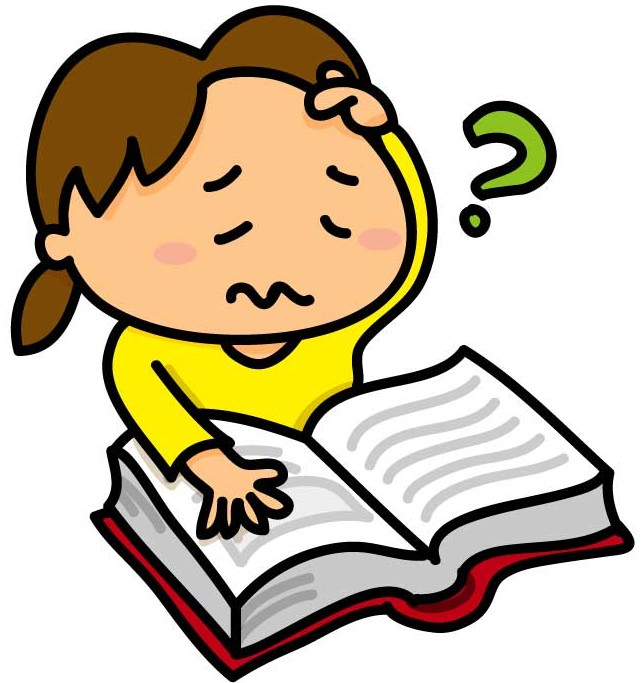
2.「高校生が一番本を読まないよ」
さてコロちゃんは、最近ちょっと興味がある記事を読むと、その「元データ」を見たくなるのですよね。
それは「新聞記事」では、「調査内容のエッセンス」をギュッと絞って書いていますが、「元データ」にはそれ以外にも興味を引く内容が多々あることが多いのですよ。
そこで今回の「ベネッセコーポレーション」の、「子どもの生活と学びに関する親子調査」を探して読んで見ましたら、以下の内容が記載されていましたよ。
◎「読書をしない」(小数点以下切り捨て)
➀「小1~少3生」
・「2015年:19%」
・「2024年:33%」
・「差 :14㌽増加」
②「小3~小6生」
・「2015年:25%」
・「2024年:47%」
・「差 :22㌽増加」
③「中学生」
・「2015年:37%」
・「2024年:59%」
・「差 :22㌽増加」
④「高校生」
・「2015年:54%」
・「2024年:69%」
・「差 :15㌽増加」
https://benesse.jp/berd/special/childedu/pdf/newsLetter/newsLetter_20251020.pdf
(出典:ベネッセコーポレーション 子どもの生活と学びに関する親子調査より:10月27日利用)
へー、「2015年から2024年の10年間」で、小中高生の全部で「読書なし」が激増していますよ。
( ¯ㅿ¯)へー
これが冒頭の記事の「読書をしない(0分)小中高生が半数を超えている」との内容ですよね。確かに「全部を合計して平均すると52.7%」になっていますよ。
しかも「社会に好奇心が高まる時期の高校生」では、何と「7割が読書なし」ですよ。増えていますよね。
コロちゃんの子どもたちが「高校生」だった頃には、わが家の本だなから「司馬遼太郎」の「竜馬が行く」や「坂の上の雲」などを持ち出して読んでいましたね。
本来ならば、子どもたちは「年令に合わせて自然に読書するものだ」と、コロちゃんは思っていましたけれど、最近は「読書なし」がここまで進んだとは知りませんでしたよ。
そして、その逆に「増えているのがスマホ時間」ですよ。これは予想通りですよね。下記でしたよ。
◎「あなたは学校のある日に、1日スマホをどのくらい使っていますか?」
(小数点以下切り捨て)
➀「小4~小6生」
・「2015年:11分」
・「2024年:33分」
・「差 :22分増加」
②「中学生」
・「2015年:43分」
・「2024年:95分」
・「差 :52分増加」
③「高校生」
・「2015年: 95分」
・「2024年:138分」
・「差 : 43分増加」
https://benesse.jp/berd/special/childedu/pdf/newsLetter/newsLetter_20251020.pdf
(出典:ベネッセコーポレーション 子どもの生活と学びに関する親子調査より:10月27日利用)
おー、こちらの「スマホ時間」も増えていますね。
(o゚Д゚)オー
これが冒頭の記事の「スマホ使用時間が小4~高校生で22~52分増えた」の内容ですよね。
これはもう明らかですよね。「読書時間」が無くなったのは「スマホ時間」が増えたからだと、一目でわかるデータですよ。
だけど、今さら「子どもたちのスマホ時間を制限する」なんてことができるのでしょうか?
ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?
「小学生」までは、何とか言うことを聞かせられるかも知れませんが、「中高生」では絶対ムリだとコロちゃんは思いましたよ。
この「ベネッセ」の「親子調査」では、「保護者」が「自分の能力を高めるための勉強」をしたり「家庭教育の中で本や新聞を読むことの大切さを伝えている」と、「子どもの読書をしない割合が低い」と書いてありましたよ。
だけど、コロちゃんは「自分が勉強している姿を見せる親御さん」は、そんなにいないと思いますよね。
だって「小学生の親ごさん」って「30代~40代」でしょう。一番「仕事と子育てに忙しい忙しい時期」ですよ。
そんな時に「父親・母親がゆっくり勉強している時間」などあるはずもないですよ。
それに「家庭教育の中で本や新聞を読むことの大切さを伝えている」ことは出来なくはないですが、そもそも皆さんは「新聞」を読んでいるのでしょうか?
現在の「新聞購読率」は、全国紙は20%そこそこですよ。
新聞を読んでいない「親御さん」が、子どもに「新聞を読むことの大切さを伝える」はずもないですよね。
それはちょっと「無理ゲー」というものだとコロちゃんは感じましたよ。

3.「読書する子どもが減るのは、もう防げないよ」
さて、上記で「子どもたちの読書なしが増えている」ことを見てきましたが、コロちゃんはもう「読書なしの増加」は防げないと考えています。
その理由は「出版販売額のトレンド」です。過去野「日本の出版販売額の推移」を見てみましょう。下記でしたよ。
◎「出版販売額の推移」
➀「1996年:2.6兆円」(ピーク)
②「2014年:1.7兆円」
③「2020年:1.6兆円」
④「2024年:1.5兆円」
上記のように、「日本の出版販売額」は「➀1996年の2.6兆円」をピークとして、昨年「④2024年の1.5兆円」まで「1兆円以上」も減少しているのですよ。
この「出版販売額がピーク」だった1996年は、日本人の「平均所得金額」の以前のピークだった「1997年の461万円※」に近い年です。
(※2024年の平均所得は478万円で27年ぶりに更新した)
一言で言うと、「豊かな時代(1980年代)の名残が残っていた1996年」までは、みんな「本を読んでいた」のですよ。
その後「年々所得が下がり続けた30年間」の中で、徐々に「本を読まなくなってきた」とコロちゃんは考えていますよ。
やっぱり「読書」は、「生活に余裕ができると増えるもの」なのでしょうね。

4.「読書なしだと、多様な知識や教養が得られないよ」
さて「本を読まない子どもや大人が増える」と、どのような影響があるのでしょうか。コロちゃんは、「学がないただのおじいちゃん」ですから、ハッキリしたことは分かりませんよね。
しかし、「小説や歴史書」を読まないと「時代を超えた多様な知識と価値観」が得られられないと思われますよね。
そもそも「人間の不幸」などは数が限られています。
今コロちゃんが思いつくのは、「貧困・病気・人間関係の悩み・失敗や挫折など」ですよね。この「4種類」だけで、ほとんどの「人間の不幸」が説明できるのではないでしょうか。
これへの「対処方法」は、ほとんどが「小説」の中で詳しく書かれていますよ。
また「歴史書」の中にも、同じように「過去の人間がどのように挑んできたのか」が書き込まれていますね。
これらの知識は、総称して「教養」と呼ばれていますが、この言葉はコロちゃんはあまり好きではないのですよ。
何となく「教養と言う言葉」には、「上流階級の香り」が漂っていように思えるのですよ。
だから、もってズバッと「小説を読めば人生の生き方の勉強になるよ」と散文で書きますよ。
皆さん「小説」でも「歴史書」でも「コミック」でもいいですから、たくさん読むことが「人生を豊かにする道ですよ」と、コロちゃんは主張しますよ。
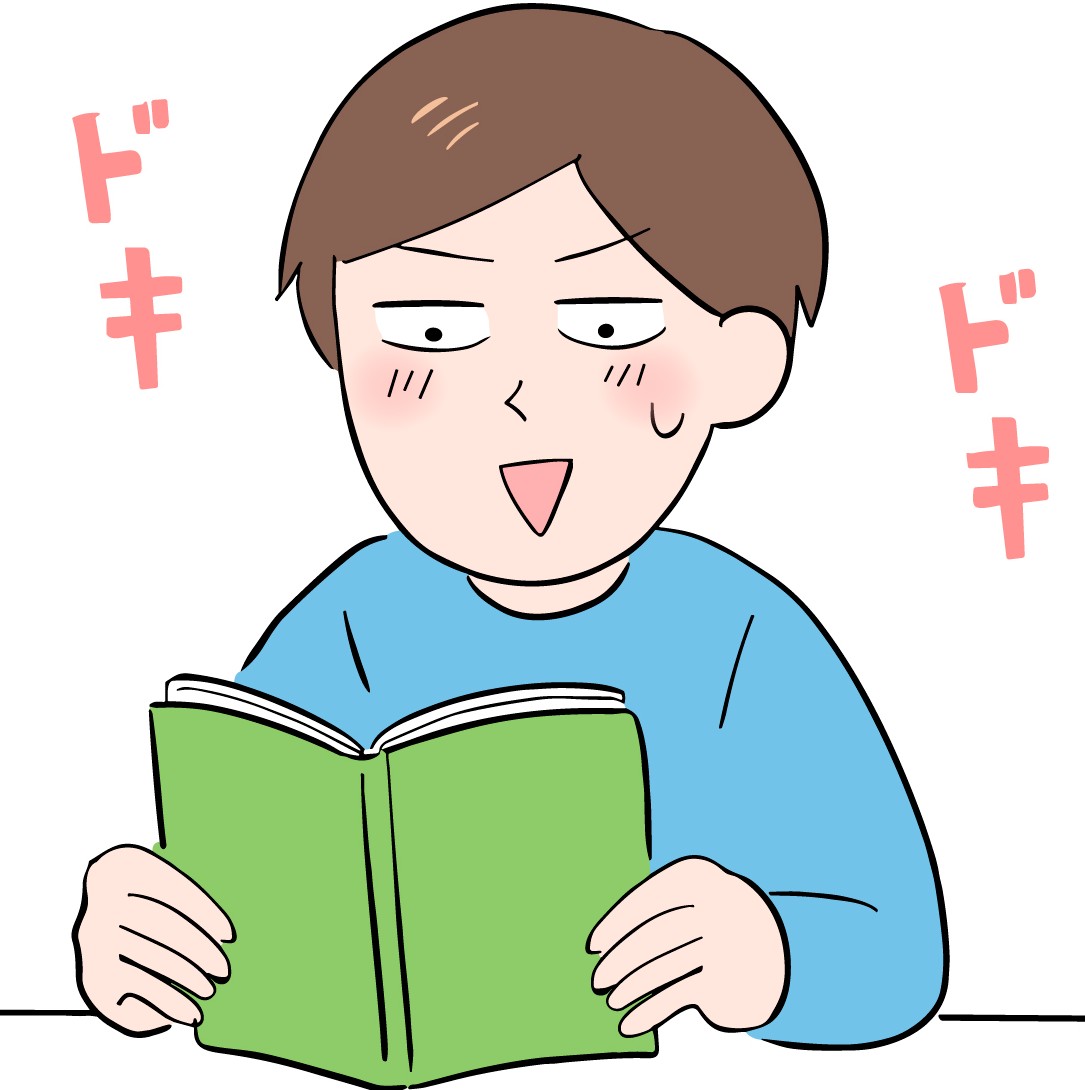
5.「子どもたちに本を読んでもらいたいけど・・・」
今日は、「小中高生の半数が読書0分」をテーマに書いてみましたが、ここでちょっとコロちゃんの考え方を書きますね。
コロちゃんは、自分では「読書が好き」ですし「1日中本を読んでいても飽きない人」ですので、もちろん「子どもたち・他の大人の方たち」にも読書をお勧めしていますよ。
だけど、今の子どもたちにいくら「言葉で言ってもムリだ」と思うのですよ。
よく「馬を川に連れて行けても、水を飲ませることはできない※」と言われますよね。
(※イギリスのことわざ:機会を提供することはできても、後は本人の意志次第)
だから「本を読め」と言っても、「本を買って置いて」あっても、子どもたちは本を読んでくれるとは限りませんよね。
しかし、目の前にいつも置いてあったら、何かの機会に「手を伸ばして読んでみる」かも知れません。
上記で書いたコロちゃんの息子たちの「司馬遼太郎の本の読書」などは、いい例ですよ。
コロちゃんは、一時「司馬遼太郎の本に耽溺した時代」があったのです。確か1980年代頃のことでしたね。
その為に自宅には「大量の司馬遼太郎の文庫本」が山積みされていたのです。
これらの本を子どもたちが読んでいたのは、確か「高校生の頃」でしたよね。あれも自宅に置いてなければ、ひょっとして読む機会はなかったかもしれませんね。
そんな記憶があるコロちゃんは、2年前に「長男一家のなーちゃん(当時小3)」に「アーサーランサム全集1セット」をプレゼントしています。
この「アーサーランサム全集(全20巻)」とは、コロちゃんがもう60年近く前の「中学生」の頃に読んでいた本です。
この本は、「児童文学」のジャンルに入ると思いますが、とても楽しく面白い物語なんです。
この「アーサー・ランサム全集」は、少年と少女が大勢集まって、キャンプやヨットで遊ぶ話です。
イギリスの「ウィンダミア湖」と「ノーフォーク湖沼地帯」が活動場所ですが、これは実際に存在する場所です。
本当に、内容がリアルなんです。いかにもありそうだけど、ちょっと現実にはなかなかできないような、「少年と少女の冒険と探検の物語」です。
子どもたちは、キャンプやヨットを通じて知り合い、遊び、冒険をし、そこでちょっとした事件が発生します。その中で、子どもそれぞれの個性と葛藤が実に生き生きと描かれているんです。
小説が書かれたのは1900年代前半でしょう。日本では、「日露戦争(1904年)から満州事変(1931年)」のあったころかと思います。
小説の中には年代は出てこないのですが、「大英帝国全盛の時代」の、比較的上の階級の子どもたちと、一般の子どもたちが入り混じって活躍する少年少女物語です。
今から100年ほど前のお話しなのに、ちっとも内容は古くないのです。少年少女が今でもワクワクする普遍的な内容のお話しだと思いますよ。
コロちゃんは、常々「長男・次男一家」の子どもたちには、この「アーサーランサム全集」をぜひ読んでもらいたいと、思っていました。
そして、「物語を読む楽しさ」、「小説を読む楽しさ」、「本を読む楽しさ」を、できるだけ早く身に着けてもらいたいと思っていたのです。
それでコロちゃんは、「長男一家のなーちゃん(当時小3生)」にこの「アーサーランサム全集全巻」をプレゼントしたのですが、その後何も言ってこないところを見ると多分「積読」しているのでしょう。
だけど、コロちゃんはそれでも良いと思っていますよ。そもそも「読書の楽しさ」は人から教えてもらえられるものではないのですよ。
子ども自身が、何かのきっかけで「その本」を手に取って楽しさを感じなければ「読書の楽しみ」は身につくものではないと思いますよ。
だからコロちゃんは、「次男一家のすーくん(現在5歳)」にも、彼が「小3生」になった頃にこの「アーサーランサム全集1セット」をプレゼントするつもりでいますよ。
そして「何かの切っ掛け」に、この本を開いてくれることを望んでいますよ。
やっぱり「子どもたち」には「川の水は自分でゴクゴク飲んでもらいたい」と、コロちゃんは思っていますよ。
下記のフォトが、コロちゃん収蔵の「アーサーランサム全集全20巻」ですよ。大人が読んでも楽しい物語ですよ。よろしかったら、是非お読みくださいね。
たぶんどこの「図書館」(児童書)」でも収蔵していると思われますよ。

6.「コロちゃんと読書の傾向」
さて今日の最後の「コロちゃん話」は、コロちゃんの最近までの読書傾向をちょっと書いてみますね。
コロちゃんは「1970年代と1980年代」には「小説」しか読まなかったのですよね。そして「面白い小説」を読むと、その作家の全作品を全部読んだのですよ。
「松本清張・大藪晴彦・西村寿行・森村誠一など」の流行作家の本はずいぶん読みましたよ。その後は「司馬遼太郎・山崎豊子・本田勝一」などの歴史関連書が続きましたよ。
そして「1990年代」になると「知の巨人と呼ばれた立花隆」の「サル学の現在(1991年)」に出会ったのですよ。
いやー、面白かったですね、夢中で読みましたよ。直ぐに「図書館」にある「古人類学の本全部」を借り出して読みましたよ。20~30冊はありましたよ。
この「立花隆」は膨大な量の本を出版していたのですよね。その中に「天皇と東大(2005年)」がありました。
この本は「明治期から戦前期の大日本帝国の実態」を赤裸々に描き出していたのです。この本を読んでからコロちゃんは、「明治~戦中までの歴史」に興味を持ち始めました。
この時には、図書館にあった「明治期~戦前期の本」から、200冊は読み漁りましたよ。
特に面白かったのは「勝海舟:2010年:松浦玲」と「遠い崖ーアーネスト・サトウ日記抄(全14巻):2008年:萩原延壽」でしたね。
その後の「2011年の福島原発事故」の後では、「図書館」の「原発関連書籍」を120冊程度読みふけりましたよ。
これだけ読み込むと「右の論理」も「左の論理」も、その元データが分かりますから、「イデオロギーぬきの全体像」が把握できた気がしましたよ。
そして、その後は現在に至るまで「経済と社会学の本」を、新刊に絞って読んでいます。その理由は「経済も社会学」も「賞味期限」があるのですよね。
つまり、新しいデータが次々と上書きされて出てきますから、それに合わせた「経済・社会学の新解釈」が新刊として出てくるのですよね。
そんな感じで、現在のコロちゃんはまだまだ「本を読みたい」と思っていますよ。
出来れば「コロちゃん最後の日」には、ベッドの上で本を片手に持ちながらバッタリと逝くのが理想ですよね。
ただ、その場合には誰かに「図書館に本を返していただきたい」のですが、たぶん「長男一家家長様のお仕事」になるかと思われますね。
嫌がるかなー?
それより「図書館」が怒るかなー?
コロちゃんは、もう死んじゃってるから、怒られても怖くないもんねー。
( ◍´罒`◍)ゞエヘヘポリポリ
皆さん、ご迷惑おかけしますね。これがコロちゃんの「読書の傾向」でしたよ。笑いながら読んでいただければ嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします。
(^_^.)
おしまい。








コメント