おはようございます。今朝コロちゃんが、朝起きたらもう「6時半」を過ぎていました。いつも「5時起きのコロちゃん」としては、久々の「大幅な寝坊」ですよね。
コロちゃんは、あわてて「シャワーとワンコ散歩」を済ませましたよ。どうやら「昨日の前立腺がん治療の大学病院の診察」で、思ったよりも疲れていたようでしたよ。
今日は「ジムでの太極拳の日」でしたから、コロちゃんはあわてて「ブログを投稿」してから、急いで出かけましたよ。
そうしましたら、なんと「ジムの太極拳の先生が体調不良でお休み」との張り紙が玄関先に貼ってあったのです。
コロちゃんは「ガッカリ」しましたよ。なんか一つ躓くと「連鎖する」とはどういう「法則」なのでしょうね。
まあ「こんな日もあるさ」と、気楽に考えることにしましたよ。だけど「今日はこれ以上変な事がないといいなー」と思ったコロちゃんでしたよ。
そんな「ガッカリコロちゃん」が、今日は「日本は物価・賃金が毎年上がる国に変身できるのか?」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「社会のエスタブリッシュメント(支配層)は今の日本をどう見ているのか?と、風景が様変わりした日本の社会」
☆「きっかけはコメ価格とコメ政策だよと、春闘システムが瓶の蓋になっているよ」
☆「春闘賃上げ5%じゃ、全然足りないよと、物価と賃金が上がる社会に変身できるのか?」
☆「コロちゃんと、居間に置いたパソコン」

1.「社会のエスタブリッシュメント(支配層)は今の日本をどう見ているのか?」
コロちゃんは、最近書いた『【経済考】誰も「物価高」を止めようとしないよ』の誤字・脱字の校正をしていた時に、ちょっと考えたことがあったのですよ。
それは「社会のエスタブリッシュメント(支配層)の方たちは、今の日本をどう見ているのか?」ということなのですよね。
コロちゃんは、「物価と賃金が上がらなかったデフレ経済の30年間(1992~2021年)」の方が、今よりも全然「生活が楽だった」と思っています。
ですから「日本」が現在のような「物価が上がる国・暮しにくい国」へと変わったのは、つい先日の「2022年の春」からの「わずか3年前」からなのですよね。
しかし、その「わずか3年間」は、それ以前の「30年間の日本社会」とは様変わりしたというのがコロちゃんの実感ですよね。
そこで今日は、ちょっとコロちゃんが「社会のエスタブリッシュメント(支配層)」は、この「物価が上がる日本」をどのように見ているのかを、大胆に想像してみたいと思いますね。

2.「風景が様変わりした日本の社会」
今日は「物価が上がらなかった30年間の日本」と「物価が上がるようになったここ3年間の日本」の姿を比べながら、いろいろ考察してみましょう。
この時の視点は「社会のエスタブリッシュメント(支配層)の眼」ですから、歴史を俯瞰するような見方となりますよ。
最初は「物価上昇率の長期推移」を見ておきましょう。下記でしたよ。
◎「消費者物価指数の推移」
①「1992年~2013年:-1.4~~+1.8%」
②「2014年 : +2.7%」
③「2015年~2021年:ー0.2%~+1.0%」
(以上が失われた30年)
(以下から物価が上がる社会へ変貌)
④「2022年 :+2.5%」
⑤「2023年 : +3.2%」
➅「2024年 : +2.7%」
⑦「2025年1~3月:+3.8%」
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je25/pdf/p040004.pdf
(出典:内閣府 令和7年度 年次経済財政報告 消費者物価指数より:11月2日利用)
ふーん、なるほど「➀1992年から③2021年までの30年間」は、「②2014年の+2.7%」を除くと、全て「-1.4%~+1.8%の2%以下」に収まっていますね。
( ̄へ ̄|||) フーン
しかもコロちゃんがポチポチ調べてみると、その「30年間の内の10年間はマイナス値」ですよ。まさにこの30年間は「デフレ大国日本」でしたね。
それが「2022年春」から一変して、「④2022年~2024年の3年間は+2.7%~+3.2%」と高い「物価上昇率」が出現しています。
コロちゃんは、これを見ていて「社会風景が一変した」と思いましたよ。つまり「一時的な物価上昇」ではなく「構造的な物価上昇だ」と「再認識した」のですよ。
この「社会構造の再認識」で、どのようにコロちゃんの見方が変わったのかを次に書いてみますね。
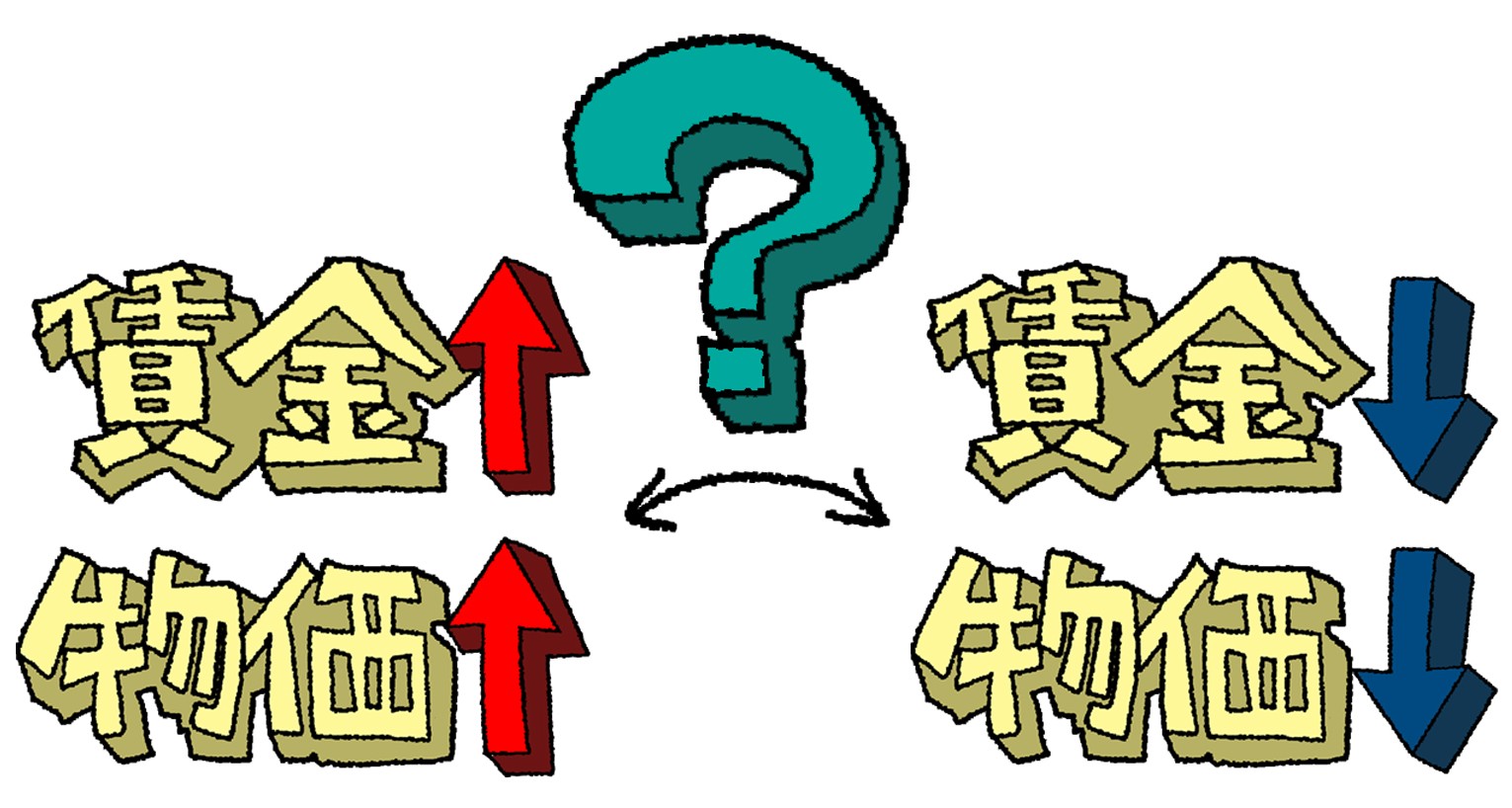
3.「きっかけはコメ価格とコメ政策だよ」
コロちゃんは、つい先日にこのブログで「石破元総理」の「(5キロで)3000円台にならなければならない」と言う「コメ政策」が、わずか2ヶ月で「大転換された」ことを書いています。
現在の「高市総理」の下の「鈴木農相」は、「来年2026年度の主食米の生産目安」を「増産から減産」に真逆の方向に変えることを表明しています。
コロちゃんは、これを「コメの値段が下がって喜ぶ消費者目線」から、「コメの値段が上がって喜ぶ生産者視線」への転換とみていました。
しかし、ちょっと考えてみれば「コメ生産者」にとっては、ここ3年間の「物価の上昇」によって「肥料・燃料・人件費の増加」があるわけですから、コメの値段は上がって欲しいわけですよね。
これを「消費者と生産者の対立」とみる見方は、正しくないと思い直しましたよ。
それでは、この「コメの値上げを巡る問題をどう捉えたらよいのか?」ですけれど、コロちゃんは「物価が上がらない社会での制度」がもう時代に合わなくなってしまったと考えましたよ。
すなわち、今までの全ての「制度・システム」が「過去30年のデフレ時代」に適応していましたから、「物価と賃金が上がる社会」に変ったことで、以前の制度がそぐわなくなってしまったのですよ。
だから「コメ価格」も、3年まえから「少しずつ上昇するような制度」に変えなければならなかったのでしょうね。
それに失敗したから、前年比で100%上昇なんて「コメ価格の暴騰」を許してしまったのでしょう。それではどのようにすれば良かったのかは、「農政に素人のコロちゃん」にはわかりませんよ。
しかし「農政の担当者」が、「過去30年のデフレ時代」と「ここ3年のインフレの時代」への変化を認識していなかったから、現在のような事態となったとコロちゃんは考えましたよ。

4.「春闘システムが瓶の蓋になっているよ」
さて上記のように「物価と賃金が上がらなかったデフレ経済の30年間(1992~2021年)」と、それ以後の「物価が上がる時代(2022~2025年)」に変ってしまった「日本」を見てきました。
その中では、「同時に賃金が上がる時代」に変身しなければならなかった「日本」が、思うように「変身できず」にいますよね。
コロちゃんは、この原因の一つに「春闘システムの変貌がある」と見ましたよ。
この「春闘」と言うシステムが、「日本」で定着したのは高度成長期の入り口にあたる「1955年」です。
欧米の場合は「企業」を横断した「産業別組合」が「賃上げ決定」に大きな力を持っています。
しかし「日本」の場合は「企業別組合」がほとんどですから、「弱い交渉力」を補うために「春に同時に賃上げ要求」をするようになりました。
当時(1950年代)では「春闘」で高い賃上げ額を得ることで、「全産業の労働者の賃上げ額」を引き上げることができるとされていましたね。
その後、その「春闘で高い賃上げ額を勝ち取るシステム」が変質しました。それは「2000年代初頭から始まった「春闘ベアゼロ合意」からです。
1990年代末の「金融危機で危機感を抱いた企業経営者たち」は、「連合」と「雇用は守るが賃上げはしない」と言う「ベアゼロで合意※」を密約したとされています。
(※経済学者の早川英男氏の推理)
この「連合と経団連」の「ベアゼロ合意」が本当にあったのかはわかりませんよ。だけど、過去30年の「春闘の歴史」を見ると、その事実関係はあきらかですね。
この「ベアゼロ密約」は、実証されているのですよ。下記ですよ。
なお「春闘賃上げ率」は、「定期昇給(2%)」と「ベースアップ(ベア)」で構成されます。本当の「賃上げ部分」は「ベアのみ」です。「定期昇給(2%)」は入りません。
その理由は後で書きますね。だから下記の数字の「2%以上」が「真水の賃上げ率」ですよ。
◎「主要企業春季賃上げ率」
➀「2001年:2.01%」ココからベアゼロ
②「2002年:1.66%」
③「2003年:1.63%」
➃「2004年:1.67%」
⑤「2005年:1.71%」
⑥「2006年:1.79%」
⑦「2007年:1.87%」
⑧「2008年:1.99%」
⑨「2009年:1.83%」
⑩「2010年:1.82%」
⑪「2011年:1.83%」
⑫「2012年:1.78%」
⑬「2013年:1.80%」
⑭「2014年:2.19%」
⑭「2015年:2.38%」
⑮「2016年:2.14%」
⑯「2017年:2.11%」
⑰「2018年:2.26%」
⑱「2019年:2.18%」
⑲「2020年:2.00%」
⑳「2021年:2.18%」
㉑「2022年:2.20%」ベアゼロ終焉
㉒「2023年:3.36%」新時代が開始
㉓「2024年:5.33%」
㉔「2025年:5.52%」
(出典:独立行政法人:労働政策研究・研修機構:早わかり グラフでみる長期労働統計より:11月2日利用)
ふー、疲れた。やっと書き終わったよ。
ε- ( ̄、 ̄A) フゥー
ふーむ、「➀2001年:2.01%」から「㉑2022年:2.20%」の23年間は、ほぼ「ベアゼロ」ですよね。
( ̄へ ̄|||) フーム
上記の「春闘の賃上げ率」は、「定期昇給(2%)」+「ベースアップ」で構成されます。この「定期昇給分(2%)」は、実は「賃上げ」ではありません。その理由は以下ですよ。
だいたい「日本企業の定期昇給分は2%程度」と言われています。
この「定期昇給(2%)」は、毎年一定金額が上昇しますが、経営者にとっては「毎年高い給与の定年退職者」と「低い給与の若い新入社員」が交代しますので「賃金総額」は変わりません。
ですから「ベースアップ」こそが、「真水」の経営者の「負担増加分」なのです。
ここに「定期昇給のマジック」があります。
「定期昇給2%+ベアゼロ」だと、「社員は年齢が上がるごとに毎年2%の賃金上昇」を実感しますが、経営者にとって「賃金総額は変わらない」のです。
その視点で、上記を見ると「ハッキリベアゼロが終焉した」のは「㉒2023年:3.36%」からです。ここまでの「23年間」に渡って「春闘ベアゼロ」が続いたのです。
ここでコロちゃんの視点ですが、上記で「春闘で高い賃上げ額を得ることで全産業の労働者の賃上げ額を引き上げることができるとされていました」と書きましたよね。
元々の「春闘の機能」とは、「全国の雇用者の高い賃上げ額の相場形成」にあったのです。
それが2001年には、「大企業の雇用確保とベアゼロの取引材料」になってしまったのです。
その結果、上記の「2001年~2022年の23年間」は、「中小企業の雇用者」にとって「春闘相場2%前後」が「賃上げの上限」となることになってしまいました。
これではまるで「びんの蓋」ですよね。
「春闘相場形成」は、1955年以来の毎年の風景でしたから、全産業の賃上げ相場の「ベンチマーク」として確立されていたのです。
それが「デフレの30年間」は、その機能が当初の目的と真逆な「中小企業の雇用者の賃上げを抑える役割」を果たしてしまったというのが、コロちゃんの考えですよ。
それでは、現在の風景である「物価が上がる時代(2022~2025年)」を、「日本」は「賃金も上がる時代」に生まれ変わることができるのでしょうか。
次に、このことを書いてみますね。

5.「春闘賃上げ5%じゃ、全然足りないよ」
最初に「物価の安定をお仕事」とする「日本銀行」は、「安定的な2%の物価上昇率と整合的な賃金上昇率の水準は3%程度」としています。
ただこれは「定期昇給」を含んでいませんから、上記の「春闘賃上げ率」と比べてみるためには、「2%の定期昇給」をプラスしなくちゃなりませんよね。下記となりますよ。
◎「日銀が目指す物価と賃金のあるべき姿」
➀「物価上昇率: 2%」
②「賃上げ率:3%+定昇2%=5%」
この上記の「計算式」が、「岸田前総理・石破前総理・植田日銀総裁」が「5%以上の賃上げを」とおっしゃっていた背景です。
しかしコロちゃんは、「ちょっとまった✋」って言いますよ。
だって現実を見ると「➀物価上昇率が2%」じゃないんだもん。

➀「賃上げは6~6.8%が妥当か?」
「物価上昇率」にはいくつかの種類がありますが、この場合は「実質賃金」の算定に使われる「持ち家の帰属家賃を除く物価上昇率」が適するでしょう。
下記に「物価が上がる時代」になった「持ち家の帰属家賃を除く物価上昇率」を書き出しますね。
◎「持ち家の帰属家賃を除く物価上昇率」
➀「2022年:3.0%」
②「2023年:3.8%」
③「2024年:3.2%」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r07/2508r/dl/pdf2508r.pdf
(出典:厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和7年8月分結果確報より:11月2日利用)
おー、全然「2%以下」じゃないですよ。
(o゚Д゚)オー
上記を見ると「2%より1.0~1.8㌽高い」ですよ。これじゃあ「日銀の目指す賃上げ率」は5%じゃなくて、「6~6.8%」じゃなきゃなりませんよね。
やっぱり「日本が物価と賃金が毎年上がる国」になるためには、「賃上げ5%」じゃ全然足りないという「風景」が見えてきましたよ。

②「賃上げ5%はホントなのか?」
ここで「賃上げ6.8%にすれば良い」と言われたら、コロちゃんは「ちょっとまった✋」って、また言いますよ。
それはそもそも「昨年2024年の賃上げ5%はホントに実現しているの?」と思ったからですよ。
だって、「春闘の賃上げ率は高い」のですが、「厚生労働省」が発表している「現金給与総額の前年比」は、そんなに高くないのですよ。少し前の「2022年からの分」を下に書き出しますよ。
◎「春闘賃上げ率と現金給与総額の前年比」
(連合:春闘最終集計より)
(厚生労働省:毎月勤労統計より)
➀「2022年」
・「連合発表 :2.07%」
・「現金給与総額:2.0%」
②「2023年」
・「連合発表 :3.58%」
・「現金給与総額:1.2%」
③「2024年」
・「連合発表 :5.10%」
・「現金給与総額:2.8%」
④「2025年」
・「連合発表 : 5.25%」
・「現金給与総額:1.3~3.4%」(1~8月)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r07/2508r/dl/pdf2508r.pdf
(出典:厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和7年8月分結果確報より:11月2日利用)https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/yokyu_kaito/kaito/press_no7.pdf?5170
(出典:連合 春闘最終回答集計結果より:11月2日利用)
あらら、「春闘の賃上げ結果」は、「連合の発表」と「厚生労働省の現金支給総額」とで随分差がありますよね。
( ¯ O¯)アララ!
「岸田前総理」が始めた「経済の好循環」での「春闘賃上げ」が実際に動き始めたのは、上記で見ると「②2023年の春闘」ですよね。
しかし、この2023年の「連合発表は3.58%」ですが、「現金給与総額は1.2%増」でしかないですよ。翌年の「2024年は5.10%と2.8%」とこちらも差が大きいですよね。
この違いは、「連合は大企業の賃上げ率のみ」であることと、「厚生労働省の毎月賃金統計調査」は「賃上げ率が低い管理職(スタッフ職)」の賃上げ率も入っていることがあるようですよ。
この点はコロちゃんもビックリしたのですが、現在の「企業」では「管理職内での選別」が進んでいるようなのですよ。下記でしたよ。
◎「管理職の賃金増加率:2024年」
➀「部長級:5.2%増」
②「課長級:4.3%増」
③「管理職中のスタッフ職」
(指揮命令系統に属さない職)
・「勤続20~24年:3.2%増」
・「勤続25~29年:3.5%増」
・「30年以上 :2.5%」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD145RT0U5A310C2000000/
(出典:日経新聞 2025年3月25日記事 実態映さぬ賃上げ集計 中小企業の動向つかみきれずより:11月2日利用)
上記のように、「連合賃上げ率」では計算に入っていない「管理職の賃上げ率」も計算している「毎月勤労統計調査」では、逆に「賃上げ率」が下がってしまっているのですよ。
なんかコロちゃんは、「中年管理職の悲哀」を感じましたよ。この方たちは、「30代・40代」では「サービス残業」で企業に貢献してきたんでしょうね。
それが「指揮命令系統」から一旦外れたら、たちまち「賃上げ率」が下げられてしまったとはね。可哀想に・・・トホホ。
おっと、話しがそれちゃいましたね。
\(-\)(/-)/ ソレハコッチニオイトイテ…
とにかく「連合・経団連発表の賃上げ5%以上」は、まったく「現場の実態」を反映していませんよ。
その実態は「厚生労働省発表の毎月賃金統計調査(賃上げ率が低い方)」の方が正しいとコロちゃんは思いましたよ。
そうなると、どうやったら「日本全体が5%以上の賃上げが出来る社会」に変えることができるのかという未曽有の課題に挑戦することになるかと思われますよ。
出来なきゃダメだよね?
はて、できるのかな?
できたらいいね?
うーむ。
( ̄へ ̄|||) ウーム
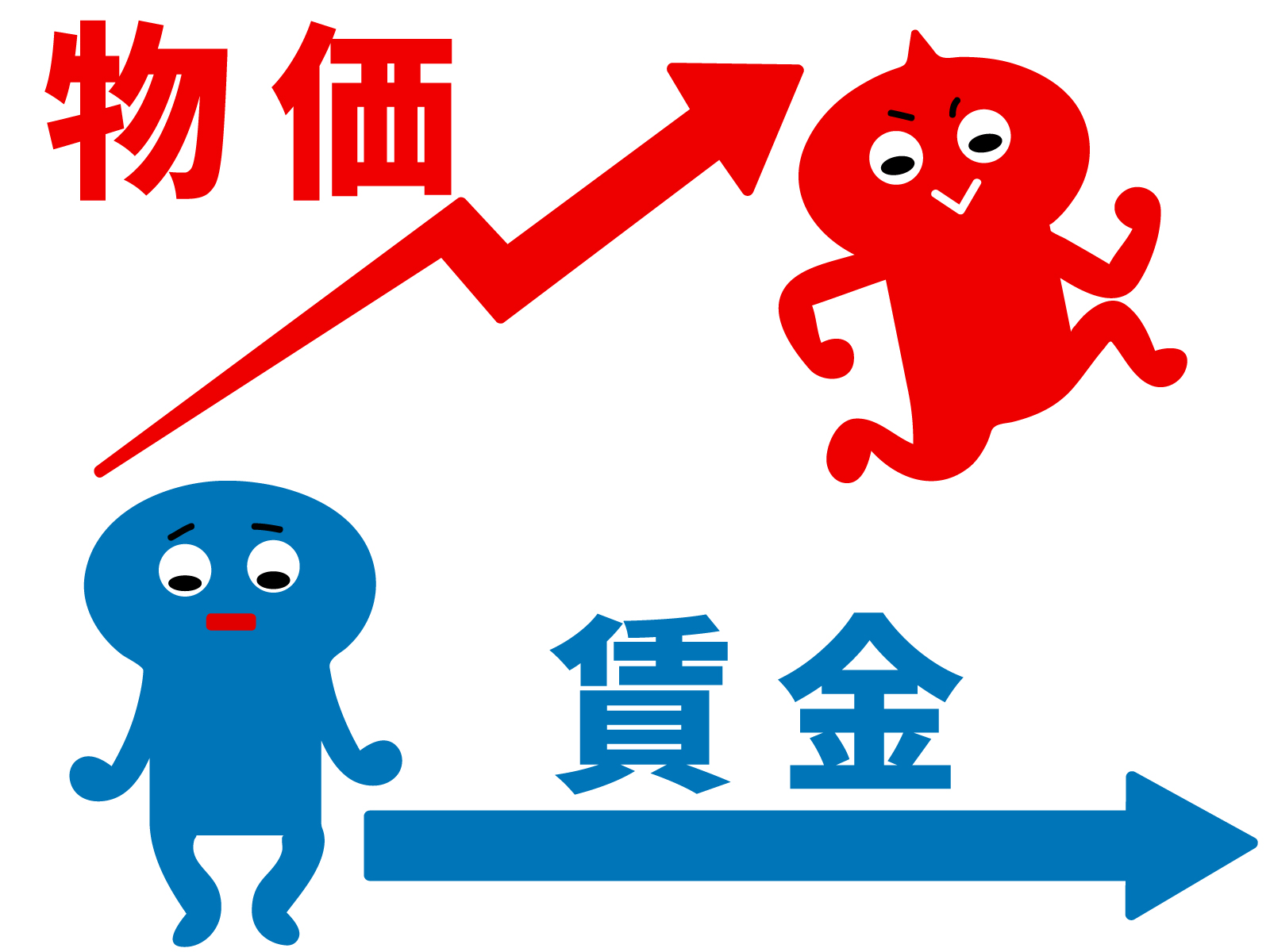
6.「物価と賃金が上がる社会に変身できるのか?」
さてここまで書いて来て、今「社会が変わらなくてはならないこと」を感じていますよ。
上記で書いた「コメ価格とコメ政策の右往左往」と「春闘の賃上げシステムの破たん」は、それぞれ個別の問題ではありません。
つまり「ここ30年続いた物価と賃金が上がらない社会」に「適合していた諸制度」が、「物価と賃金が上がる社会」に向かって次々と破綻していく風景ですよ。
このような視点で見ると、これは「コメと春闘」だけの問題ではないことに気が付きます。
たとえば「コロちゃんの生活の支えである年金制度」も、現在のシステムでは「物価に追いつかない賃上げ(改定額)」しか得られない不十分な制度であることに気が付きます。
今日は、ちょっと長くなりましたから「年金制度」についてはまた別の機会に書きますね。しかし「日本はここ30年の物価と賃金が上がらない社会」に慣れ過ぎました。
その為に「米と春闘・年金」以外にも、あらゆる「社会システム」が「物価と賃金が上がらない社会」に適するように社会の隅々まで行き渡っています。
それは、それなりに「居心地が良い社会」であったことは間違いが在りませんが、たぶんもう戻ることはないのでしょう。
そうなると、残された道は「日本は物価・賃金が毎年上がる国に変身できるのか?」が課題として、目の前に拡がっています。
今日の考察はここまでにしましょうね。コロちゃんの頭ではもう「お腹いっぱい」ですから、ちょっとまた深く考えてから整理して書いてみたいと思いましたよ。

7.「コロちゃんと、居間に置いたパソコン」
今日のテーマは、「日本は物価・賃金が毎年上がる国に変身できるのか?」をテーマに考察してみましたよ。
ちょっとコロちゃん風情が扱うには、あまりにも「大きなテーマ」でしたから、明らかに「生煮えな内容」ですよね。また今度もっと「説得力のある議論」を書いてみたいですね。
今日の最後の「コロちゃん話」は、上記で書いた「2001年の連合と経団連のベアゼロの開始」頃の「コロちゃんちの話」を書きますね。
コロちゃんが、ちょっと「時代を俯瞰」して見るとこの2001年は「時代の転換点」だったと思うのですよ。
つまり「1991年のバブル崩壊後」の不況で、「1993年から新卒採用を激減させた大企業」が、それでも1990年代末に「金融危機」が進む中で、とうとう「2001年にベアゼロ」に踏み込んだのですよ。
この「1993年の新卒採用の減少」は、その後の2004年までのほぼ10年間続けられて「就職氷河期世代」を生み出しています。
この時点の「大企業」にしては、「終身雇用制度を放棄する」のか、それとも「ベアゼロ・非正規雇用の拡大に踏み込むのか」の選択だったのでしょう。
その結果を現在から振り返って見ると、「大企業は終身雇用を維持した」代わりに「社会には賃上げが23年間ほぼゼロと、非正規雇用者40%弱の風景が広がった」結果となっています。
これの「歴史的評価」は、まだもう少し時間がかかるのでしょうけど、コロちゃんは「いいところがなかった決断だった」と思っていますよ。
そんな「時代の転換点」だった「2000年のコロちゃんち」には、「新しいパソコン」が初めて入って来ていました。
当時のコロちゃんの長男(15歳)の「高校の入学祝い」として、本人が「パソコンが欲しい」と希望したのですよ。
もちろん「デスクトップ」の大きなパソコンでしたよ。「専用のラック」も購入しましたよね。
確か「NEC のVALUESTAR」だったかと思われます。お値段は35万円ぐらいだったような気がしますね。
この「パソコン」は、コロちゃんちの「居間の隅」にデンと置かれていましたから、その日から「家族全員(妻を除く)」が使うことになりました。
「長男・次男」は、「タイピング練習ゲーム」を声を出しながら毎晩遊んでいましたよ。
そしてコロちゃんは、当時「ボランティア」で参加していた「ボーイスカウト隊」の「資料や活動報告など」をこのパソコンを使って作成するようになりましたよ。
今から振り返って見ると、この「パソコン導入で良かった点」として、「家族の一体感の醸成」があったように思えますね。
コロちゃんちは、「2人の男の子」がいたのですが、どちらも「自分の部屋にこもりっきり」と言うことがありませんでした。
今振り返って思い出しても、「家族4人が居間でワイワイガヤガヤ」と騒いでいた記憶しかないのですよ。「騒がしい家族」でしたよ。
たとえ「居間でパソコンの取り合いをする」ことはあっても、「自分の部屋に籠って顔を合わせない」と言うことは一切なかった家族だったのですよ。
現在では「家族全員がそれぞれスマホを持つ時代」になっていますよね。
しかし「パソコン黎明期の2000年代初頭」のコロちゃんちでは、一昔前に「囲炉裏」の周囲に家族が集まっていたように、「一台のパソコンの周囲」に家族が集まってにぎやかに騒いでいましたよ。
コロちゃんは、そんな「我が家」が大好きでしたよ。あの頃は楽しかったなー。
(・_・;).。oO
今日の最後の「コロちゃん話」は、もう20年も前の昔話を「遠い目」で見る思いで書いてみましたよ。当時こんな家庭もあったと、笑いながら読んでいただければコロちゃんは嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします。
(^_^.)
おしまい。








コメント