おはようございます。今朝コロちゃんはワンコとの散歩は、家の「物干し場」に大量の洗濯物が干してある横を通って歩いてきましたよ。
昨日はコロちゃんの「次男とすーくん(5歳)」が帰省していましたので、布団のシーツなどの洗濯物が沢山ありました。
それで午後から洗濯したのですが、夜になってもまだ乾いてなかったのですよ。つい面倒になったコロちゃんは、昨日の夜も洗濯物を干しっぱなしに残していたのです。
今日は「秋晴れの天気」となるようですから、直ぐに乾くと思われますよね。
コロちゃんは、「お一人様のおじいちゃん」ですけれど「清潔感がある高齢者」を目指していますから、「毎日洗濯」をしているのです。だから「洗濯は苦はなりません」ね。
だけどコロちゃんは思うのですが、この「清潔感のある高齢者」って「なかなか達成が難しい」と思うのですよね。「洗濯済みの着衣」だけでは多分ダメなんでしょうね。
コロちゃんは「床屋さん」にも「2ヶ月に1回」キチンと通っていますし、後は「化粧品」ぐらいでしょうか?
いやいや、「化粧品」はちょっとコロちゃんには「ハードルが高い」ですよ。コロちゃんは「昭和のオヤジ」でしたから、そこまでは手が届きませんよ。
他になんか「清潔感のある高齢者」になる方法があったら、どなたか教えていただきたいコロちゃんでしたよ。
そんな「清潔感がある高齢者を目指しているコロちゃん」が、今日は「もう無制限な資本主義には厳しい規制が必要だよ」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「現在は資本主義と民主主義の危機だってと、日本は賃上げが出来ない社会システムだよ」
☆「労働時間規制の緩和を誰が望んでいるのか?と、日本は大インフレ時代へと変わったよ」
☆「コロちゃんと1970年代の年末年始」

1.「現在は資本主義と民主主義の危機だって」
コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「無制限な資本主義 是正を」との見出しが目に入りました。
この記事は「日経新聞の1面全部を使ったインタビュー記事」でしたね。
コロちゃんは、この記事の「副題」の「不平等が歪みを生む」にも共感を感じましたので、ジックリと読んでみることにしましたよ。
この「記事」は、「2001年にノーベル経済学賞を受賞した「アメリカのジョセフ・スティグリッツ教授」への「インタビュー記事」でしたよ。その主な内容は、下記でしたね。
◎「アメリカのジョセフ・スティグリッツ教授の主張」
➀「かつて資本主義と民主主義は共存すると考えられていたが、今は資本主義が分断や利己主義を助長し、民主主義と対立している」
②「無制限の資本主義は大きな不平等を生む」
③「資本主義の根幹は競争にあるはずだが、実際には独占資本主義に陥っている。経済力の集中は政治的不平等を招き民主主義に反する」
④「自由民主主義と市場経済は大きな緊張関係にある」
⑤「不平等の代償は政治や社会だけではなく経済にも及ぶ。より健全で教育を受けた労働力は生産性の高い労働力になる」
上記がコロちゃんが読んだ「ジョセフ・スティグリッツ教授のインタビューの概要」ですが、コロちゃんは最近の「日本の政治・経済情勢」にもピッタリ当てはまる議論だと感じましたよ。
上記のように「ジョセフ・スティグリッツ教授」は、現在の「世界の資本主義システム」が「民主主義と共存できないレベルに変質してしまった」と指摘しているのですよ。
記事では、以下の「グラフ」を添付していますが、数字で下記に記載しますね。
◎「世界の富は上位10%の富裕層に偏在している」
〇「所得」
・「上位10%:全体の50%を得る」
・「中位40%:全体の40%を得る」
・「下位50%:全体の10%を得る」
●「資産」
・「上位10%:全体の80%を保有」
・「中位40%:全体の20%を保有」
・「下位50%:全体の 数%を保有」
うーむ、上記を見ると「上位10%の層に〇所得の50%と●資産の80%」が集中してしまっていますね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
一度ここまで「不平等」が完成してしまうと、ここからの「再分配」は難しいでしょうね。
上記の「資産と所得の格差の拡大」が、世界中で「社会の分断」を生み出しているから「無制限な資本主義は是正されなければならない」と言うのが、「ジョセフ・スティグリッツ教授」の主張でしたよ。
コロちゃんは、「日本の社会の分断」は「始まったばかり」だと思っていますが、このまま進めば「アメリカの共和党と民主党の分断」のような光景が「日本でも出現しかねない」と思いましたね。
なお、この「日経新聞」の「無制限な資本主義 是正を」の見出しの記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
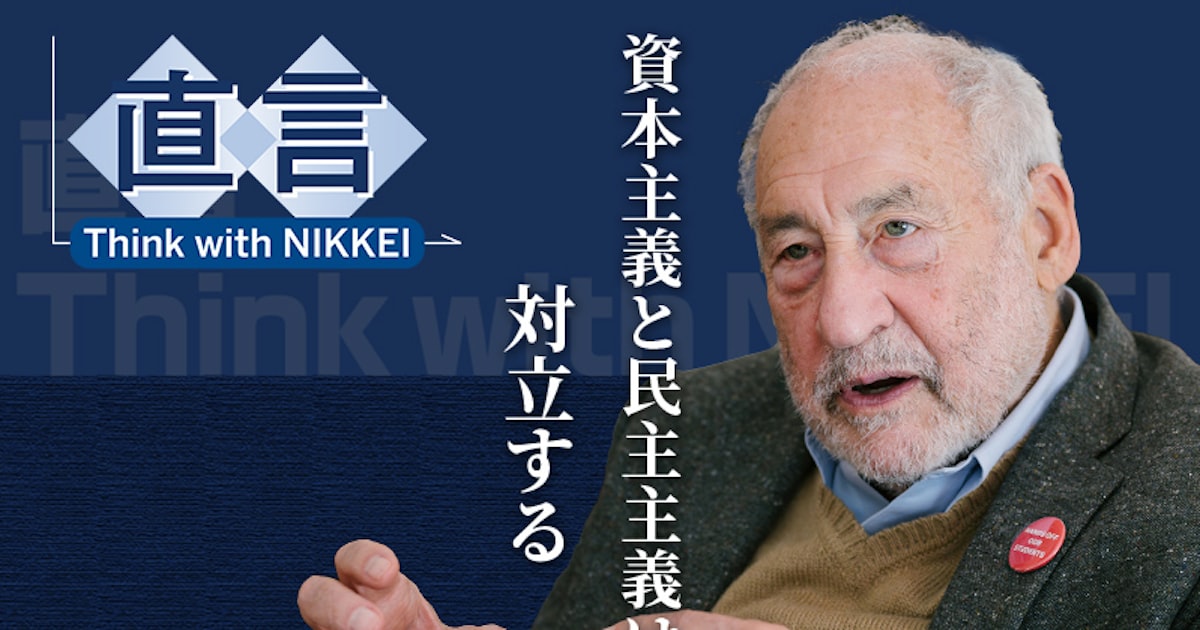

2.「日本は賃上げが出来ない社会システムだよ」
コロちゃんが、冒頭の「ジョセフ・スティグリッツ教授」の「無制限な資本主義 是正」の記事を読んで、真っ先に考えたのは「毎年の賃上げ」と「労働時間の規制緩和」についてでしたよ。
最初に「毎年の賃上げ」について書きますね。
まず「毎年の賃上げ」については、「岸田前総理」が「2022年の春闘賃上げ」から「経済界・労働界」に働きかけて「5%以上の賃上げ」を要請していました。
ところが、それから「2022年~2025年」と4年間経っても、一向に「雇用者全体の賃上げ」は実現していません。
ここ5年間の前年から「所得が上がっていない人の割合」は以下の通りです。ちょっと、ここで「2020年以降の所得の推移の様子」を見てみましょう。
◎「所得が前年と同額もしくはそれ以下の人の割合」
(59歳以下の就業者:少数点以下切り捨て)
①「2020年:59%」(コロナ禍)
②「2021年:56%」
(ココから好循環開始)
③「2022年:55%」
④「2023年:53%」
⑤「2024年:50%」
https://www.works-i.com/column/hataraku-ronten/detail040.html
(出典:リクルートワークス研究所 「失業」から「所得停滞」へ―50.8%の働き手のための労働政策の新たなる課題より:11月17日利用)
うーむ、「岸田前総理」が「経済の好循環(物価と賃上げの好循環)」が始まったのは、「③の2022年春闘」からですけど「賃金が上がっていない人の割合は55%」と半分以上ですよ。
( ̄へ ̄|||) ウーム
その後も「④2023年が53%」と「⑤2024年も50%」と「賃金は上がっていない人の割合」は、微減にとどまっていますよ。
これって「岸田前総理」と、それを継承した「石破前総理」の「政労使会議などの政策効果」がほとんどなかったってことじゃないですか。
コロちゃんは、この上記の「賃上げの実態」を「日本の賃上げシステム」が機能していない。つまり「日本の資本主義の限界が見えた」と感じていますよ。
かつて「デフレの時代(1990年代末~2021年)」には、「物価も賃金も上がらなかった」のですから、「賃上げシステム」がなくとも誰も困りませんでしたよね。
しかし、現在は3年前から「インフレの時代(2022年~2025年)」に転換しています。
現在の「物価が上がり続ける時代」に於いて、「賃上げシステムがない」ことは「日本資本主義の欠陥ではないか」とコロちゃんは考えていますよ。
「高市総理」は、「賃上げができる環境の整備」が重要と言っていますから、あくまでも「賃上げは企業が決めること」との姿勢ですよね。
しかし、コロちゃんは「いつまでたっても賃上げしようとしない企業」を見ていると、これは「資本主義の市場の失敗だ」と思っていますよ。
だから冒頭の「ジョセフ・スティグリッツ教授」の「無制限な資本主義は是正されなければならない」との主張は、コロちゃんの胸にストンと落ちましたよ。
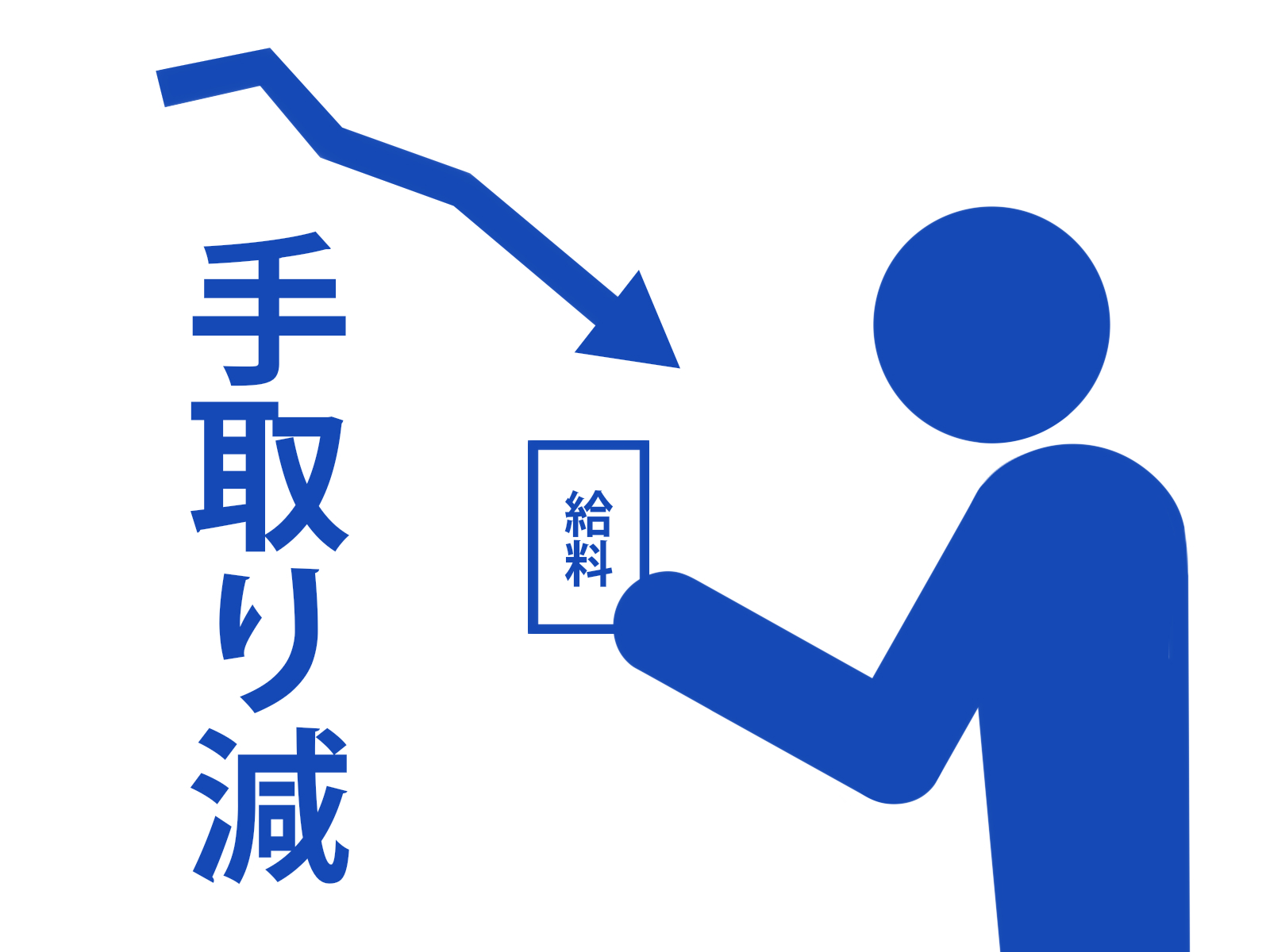
3.「労働時間規制の緩和を誰が望んでいるのか?」
もう1つコロちゃんが、冒頭の「ジョセフ・スティグリッツ教授」の記事を読んで考えたのは「労働時間の規制緩和」についてでしたよ
もともと「労働時間の規制」は、「典型的な資本主義の政治による規制」ですよね。
「日本」で「1日8時間・集48時間労働」に規制されたのは「1947年」です。その後「1994年」に「週40時間」に短縮されました。
しかし「残業規制」が始まったのは「2019年」です。まだたった「6年前」にことなのですよ。
「資本主義制度」は、「社会の生産力を上げる為の最適な制度」とされています。しかし「無制限の資本主義」は、逆に「社会と人間を破壊してしまう」とコロちゃんは理解していますよ。
コロちゃんは「昭和のオヤジ」でしたから、心情的には「高市総理」の「働いて働いて働いて働いて働いて、参ります」ってよくわかりますよ。
だって「昭和の時代」では、そのような「働き方」をコロちゃんもしていましたからね。だから、この「高市総理の言葉」には「責任感が強い」と好感を感じたりもしているのですよ。
しかし「高市総理」は、現在「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」を指示しているとされています。
もし、これらの「労働時間規制の緩和」が実現したならば、「企業経営者」は「(雇用者の)心身の健康維持は自己管理だよ」と言うに決まっていますよ。
「資本主義経済の理念」では、「法律のギリギリまでチャレンジすること」が経済合理性から言っても「最善の選択」となりますよね。
コロちゃんは、「法律の立案者」は「企業経営者の善意」をアテにすべきではないと考えていますよ。
冒頭の「ジョセフ・スティグリッツ教授」の「無制限な資本主義は是正されなければならない」との言葉を思い起こしてくださいね。
「長時間労働規制の緩和」は、この「無制限な資本主義への道」だとコロちゃんは考えていますよ。
「高市総理」は以下のご発言をなさっています。
「残業代が減ることによって、生活費を稼ぐために無理をして副業することで健康を損ねてしまう方が出ることを心配している」by高市総理(11/5発言)
「やさしい心遣い」ですよね。「女性総理」らしい素晴らしい心情だと思いますよ。コロちゃんは、その点は高く評価しますよ。
しかし、「労働政策」として「残業代が減ること」を心配するならば、「残業割増賃金率」を上げることを提案しますよ。
「日本」は世界の先進国の中でも、一番「残業割増賃金率が低い国」なのですよ。下記をご覧ください。
◎「世界の残業割増賃金率比較」
➀「日本」
「25%以上ただし、1か月で60時間を超える時間外労働については50%以上」
②「アメリカ」
・「50%」
③「イギリス」
・「規定なし一、般的には50%」
④「フランス」
・「25%、1週間で8時間を超える時間外労働については50%」
⑤「ドイツ」
・「規定なし、一般的に労働協約を超え1日の最初の2時間は25%、それ以降は50%」
➅「韓国」
・「50%」
https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/k-s-kouzou/shiryou/2th/shiryo4.pdf
(出典:内閣府 割増賃金の状況等についてより:11月17日利用)
うーむ、上記を見ると「日本」って「①~⑥の6ヶ国」の中で、一番「残業割増賃金率が低い国」なのですよね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
ほとんどの国が、「日本の25%」の2倍の「50%」を採用していますよ。
この「残業割増賃金率」を上げれば、「社員に無理な長時間労働」を強いるよりは、新人を雇用した方が安くつきますよね。
そうすれば「過労死」や「無理な副業」なども無くなり、みんなが幸せになりますよ。
これを見ても、コロちゃんは「無制限な資本主義は是正されなければならない」と、心から思いましたよ。
そもそも「残業時間を増やしたい」とする方は、そんなに多くないのですよ。下記をご覧ください。
◎「一般労働者:Q.残業時間を増やしたいか?」
(小数点以下切り捨て)
➀「増やしたい :4%」
②「やや増やしたい :6%」
③「このままで良い:63%」
④「やや減らしたい:12%」
⑤「減らしたい :13%」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001486603.pdf
(出典:厚生労働省 労働時間法制の具体的課題について①より:11月17日利用)
なーんだ、「残業時間を増やしたい」と言う労働者は、上記を見ると「10%」しかいませんよ。
( ̄o ̄)oナーンダ
だったら「残業規制を緩和したい」のは「企業経営者に皆さんたち」ですよね。そんなの社員に押し付けないで「自分が長時間労働」をやったらいいのにねー。

4.「日本は大インフレ時代へと変わったよ」
さて、ここでちょっとコロちゃんの考え方を書きますね。
コロちゃんは、「日本の社会」は「1990年代後半~2021年までのデフレ時代」から、3年前の「2022年~現在までのインフレ時代」に大きく転換したと考えています。
そして、この「インフレ時代」は、今後長く続くことになるとも思っています。
しかし、今まで長い間かかって築き上げられてきた「社会システム」や「国民の意識」はそう簡単に「デフレ時代のもの」から抜け出しきれていません。
そこで「様々な社会の軋み」が生じてきていると思われますね。
上記で書いた「賃上げシステムがないこと」や「長時間労働規制を巡るやり取り」などは、その「典型的な軋みの例」だと思いますね。
だから、これらの「社会の軋み」を改善するには、今までのやり方の延長線では出来ませんよ。
もっと断固とした「法律による縛り」を掛けることによって「無制限な資本主義を是正」するのが良いとコロちゃんは考えていますよ。

5.「コロちゃんと1970年代の年末年始」
さて今日は、「もう無制限な資本主義には厳しい制限が必要だよ」をテーマとして、「ジョセフ・スティグリッツ教授」との「インタビュー記事」を考察してみましたよ。
コロちゃんは、この記事を読んだ時に「激しく同意する思い」が湧いてきていましたので、今日のブログも思わず力が入ってしまいました。
最後の「コロちゃん話」ですが、上記で「長い間かかって築き上げられてきた国民の意識はそう簡単にデフレ時代から変わらない」と書きましたが、その「具体的エピソード」を書きたいと思いますね。
コロちゃんは、1970年代に20代の青年時代を生きて、その後現在までの「50年間」に渡って「日本の社会の変遷」をリアルタイムに見てきました。
その上で感じたことは、「無制限な資本主義の精神」が日本社会に浸透してきたのは「2000年代初頭」からだったように思っていますね。
この「無制限な資本義の精神」とは、一言で言えば「お金が儲かるのが正しいと言う価値観」です。
その具体的エピソードとして、コロちゃんが「20代」だった頃の「1970年代初頭の年末年始」の「日本の風景」を書いてみますね。
コロちゃんが東京に上京した「1970年代初頭」の「年末年始にあたる12月29日ごろ~1月7日」までは、「官庁・銀行」などはおろか、ほぼすべての「商店・小売店など」も全て休業となっていました。
今と違って「コンビニの業態」はまだありません。年中無休の「牛丼屋」などもありません。
この「年末年始」は、都市部へ上京して働いていた「地方出身者」は、ほとんどが帰省していましたし、それ以外の「独身者」は、毎日の食事する場所にも困るような「社会の風景」があったのです。
その頃の青年コロちゃんは、事前の年末に「上野のアメ横」に買い出しに行って「マグロの刺身や新巻きザケ1匹やハムなど」をまとめ買いしていましたね。
更に「ビール」や「なべ物の具材」を大量に買い込んで、友人たちを誘って「年末年始の徹夜麻雀大会」を自宅のアパートで開催していました。
この頃のコロちゃんのアパートでは、大晦日の12月31日の夕方になると、ポツリポツリと友人たちが集まり始めて、4人そろえばすぐに「麻雀大会」が始まりましたよ。
その後、入れ替わり立ち代わりと何人も集まると、「半荘で2抜け」で交代しながら遊び始めて、夜も更けると「刺身や鮭焼き、鍋物」が、手の空いた仲間たちによって調理されてきましたね。
後ろのテレビでは「紅白歌合戦」が放映されている中を、「ポン、チー、ロン!」とやかましい事この上ない様子でしたね。
しかし、アパートの周囲の部屋の住民はみな「帰省」していましたから、何も問題はありませんでしたよ。
この時代に友人たちが、コロちゃんの誘いで「年末年始の麻雀大会」に集合したのは、当時の「日本社会」では「年末年始の10日間ほど」はどの店も開いていないという事情がありました。
だから「独身者」は、事前の準備をしていないとそれこそ「餓死の危険」があるような社会状況だったのですよ。
「1970年代初頭の東京」では、今では考えられないほど「年末年始はみな休んでいた」のです。
そして、地方出身者はみな「帰省」していましたし、「東京出身者」は「年始のあいさつ回り」を歩いていました。
もちろん、みんなが休みなのですから、その機会に「商売で稼ぐこと」は出来たのでしょうけれど、そのような「例外」は当時の青年コロちゃんはほとんど見ませんでしたね。
これって「年末年始は休むものだ」と言う「日本の社会文化」があったからですよね。
この「社会文化」は、その後1990年代頃から変わり始めて、やがては「元旦でも開店するスーパー」が登場しています。
これは「日本の旧来の社会文化」が「無制限な資本主義の精神」に侵食されていったとも見ることもできますよね。
コロちゃんは、かつての「1970年代」には「いくらお金を貰っても年末年始は休みたい」とほとんどの人が思っていたことを見てきましたよ。
それが徐々に「無制限な資本主義の精神」が社会に広がり始めて、それが誰の目にも見えるようになったのが「2005年のホリエモンのフジテレビ騒動」の頃でしょう。
その「無制限な資本主義の精神」も「行き過ぎちゃった」のでしょうね。今その反動が「社会を揺るがしている」とコロちゃんは考えていますよ。
ですから、コロちゃんは「1970年代から現在までの日本社会の変貌」を見てきて、「無制限な資本主義の精神を制限すること」になったことは「歴史的な必然」だと思っていますよ。
今日の「コロちゃん話」は、「1970年代初頭の年末年始の麻雀大会の経験」から得た知恵をちょっと書いてみましたよ。
当時の若き青年コロちゃんの「年末年始の雰囲気」と「歴史の見方」を、知っていただければ嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。








コメント