おはようございます。昨日にコロちゃんは、「長男一家宅」の子どもたちが「夏休み」で自宅で留守番をしていますので「留守番支援」に行ってきました。
コロちゃんは、子どもたち2人(なーちゃん〈小5)+たーくん〈小1〉)と一緒に夕方まで「留守番」をしていたのですが・・・ちっとも言うことを聞いてくれないのですよ。
「なーちゃん(小5)」は、年長ですからちゃんと言えば分かってくれるのですが、年少の「たーくん(小1)」は、お昼の食事を目の前に並べても、まるで食べてくれません。
黙って「テレビのアニメ」を見るばかりなのですよ。
そこでコロちゃんが、「食事をしなさい」と何度言ってもわからないならと、テレビを消したところむくれて「奥の6畳間」にお籠りして出てこなくなってしまいました。
・・・・コロちゃんはどうしたらいいの?
(o_o ;)コマッタナー
子どもたちに「お昼」を食べさせないわけにはいかないし、だけど「たーくん(小1)」はコロちゃんの言うことをちっとも聞いてくれないんだぞー!
(´ヘ`;)ウーム…
結局「たーくん(小1)」は、ママさんが帰ってくる夕方まで「奥の6畳間でお籠り」を続けていましたよ。
これって「たーくん(小1)」の、「意志が強い」って見るべきか、それとも「我が強い」って見るべきか?
ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?
コロちゃんの40年近く前の「子育ての記憶」だと、みんな「妻に丸投げ」していましたからね。
なにしろ「会社員と専業主婦」の「昭和の時代」でしたから、コロちゃんには「小さい子ども相手のスキル」ってほとんどないんですよ。
ただ帰り際に「ママさん」と話したところでは、「絵本を読むこと」は「たーくん(小1)」は好きなようですから、次は「絵本を読んでみよう」と思ったコロちゃんでしたよ。
そんな「小1の子どもに振り回されるコロちゃん」が、今日は「デフレはとっくに脱却しているって?」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「デフレ脱却はホントはもう3年目だって?と、日本はデフレなのか、それともインフレなのか?」
☆「日銀の物価予測って当たっているの?と、誰が間違っているのかな?」
☆「コロちゃんとデフレ経済」

1.「デフレ脱却はホントはもう3年目だって?」
コロちゃんが、朝コーヒーを飲みながら新聞をバサバサ読んでいると「デフレ脱却、既に3年目?」といういう見出しが目に入りました。
コロちゃんは、この間ずっと「物価高」に悩まされていますので、「現状がデフレだ」とはとても思えないものですから、この記事をジックリと読んでみましたよ。
そもそも「デフレ」って「物価が下落する経済現象」を言いますよね。とても「今の現状」とはかけ離れていると思いますよ。
この「記事」では、民間エコノミストの判断を「1面トップ」で報じていましたよ。
その内容は、「経済」がインフレかデフレかを判断する「受給ギャップ」についての見解でしたよ。下記でしたよ。
◎「需給ギャップのプラス転換時期」
➀「BNPパリバ証券の河野龍太郎氏」
・「2021年:10月~12月期からプラス」
②「みずほリサーチ&テクノロジーの河田皓史氏」
・「2022年7~9月期からプラス」
この「需給ギャップ」がプラスとなると、経済学では「デフレ」ではなく「インフレ」と判断するそうなのですよ。
ちょっとここで、過去の「物価上昇率」を見ておきましょう。下記でしたよ。
◎「物価上昇率」(生鮮食品を除く総合)
①「2021年:-0.2%」
②「2022年: 2.3%」
③「2023年: 3.1%」
④「2024年: 2.5%」
https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
(出典:総務省 消費者物価指数 全国2025年6月分より:8月5日利用)
現在の物価上昇が始まったのは、「月別」では「2021年の9月」からですし、上記の「年別」では「②2022年:2.3%」からになっています。
だからもう「丸3年以上物価上昇(インフレ)」が続いていることになります。
この記事の民間エコノミストの「河野龍太郎氏」は、上記の「2021年10~12月期」から「需給ギャップ」はプラスに転換したと言っているのです。
そして「河田皓史氏」は、「2022年7~9月期」からプラスに転換したと言っています。
この「需給ギャップがプラス転換」したとなると、普通に考えれば「デフレ脱却」となりますよね。
しかし、現在の「政府と日本銀行」は、まだ「デフレ脱却宣言」を出していません。
記事では、この「政府・日銀」と上記の「民間エコノミスト」の推計の違いを、「労働時間の解釈の違い」と指摘しています。
その違いを以下のように記載していますね。
「日本の労働時間は24年も19年を下回り、コロナ禍の落ち込みから戻り切っていない。民間エコノミストは19年開始の残業規制や有給休暇の取得拡大が影響していると見ている」
「労働時間の伸びしろが少ないことが供給力を制約している」
上記のように、記事では現在の日本では「デフレ下」の「需要不足」ではなく、「労働力不足」の「供給制約」が起きていると言っているのです。
この「供給制約」が起きると、何が起こるかと言うと以下の指摘を記載していますよ。
「需給ギャップがプラス圏にあるなら、減税や給付金は物価高を助長する」
「需要に供給が追い付かないのに、需要ばかり刺激する財政出動や緩和的な金融環境を続けてきたことになる」
そうなんですよね。コロちゃんの拙い「経済知識」でも、「デフレ」でなく「インフレ下」では、「財政政策(減税や給付金など)」や「金融緩和政策(低い金利)」は物価高を招くとありましたよ。
コロちゃんは、上記のような「政府・日銀」にケンカを売るような「記事」が、「日経新聞の1面トップ」に掲載された意味を、ちょっと考えちゃいましたね。
これって現在の「物価高」は、現在の「財政・金融政策の誤り」が原因だって見方が、「経済界」で拡がってきているってことじゃないかとコロちゃんは受け止めましたよ。
なお、この「日経新聞」の「デフレ脱却、既に3年目?」の記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。


2.「日本はデフレなのか、それともインフレなのか?」
この現在の日本が「デフレ」なのか、それとも「インフレなのか」の「政府と日本銀行」の公式見解をちょっと見ておきましょう。以下でしたよ。
最初は「政府」を見てみましょう。「政府」は先月の7月29日に「令和7年度経財白書」を発表しています。その中で以下の記載がありました。
「我が国経済は、現在、消費者物価が上昇しているという点で、明らかにデフレの状況にはなく、経済学的に言えばインフレの状態にあるが、再びデフレに後戻りする見込みがないとまでは言えず、これについては総合的かつ慎重な判断が必要である」
うーん、なんかどっちつかずの書き方ですよね。
(´ヘ`;)ウーン
もう「デフレではなくインフレ」なんだけど、また「デフレに戻る」とイヤだから、ちょっと様子を見ておきましょうって感じでしょうか。
次は「日銀」を見てみますね。「植田日銀総裁」は、2月4日の「衆院予算委員会」で、「現在はデフレではなくインフレの状態にある」と述べられています。
そして、報道では先月の7月31日の「金融政策決定会合」の後の「記者会見」で、以下の様の述べたと報じられていますね。
「(今年度の物価上昇率の見通しを前回の見通しよりも引き上げたことについて)今年度(2025年度)分はかなり大きく上方修正したが、これはほとんどコメを含む食料品価格の上昇を反映したものだ」
「時間がかかるかもしれないが、今後インフレ率は低下に向かうと予想しているので、今回の上方修正だけをもって金融政策が左右されるというようなものではない」
上記を見ると「日銀」も、今後は「物価上昇率(インフレ率)が下がる」と予測しているようですね。ホントに下がるのかなー?
この「日本銀行」の「金融政策決定会合」の、現在時点の「今後の物価予想」は以下でしたよ。
◎「2025~2027 年度の政策委員の大勢見通し」
(政策委員9人の見通しの中央値)
➀「2025年度:+2.7%」
②「2026年度:+1.8%」
③「2027年度:+2.0%」
https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor2507a.pdf
(出典:日本銀行 経済・物価情勢の展望 2025年7月より:8月5日利用)
ふーむ、「日銀の政策委員」って、先行きの「②2026年には+1.8%」になるから「安定的な2%」ではないって考えている様ですよね。
( ̄へ ̄|||) フーム
「日銀」の「物価目標」って、「2%を持続的・安定的に実現」って言っているのですよね。
だから「②2026年:+1.8%」の予測だから、まだまだ「利上げの時期」じゃないってことでしょうか?
だけどコロちゃんは、「素人のおじいちゃん」だから言いますよ。
この「日銀の2%を持続的・安定的に実現」するって、いつまでたっても達成できない「見果てぬ夢」なんじゃないでしょうか。
冒頭の「日経新聞」の「デフレ脱却、既に3年目?」と言う記事も、現在の「日銀の判断への不信」が底流にあるようにコロちゃんは感じましたよ。

3.「日銀の物価予測って当たっているの?」
さて、上記で「日銀の物価の見通し」を引用したコロちゃんでしたが、何となく「これって当たるのかな?」と不信を感じましたよ。
だって、来年の2026年度は「②2026年:+1.8%」の「2%以下」に下がるって言うのですよ。思わず「ホントかなー?」って呟いちゃいましたよ。
そこで、3年前の2022年4月に発表された「2021~2024年度の政策委員の大勢見通し(予測)」を読んでみましたよ。
この「日銀の物価予測は年度単位」なんですよね。コロちゃんが比較する数字は「総務省 消費者物価指数 」なんですが、こちらは「年単位」となっています。
その点は頭に置いて比較してみましょうね。下記でしたよ。
◎「日銀予測と総務省の消費者物価指数との比較」
(日銀は年度単位、総務省は年単位)
(日銀予測の発表日は2022年4月)
➀「2022年」
・「日銀予測 :+1.9%」
・「消費者物価指数:+2.3%」
②「2023年」
・「日銀予測 :+1.1%」
・「消費者物価指数:+3.1%」
③「2024年」
・「日銀予測 :+1.1%」
・「消費者物価指数:+2.5%」
https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor2204b.pdf
(出典:日本銀行 経済・物価情勢の展望 2022年4月より:8月5日利用)
https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
(出典:総務省 消費者物価指数 全国2025年6月分より:8月5日利用)
なんだなんだ、外れっぱなしじゃないの?
(゚Д゚)ナンダナンダ
繰り返しますが、上記の「日銀のデータ」は「年度単位」で、「総務省の物価上昇率」は「年単位」ですから単純な比較はできません。
それでも「日銀の物価の見通し」って、甘々ですよね。「①2022年~③2024年の見通し」は、全部「1%台」ですよ。
それが実際に後から振り返って「消費者物価指数」を見てみると、「2~3%台」になっていましたよ。
ちっとも「日銀の予測」が当たってないじゃないですか。
こんな「物価の見通し」を繰り返していたら、例え「3%・4%の現実」があっても、後から予測をみてみたら「2%以下だった」があり得ちゃいますよ。
あとから、「あらら、思ったよりも物価は上がっていたね」では、コロちゃんたち「物価上昇で苦しむ庶民」は立つ瀬がないですよ。
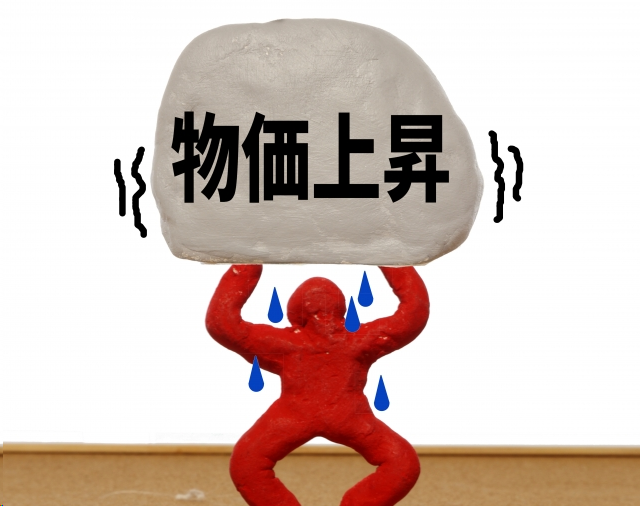
4.「誰が間違っているのかな?」
上記の「日銀の物価の見通しの誤り」は、誰が間違っているのでしょうね。コロちゃんが考えるところでは、以下の3つのどれかです。
◎「日銀の物価の見通しの誤りの原因」
➀「データの誤り」
②「データの活用法の誤り」
③「政策委員の判断の誤り」
これはコロちゃんの勝手な考えですが、上記の「①データ」は誤りはないと思うのですよね。この「データ」を収集するために「日銀」は全国に「支店網」を張り巡らせています。
そして「優秀な日銀マン」が一生懸命データを収集しているのだろうと考えますから、まずありえないと思うのですよ。
そして「③の政策委員」は、現在の日本で一番優秀な「経済専門家」たちですから、そうそうは間違いはないと信じたいですよね。
そうなると、最後に残った「②データの活用法の誤り」が臭いですよね。
ここで冒頭の「デフレ脱却、既に3年目?」の「新聞記事」が頭をよぎりますよね。この記事では「需給ギャップ」はとっくに「プラス転換」していたのではないかと記載しています。
つまり「3年前からデフレ脱却はしていた」としているのです。
これは「民間エコノミスト」の推計によるものですが、「労働時間の解釈の違い」と指摘しています。このような「解釈の誤り」はたとえ専門家でもあり得るのでしょう。
コロちゃんは、もう「物価上昇」に飽き飽きしていますよ。一刻も早く「日銀発のインフレ社会」を利上げで転換していただきたいと考えていますよ。

5.「コロちゃんとデフレ経済」
今日は「デフレはとっくに脱却しているって?」をテーマに、1面トップの「新聞記事」から「日本銀行」の経済予測などを考察してみました。
最後の「コロちゃん話」では、「デフレ下のコロちゃんの生活」を書いてみますね。
皆さん「デフレ」って一口に言いますけど、「日本のデフレ」が始まったのは「1990年代の半ば」からです。その後、2021年まではほとんど「物価が上昇しない社会」が続いていましたね。
コロちゃんは、この全期間を「40代~60代」で生きていましたから、この30年を間近に見てきましたよ。
その記憶ではこの「デフレの30年」とは、「物価も上がらなかった」けれど「賃金も上がらなかった」のですよ。
コロちゃんの「給料」も、40代の時と50代の時と比べてもほとんど上がっていませんでした。
ただこの間の「物価」は、むしろわずかでしたが「下落」していましたから、「生活は苦しく」はなりませんでしたよ。
このようになると「社会が保守的になる」のですよ。だって「無理して成長する理由」が無くなるのです。
これが「物価が上がる社会」だったら、「安い給料の会社員」は「転職やスキルアップ」して「より高い給料」を目指さざるを得なくなるでしょう。
それが「物価が少しでも下がっている社会」でしたから、無理することはありませんでした。
これは「経営者」でも同じ事が言えます。「物価が上がる社会」だったら、会社の価値は何もしなければ、ドンドン落ちてしまいます。
「会社の資産」は現物ですから、「物価が上がる」とその逆に「価値は下落する」のですよ。
それが「物価が下がる社会」でしたし、「賃金も上げなくて良い社会」でしたから、経営者はみな「保守的」になっていました。
だって、「このままでも儲かっているんだから無理することはないよね」となりますよ。
「日本の経営者たち」は、すっかり「資本主義経済」の「アニマルスピリッツ」を失ってしまっていたのですよ。
ああ「日本の労働組合」も同じですね。
「物価が上がらないなら賃上げもゼロでいいや」って、こちらも「アニマルスピリッツ」をなくしていましたからね。
ただ「1個人のコロちゃん」としては、この「30年間」は「ほぼ変わらない給料」と「やや下落した物価」と言う「安定した生活」がありましたよ。
コロちゃんは、毎月10万円強の「住宅ローン」を抱えていましたからね。 「変わらない賃金」と「やや下落する物価」の「ほとんど変わらない30年間」は居心地が良いものでしたよ。
このように、リアルタイムの「デフレ経済」は、ほとんどの庶民には「居心地が良い」ものだったのです。
しかし、これが「資本主義経済」の根幹である「成長を追求する精神(アニマル・スピリッツ)」を殺していたとは、当時は誰も予想もしませんでしたよ。
現在の社会は、中長期的には「成長しないと成り立たない社会」になっているのですよね。
それが「デフレが30年間」続いたことにより、その悪影響がいろいろと顕在化してきました。
代表的な「悪影響」は、「安いニッポン」ですよね。
今の「日本」は、「モノの値段(賃金も)」が東南アジアの30年前の水準となっていますから、インバウンドが旺盛なわけですよ。
今後の「日本」は「何とかして経済成長する社会」に戻すか、それとも「小さな成長でも安定した社会」を目指すかの、どちらかになるかとコロちゃんは考えますよ。
しかし、前者の「何とかして経済成長する社会」へ進む道は、もう「30年間も試行錯誤」をしても今だに「その道」は見えてきていません。
後者の「小さい成長でも安定する社会」が、コロちゃんにはお勧めですが、道のりはまだまだ遠いとコロちゃんは思いましたよ。
なかなかみんな「成長する社会」をあきらめ切れないのですよ。
今日の「コロちゃん話」は、「デフレの30年間」の「コロちゃんの生活」と「今後の社会の行方」についてお伝えしましたよ。
ご年配の方は、ご自分の生活とどうぞお比べください。お若い方には、「こんな時代も日本にはあったんだ」と読み流してくださればコロちゃんは嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。








コメント