おはようございます。今日のコロちゃんは、ちょっと嬉しいことがあったんです。
現在のリアルタイムは午後3時なのですが、少し前に「インターホン」がピンポーンとなりました。コロちゃんは、「こんな時間にいったい誰だろう?」と出てみましたよ。
そうしましたら「電気設備の点検です」との呼びかけです。屋外の「電気メータ―」をチェックし、その後に「屋内の配電盤の点検」をするとのことでした。
コロちゃんは、「ハイどうぞ」と屋内に案内したところ、この50代ぐらいの「電気屋さん」は、小さな「3段の脚立」を持ちこんで「洗面所の配電盤」の点検をしていたのですよ。。
そこでコロちゃんは「ピン」とひらめきました。
コロちゃんちの居間の天井の「蛍光灯の豆球」が、先週にいきなり点灯しなくなっていたのですよ。ところがコロちゃんでは、椅子に乗っても手が届かないのです。
そこでコロちゃんは、「電気屋さん」に「すみませんが脚立をちょっと貸していただけませんか?」とお願いしたところ、「いいですよ」と嬉しい返事です。
そして「脚立」を借りたコロちゃんが、天井の豆球の交換に四苦八苦していると、なんとこの「電気屋さん」から、「私がやりましょうか」とうれしい言葉をいただいたのですよ。
いやいや、世の中はまだまだ捨てたものじゃないですよね。コロちゃんはすっかり嬉しくなっちゃいましたよ。
コロちゃんは、「天井の蛍光灯の豆球」を交換してくれた「電気屋さん」に、心からのお礼を申し上げましたよ。
そんな嬉しい気持ちでいっぱいのコロちゃんが今日は「住民税非課税世帯と豊かな高齢世帯」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「住民税非課税世帯へのバラマキは格差の拡大を招くの?と、住民税非課税世帯への給付金の実態を見る」
☆「住民税非課税世帯の年代を見るよと、所得がいくら以下なら住民税非課税世帯になるの?」
☆「高齢者世帯でほとんど貯蓄がないのは2割弱だよと、資産がある高齢者の住民税非課税世帯数は?」
☆「コロちゃんは金融資産把握をお勧めしますよと、コロちゃんと貯蓄の話」

1.「住民税非課税世帯へのバラマキは格差の拡大を招くの?」
コロちゃんは、最近の報道の中に「住民税非課税世帯」への給付金は、「豊かな高齢者へのバラマキとなっている」との論調を読み、その実態を詳しく見てみようと思い立ちました。
まず、コロちゃんが読んだ「論考」は、「日経新聞」の「経済教室」での「北尾早霧政策研究大学院大学教授」の「時代遅れの政策/転換が必要」との見出しの論考です。
この中で「北尾教授」は、以下のように記載しています。
「低所得層支援や老後の安心は重要だ。しかし日本で平均資産が最も多いのは高齢者、貧困が深刻なのは20~50代の若者だ。」
「低所得層支援を掲げて繰り返す住民税非課税世帯へのバラマキは大半が裕福な高齢者に届き、格差を拡大する」
上記のように「北尾教授」は、「貧困層の支援は生活保護のルートなどを通じて対象を絞るべきだ」と言っているのです。
コロちゃんは「住民税非課税世帯」に入っていませんから、上記の「バラマキがされる裕福な高齢者」のお仲間ではありません。
しかし、この「北尾教授」のおっしゃる「バラマキの大半が裕福な高齢者に届く」ことがホントかどうかを調べてみようと思いましたよ。
なお、この「北尾教授」の論考をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。

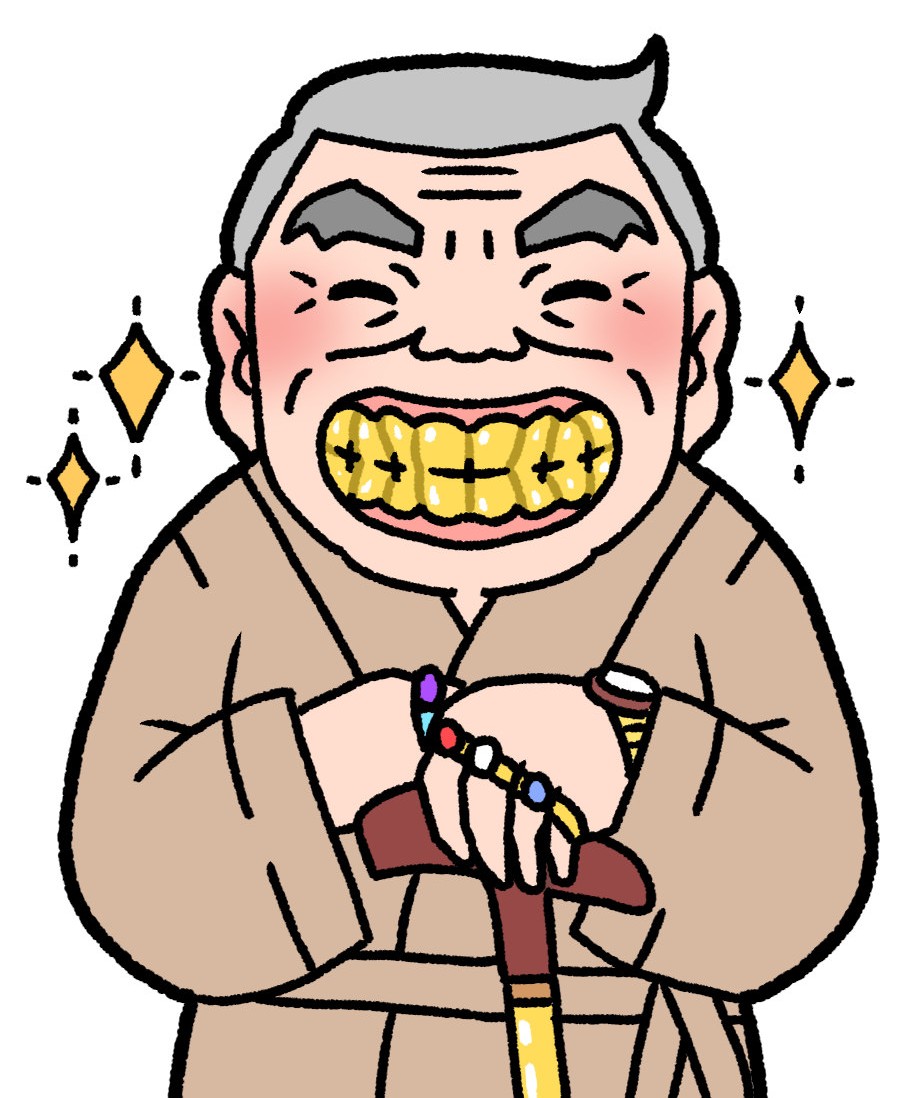
2.「住民税非課税世帯への給付金の実態を見る」
コロちゃんは、上記したように「清貧な年金生活」をおくっていますがこの「住民税非課税世帯」には入っていません。
コロちゃんの「年金所得」はギリで「税金」を徴収されているのです。
だから「自治体からの給付金の連絡」はありませんから、「住民税非課税世帯への給付金」がいつあったのかを知りません。
普通そうですよね。自分に給付されない限り、「給付金や還付金」への関心はほとんどありませんよね。
たとえ新聞で報道があっても、関係ない記事はスルーして記憶に残りません。
そこでコロちゃんは、ここ数年間の「住民税非課税世帯」への「給付金」を調べてみましたよ。以下ですよ。
◎「住民税非課税世帯への政府の対策」
➀「2021年 :1人10万円給付」
➁「2022年 :1人10万円給付」
③「2023年夏 :1人3万円給付」
④「23年末~24年初:1人7万円」
⑤「2024年:1人3万円+子ども1人2万円」
上記のように「住民税非課税世帯」への「政府の給付金」は、「➀2021年」以降の毎年行なわれています。
コロちゃんは、総額でどのくらいの金額の「国費」が投入されているのかを調べてみましたが、どうやら毎年「1~1.4兆円規模」の様でしたよ。
はてさて、これだけの規模の「給付金」が、上記で「北尾教授」がおっしゃるように「住民税非課税」の「豊かな高齢者のふところ」に入っているのでしょうか。
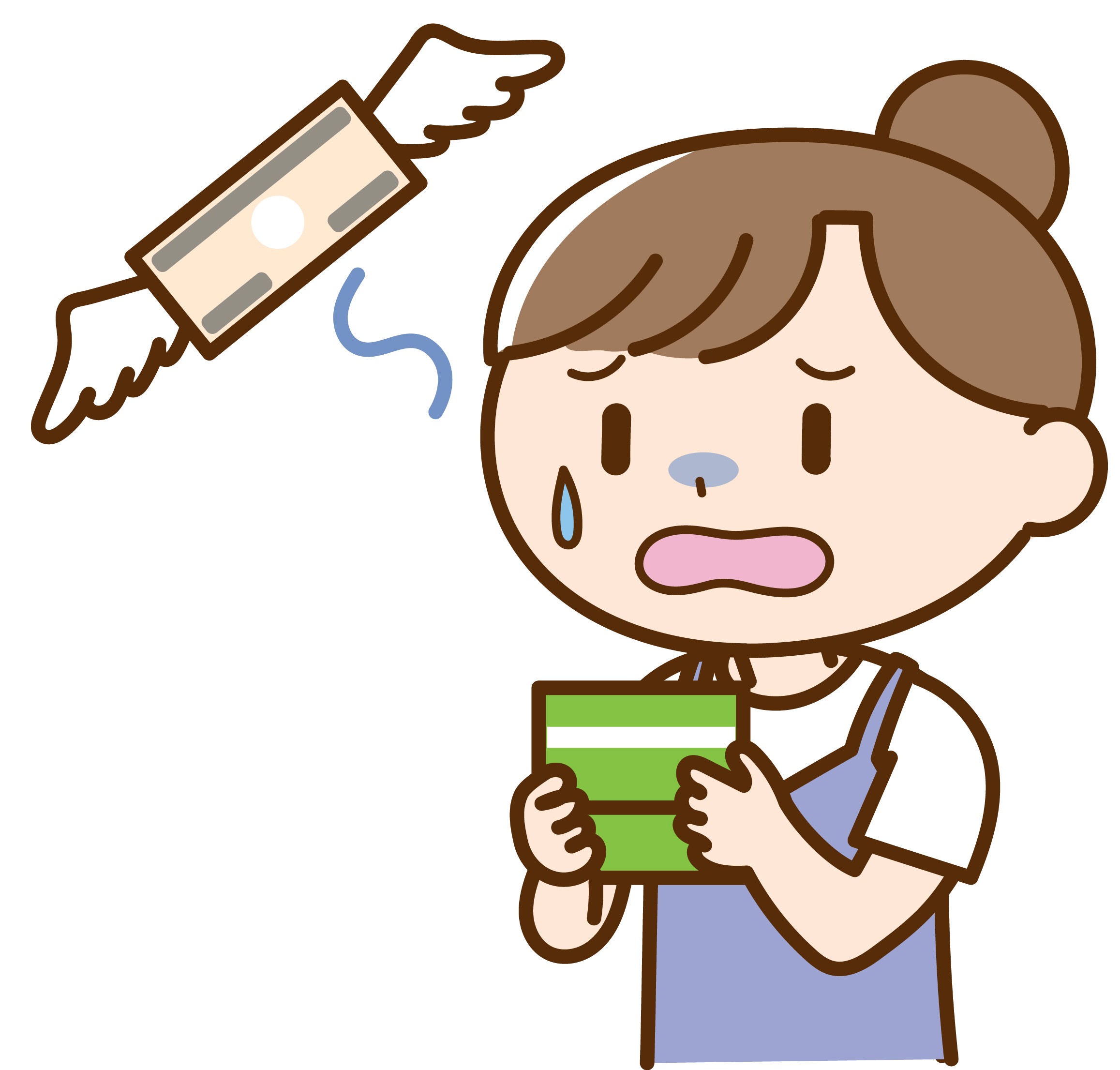
3.「住民税非課税世帯の年代を見るよ」
まずは「非課税世帯の数」ですが、以下のようになっているようです。
◎「総世帯数と住民税非課税世帯数」
➀「総世帯数 :5696万世帯」
➁「住民税非課税世帯:1320万世帯」(23%)
ざっと、上記のように現在の「日本」の総世帯の1/4が「住民税非課税世帯」となっているようです。4世帯に1軒とは多いですよね
その「年齢別の内訳」は、どうやら「厚生労働省:国民生活基礎調査」の「住民税」の項目から計算しなければわからないようですよ。
コロちゃんは、ポチポチと探し出して下記に計算してみましたよ。
◎「住民税額:非課税世帯:➀~⑧」(小数点以下切り捨て)
➀「非課税世帯数:1320万世帯」(100%)
➁「29歳以下 :52万世帯」(3%)
③「30~39歳 :35万世帯」(2%)
④「40~49歳 :52万世帯」(3%)
⑤「50~59歳:106万世帯」(8%)
⑥「60~69歳:212万世帯」(16%)
⑦「70~79歳:432万世帯」(32%)(最多)
⑧「80歳以上 :389万世帯」(29%)
⑨「65歳以上:955万世帯」(72%)
⑩「75歳以上:611万世帯」(46%)
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450061&tstat=000001219189&cycle=7&tclass1=000001219191&cycle_facet=tclass1&tclass2val=0
(出典:e-Stat:データセット情報:国民生活基礎調査 / 令和5年国民生活基礎調査 / 所得より:3月12日利用)
上記はコロちゃんが「国民生活基礎調査のデータセット」から、「住民税の課税世帯数」を見て、「全世帯数」から引き算して「非課税世帯数と割合」を計算したものです。
この計算でたぶんいいと思いますが、「⑦70~79歳:432万世帯:32%」がボリュームゾーンですね。
さらに「年金世代」もまとめてありました。「年金受給」が始まる「⑨65歳以上:955万世帯:72%」と7割以上を占めています。
これを見ると、確かに「住民税非課税世帯」向けの毎年1兆円を超える「給付金」の7割は、「65歳以上の年金世代」に渡されていますね。
コロちゃんとこには来ませんけど。
(´^`)チェ
この後でこの「⑨65歳以上:955万世帯:72%」中にどのくらいの「豊かな高齢世帯」があるのかを調べてみますね。
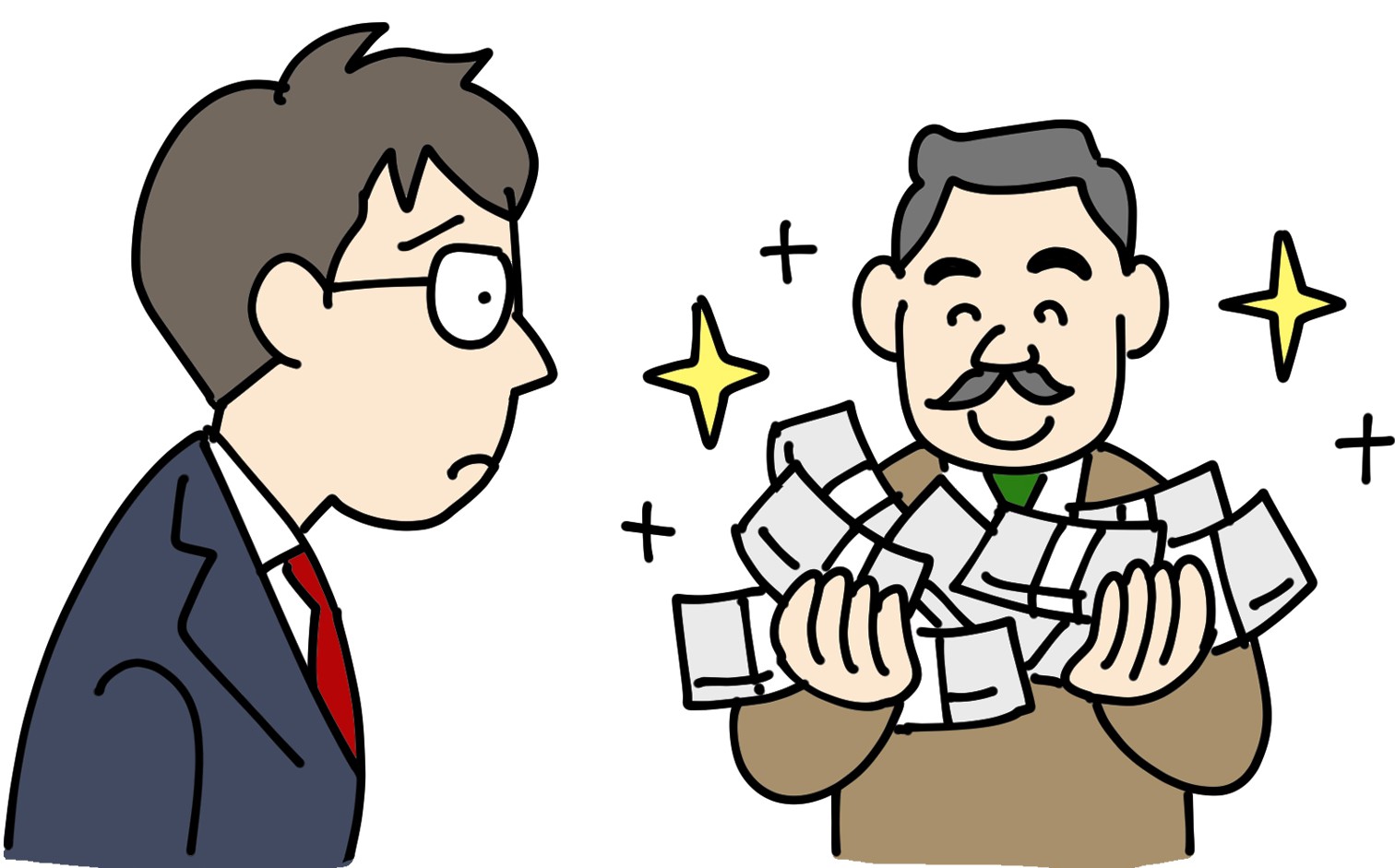
4.「所得がいくら以下なら住民税非課税世帯になるの?」
次にちょっと「住民税非課税世帯」と認定される所得の条件を確認しておきましょう。
多くの若い方々には、「住民税非課税世帯」の方は少ないですから、お給料がどのくらいならば「住民税非課税世帯」に該当するのかを知る方は少ないでしょうね。
コロちゃんも、自分が「住民税非課税世帯」にギリで該当しないことは知っていますけれど、正確な所得金額のラインは知りません。
そこでポチポチ調べてみましたが、「住民税は地方自治体」によって変わりますので、以下は「東京都」の例を書きますね。
◎「住民税非課税世帯規準」(1000円以下切り捨て)
➀「単身者の場合」
・「給与所得が100万円以下(月8万円以下)」
・「年金所得が155万円以下(月12万円以下)」
➁「夫婦と子1人」
・「世帯所得が205万円以下(月17万円以下)」
③「夫婦と子2人」
‣「世帯所得が255万円以下(月21万円以下)」
上記でも書きましたが、「住民税非課税世帯の基準」は「地方自治体」によって違います。それに「1000円以下切り捨て」で丸めましたから、参考値としてください。
コロちゃんの場合は、上記では「①高齢単身者:年金所得155万円以下(月12万円以下)」ですから、該当しませんでした。
これは・・・「残念」というのは違うよね?
ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?
だけど、「➀単身者:給与所得が100万円以下(月8万円以下)」って「生活保護基準」より低いんじゃないの?
(o゚Д゚)エエッ!!
確か「生活保護基準」も地域で違っていて「単身者」の場合の「最低生活費」は、「1級地-1では13万円」「2級地-1」では「11万円」ですよ。
あらら、コロちゃんは知りませんでしたね。「最低生活費」の基準が、「住民税非課税」と「生活保護」とでは違っているんですね。
(゚Д゚)アララ!
だけど「生活保護者は住民税免除」と決まっているようですから、それは問題にはならないみたいですね。

5.「高齢者世帯でほとんど貯蓄がないのは2割弱だよ」
上記の「住民税非課税世帯」の基準は、あくまでも「所得」であり「資産」は調査しません。
その結果「年金所得は年155万円(月12万円)以下でも資産は沢山保有する高齢者」が、「住民税非課税世帯」となり「政府の給付金」を受け取っているというのが、冒頭の論旨でした。
そこで、次に「高齢者の資産分布」を見てみましょう。下に書き出しますね。
◎「高齢者世帯の金融資産分布」(小数点以下切り捨て)
➀「貯蓄がない:11%」
➁「貯蓄がある:80%」
・「100万円未満 :6%」
・「100~400万円未満 :15%」
・「400~700万円未満 :10%」
・「700~1000万円未満 :6%」
・「1000~2000万円未満:14%」
・「2000万円以上 :22%」(ボリュームゾーン)
③「高齢者世帯平均:1600万円」(100万円未満切り捨て)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/14.pdf
(出典:厚生労働省:2022年 国民生活基礎調査の概況より:3月12日利用)
上記は、「厚生労働省」の発表した「各種世帯の貯蓄額階級別・借入金額階級別世帯数の構成割合」のデータです。
上記では「➀貯蓄がない11%」+「➁100万円未満6%」=17%ですね。
現在「高齢者世帯(65歳以上世帯)」は2747万世帯(※)ですから、その17%というと466万世帯の「ほとんど貯蓄のない高齢者世帯」がいることになりますね。
(※内閣府:令和6年版高齢者会白書より)
だけど、確かに「2割の貧しい高齢者」がいますが、「2000万円以上が22%でボリュームゾーン」ですよ。金あるなー。
(o゚Д゚)オオォォォ
それに「平均でも1600万円」ですし、これで「住民税非課税世帯」となって「給付金」を受け取っているヤツがいたら「国賊※」ですよ。
(※コロちゃんのやっかみ※です)
(※やっかみ:相手をうらやましく思う気持ちからその人を憎んだり嫌ったりする行為)

6.「資産がある高齢者の住民税非課税世帯数は?」
ざっと、上記のように「住民税非課税世帯への給付金」の周辺事情を見てきました。それをまとめると以下のように言えるかと思われます。
➀「住民税非課税世帯数は1320万世帯」
➁「そのうちの65歳以上の年金世帯は955万世帯(72%)」
ここまでは、わかりやすいと思うのですよね。
この「②65歳以上の年金世帯955万世帯」の中に、「所得はないが資産はある高齢者」がどれだけ含まれているのかを考えてみましょう。
一つ上の項では「貯蓄がない+100万円以下の高齢世帯数」を書いています。下記ですね。
❶「貯蓄がない+100万円以下の高齢者世帯数は17%」
❷「高齢者世帯数は2747万世帯(※)でその17%は466万世帯」
(※内閣府:令和6年版高齢者会白書より)
ここからはコロちゃんの想像なのですが、上記の「❶貯蓄がない+100万円以下の高齢者世帯」はほとんどが「住民税非課税」なのではないでしょうか。
もちろん中には「所得は高いが貯蓄はない」「宵越しの銭は持たない」という高齢世帯もいらっしゃるかと思われますが、コロちゃんはそのような世帯はごく少数ではないかと思ったのです。
もし、このコロちゃんの見方が正しければ、以下の計算式が成り立ちますね。
◎「資産がありながら住民税非課税世帯の高齢者世帯数」
➀「65歳以上の住民税非課税世帯数は955万世帯」
➁「貯蓄がない+100万円以下の高齢者世帯数は466万世帯」(仮に所得も低いとする)
③「貯蓄(資産)がある65歳以上の住民税非課税世帯は489万世帯」
はて、ホントにこんな雑な三段論法の計算が成り立つのかな?
(。・_・?)ハテ?
これだと「65歳以上の住民税非課税世帯」のだいたい51%が「資産がある」となりますね。
冒頭の「北尾教授」の「新聞の論考」では、「住民税非課税世帯へのバラマキは大半が裕福な高齢者に届き格差を拡大する」とありましが、「大半が」ではなく「半分が」でしたね。
しかし、これは「貴重な国税」が「半分も裕福な高齢者の元にプレゼントされている」と見るべきでしょうね。

7.「コロちゃんは金融資産把握をお勧めしますよ」
このような問題に対しては「日本維新の会」が良い政策を提案しています。
それは「マイナンバーカードを使った金融資産の把握」です。以下ですね。
「マイナンバー制度の活用や銀行口座との紐付けにより、個人・法人の資産と収入を正確に把握し、効率的かつ公平で抜け漏れのない徴税を行います。」
(日本維新の会:維新八策2024:税制改革より)
コロちゃんは、この「マイナンバーカードと銀行口座」を紐付けして、「住民税非課税の対象世帯」を「一定の資産額以下」に資格条件を絞るべきだと考えますよ。
そのくらいなことをしない限り、数億円の資産を持つ高齢世帯が「住民税非課税世帯」の指定を受ける不条理さは変えられないと考えますよ。
ちょうど現在は「立憲民主党+日本維新の会+国民民主党+その他」で、衆議院は多数派なのですから、やる気さえあれば明日にでも出来るとコロちゃんは思っていますよ。
コロちゃんは、今日にでも「自分の資産」をお国に公開出来ますよ。だって、そんなにないもーん。
( ¯ ^¯)へへーンダ!!!

8.「コロちゃんと貯蓄の話」
コロちゃんは、今の若い方のように「計画的に貯蓄をする」ことはあまりしていませんでしたね。そもそも、コロちゃんが青年だった1970年代は毎年給料は上がるものだと思っていました。
若い年代では、まだ給料は少なくとも職場の先輩たちを見ると、高齢になるほど高くなっていましたから、コロちゃんもいずれその高い給料になるから将来の心配はないと思っていましたよ。
だから「貯蓄」をするのは、給料が高くなるもっと年配になってからと、周りのみんなも考えていましたよ。
その中でコロちゃんが唯一行なっていたのは「労働金庫」の「財形貯蓄」でした。
これは毎月定額を積み立てるもので、コロちゃんが60歳を過ぎて「大腸がん」で退職するまで積み立て続けていましたよ。
今の時代のような「ファイナンシャルプランナー」などは、誰もいない時代の話でしたよ。
1970年代のコロちゃんの同僚の話ですが、毎月必ず給料日まで手持ちの生活費が足りなくなってしまう友人がいました。
このような「同僚の話し」と言うと、みんなコロちゃんのことだと考えるのですよね。
どうしてかなー、なんか理不尽ですよね。
(˘^˘,,)フーンダ!!!
その当時はこのような「若者」が珍しくなかったのですよ。まだ「サラ金」が全国展開する前でしたね。
そんな時に頼るのは「周りの友人たち」でしたが、その「周りの友人たち」も似たり寄ったりなのはどこでも見られた風景でしたよ。
そこで、コロちゃんのその友人はよく「労働組合」からお金を借りていましたね。もちろん「正規のルート」ではありません。明らかに違法です。
当時の「労働組合」の支部の会計担当の「執行委員」を務めていたオヤジさんに、毎月どうしてもお金がなくなり、その日の夕飯も食えないと泣きつくと3000円とか5000円を貸してくれていたのですよ。
もちろん「返済」は給料日です。利子なんか取りませんよ。
この「組合の会計担当のオヤジさん」は、「みんなには言うなよ」と言いながら「お説教はしない」のがスタイルでしたね。
ただ、あの金はたぶん「組合の支部予算」を横流ししていたんだろうなー、とコロちゃんはその後に思いましたけれどね。
その時の「執行部の面々」は、その事を知っていたのでしょうけど、誰も「ヤメロ」とは言わなかったようですね。見てみぬふりをしていたのでしょうね。
今振り返っても、あったかい「昭和の時代の職場の人間関係」でしたよ。違法でしたけどね。
今日は、「住民税非課税」と「豊かな高齢世帯」をテーマに、その内実をちょっと探ってみました。
結論は「豊かな高齢者の中に、一定数の住民税非課税世帯」がおり、政府から「給付金を受けとっている」ことを確認することになりました。
コロちゃんは、人間は「お金のためにはどこまでも卑しくなる」と感じましたが、この感覚はもう「古い時代」のものかもしれないとも思いましたよ。
ただコロちゃんは、自分の感性に正直に生きたいと思いましたよ。
「今更お金持ちに何てなってやるかい!」との気持ちですよ。もちろんなりたくても出来ませんけどね。
( ◍´罒`◍)エヘヘ
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。








コメント