おはようございます。朝から暑いですね。( ˙o˙; )アー( ˙ε˙; )ツー( ˙罒˙; )イー
なんか昨日のブログ記事でも、冒頭で同じことを書いたような気がしますが、顔文字が違いますのでご容赦下さいね。
今日のコロちゃんは、今「長男一家宅」でなーちゃん(9歳)とたーくん(5歳)とお留守番をしているのです。
コロちゃんはついさっき「長男一家宅」へ着いたばかりなのです。
2人の子どもたちは、居間でテレビゲームをしています。その隣でコロちゃんは、このブログをカキコキしていますよ。
「長男一家パパさん」は、早朝に「お仕事」に出かけています。そして、「長男一家ママさん」は、ついさっき「お仕事」に出かけましたよ。
今家に残っているのは、ママさんが出かける少し前にここに到着したコロちゃんと、夏休み中の二人の子どもだけです。
今日のコロちゃんは、「留守番と子守」という重大な任務を遂行しているのです。
今日は「コロちゃんと子どもたちのお留守番の1日」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」

コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「お義父さんと呼ばれたらなんでもするよと、留守番してたらなーちゃんのお友達がピンポーン」
☆「たーくんは組み立ておもちゃで遊び始めると、お昼はカレーです」
☆「なーちゃんとたーくんはプールですと、ママさん&子どもたちが帰宅しました」
☆「5歳児と9歳児とコロちゃんと、孫のいる高齢者」
☆「コロちゃんと時代によって変わる価値観」

1.「お義父さんと呼ばれたら何でもするよ」
先週は、コロちゃんと「長男一家」+「次男一家」とは一緒に「浜名湖にょろにょろ日記」の日々をすごしましたが、その時にコロちゃんは「長男ヨメ様」から次のようにお願いされました。

長男一家ママさん
お義父さん。
来週にお留守番と子守をお願いできますか?
午後にはプール教室があるので、入り口まで見送りしていただくと助かります
「お義父さん※」って良い響きの言葉ですね。コロちゃんはこの言葉を聞くと嬉しくなっちゃうのですよ。
(※お義父さん:義理の父親、配偶者の父)
このコロちゃんの「嬉しくなっちゃう」という感覚は、若い方にはなかなか想像できないと思うのですが、コロちゃんと同じ年齢層の方には分かると思われます。
言葉には、必ず「その時代の価値観が宿る」のですよ。
昭和年代に生きた人々は、旧時代の「家族制度の価値観」が未だに身に沁みついています。古い「家族制度」では、「嫁の地位」は低く「義理の父親の権威」は高かったのです。
だからコロちゃんの年代が「お義父さん」という言葉を聞くと、その言葉に内在している「高い権威」のイメージが思い浮かばれて嬉しくなるという構造が成り立っているのですよ。
おかしいでしょう? 現在では「お義父さん」という言葉は、文字通り「配偶者の父親」という意味しかありません。
もちろんその「お義父さん」という言葉に「権威のにおい」等は、まったく含まれていません。
しかし、リベラルを自称するコロちゃんですら、古い時代の価値観からは完全に解放されてはいないのですよ。
時代の流れと共に「社会制度」は変わっても、人の意識はそう簡単には変わらないという実例ですね。
だからヨメ様が、コロちゃんに何かをお願いしたい時には、「お義父さん、お義父さん、お義父さん」と3回ほど呼びかければ、気分が良くなって何でもすると思いますよ。
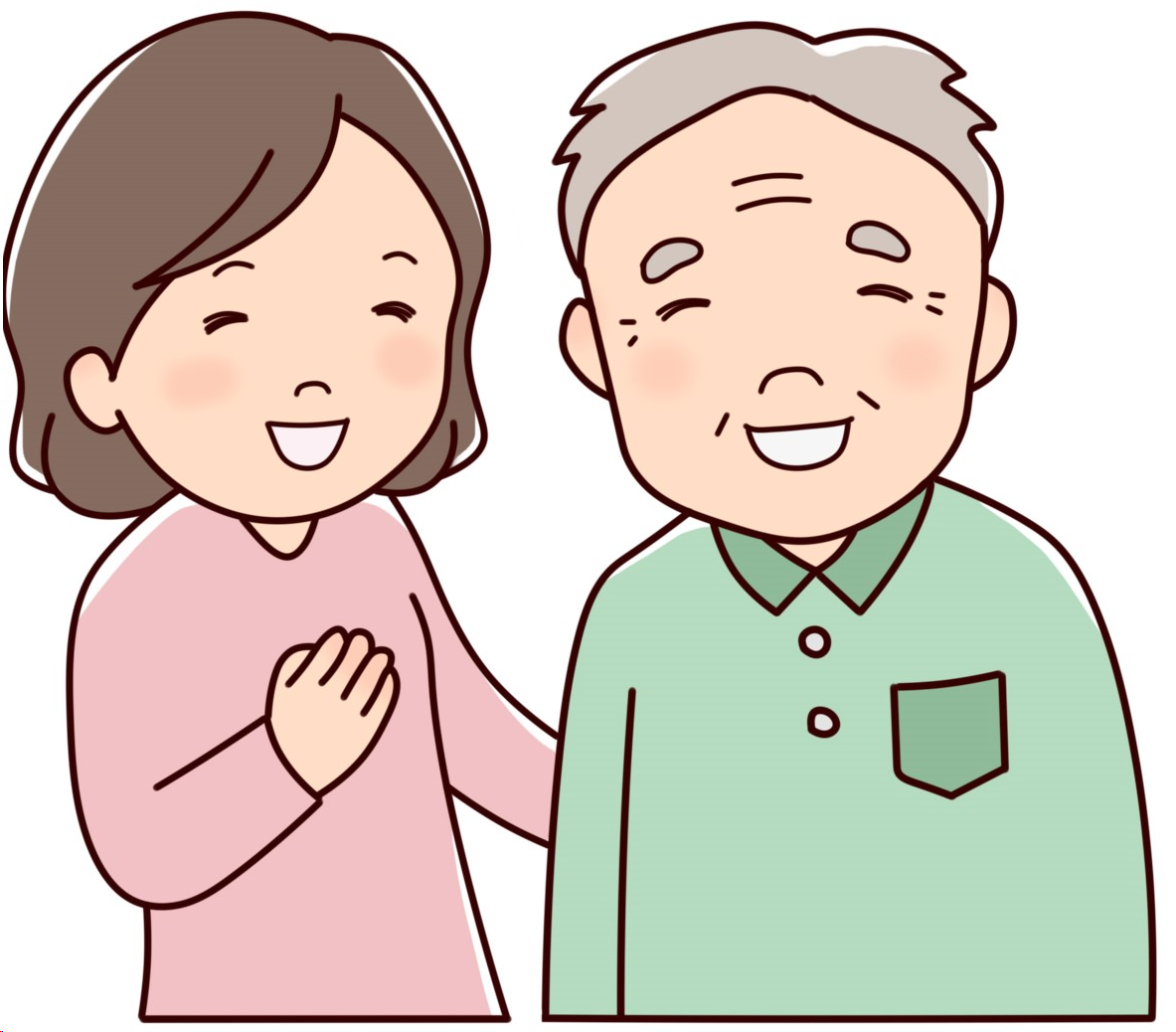
2.「留守番してたらなーちゃんのお友達がピンポーン」
さて、コロちゃんがお願いされた「子どもたちとの留守番」ですが、なーちゃん(9歳)のお友達が遊びに来ました。
「ピーンポーン」
それまでたーちゃん(5歳)と、時々ケンカしながらテレビゲームをしていたなーちゃん(9歳)が、トコトコと玄関に迎えに出ていましたよ。
なーちゃん(9歳)のお友達は、同い年らしい女の子でした。髪の毛をおさげにした可愛い子でしたよ。
コロちゃんは、ここの家では「子どもたちのテレビゲーム時間を制限」しているのを以前に聞いていましたので、朝ママさんに「今日はテレビゲームは良いの?」と聞いていました。
そうしましたら「いつもは平日はゲーム禁止なんですが、今日は解禁しました」ということでしたので、コロちゃんはホッとしましたね。
コロちゃんは、子どもたちと遊ぶのが苦手なのですよ。子どもたちが何をやりたいのか、いつもさっぱりわかりません。
コロちゃんは「昭和のオヤジ」でしたから、子育ては妻に丸投げでしたね。
そんなことを考えていたら、それまで3人で仲良くゲームをしていた子どもたちが騒ぎ始めましたよ。
どうやらたーくん(5歳)が、やりたいゲームを取り合って騒ぎ始めたようですね。しかし、これはどうしたらいいのか・・・。
(° д° ; )ォロォロ(; ° д°)

3.「たーくんは組み立ておもちゃで遊び始める」
いやいや、別にコロちゃんが心配することはなかったですよ。直ぐにたーくん(5歳)は気分を変えて、組み立てした車で遊び始めましたよ。
子どもって、直ぐ気が変わるから・・・分からんなぁ?
┓(゚~゚)┏さぁ分らん💧
コロちゃんも座り込んで、たーくん(5歳)と遊んでやりましたが、なんとも不器用なコロちゃんでしょう。ギクシャクしながらたーくん(5歳)と遊んでもらいましたよ。
そのうちになーちゃん(9歳)のお友達が帰ってしまうと、たーくん(5歳)は、またなーちゃん(9歳)とゲームで遊び始めましたよ。
まあ姉弟とは、このようにケンカしながら遊ぶのでしょうね。「仲良くケンカしな※」とはよく言ったものですね。
(※仲良くケンカしな:トムとジェリーの日本語版主題歌に出てくるフレーズ)

4.「お昼はカレーです」
お昼は、ママさんがカレーを準備してくれました。大きなジャガイモがゴロゴロ入っているカレーと,パパさんが作ってくれたらしいスープですね。
コロちゃんは一気に食べてしまいましたが、子どもたちはTVでユーチューブを見ていて、なかなか食べてくれませんね。
特にたーくん(5歳)は、TVばかりを見てなかなかカレーを食べてくれません。
そうしましたら、なーちゃん(9歳)がTVを見ながら食べられる場所に変えればいいよと教えてくれたのですが、いやいや相変わらずたーくん(5歳)は言うことを聞きませんね。
最後は業を煮やしたコロちゃんが、たーくん(5歳)の口に、ひとくちひとくちずつ小鳥のヒナの給餌をするようにカレーを食べさせて、やっと昼食が終わりましたよ。
なんと手間暇がかかる子どもだとか。ワンコの方がまだ言うことを聞きますね。良い子の時は「天使」なのですが、悪い子の時は「××」ですよ、子どもっていう存在は。
コロちゃんは、もう30年以上も幼い子どもと遊んでいませんでしたから、すっかりこのことを忘れていましたよ。
普段の生活の中でのパパさん、ママさんのご苦労が良くわかりましたね。
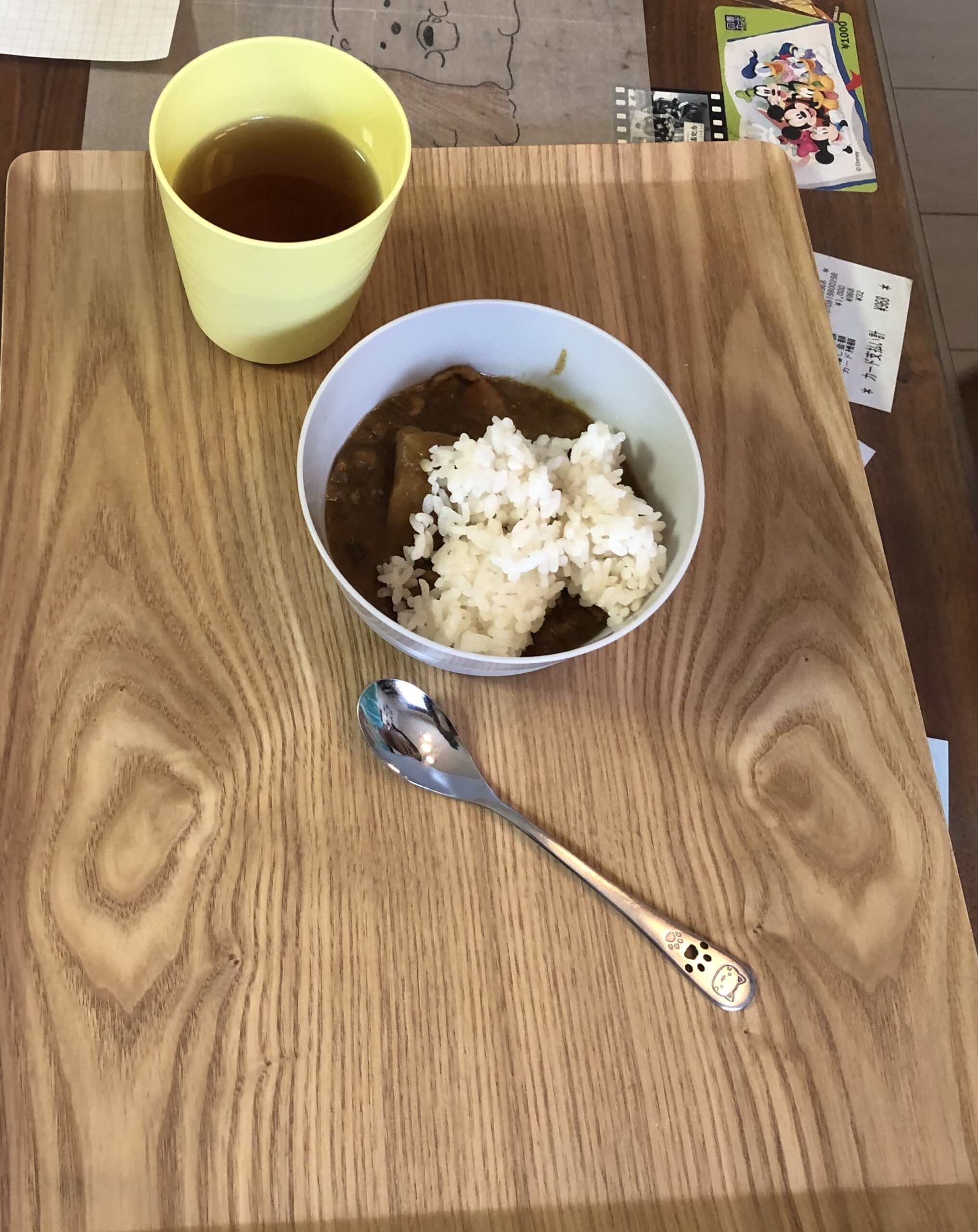
5.「なーちゃんとたーくんはプールです」
今日の午後は、なーちゃん(9歳)はプールがあるということで、その場所の玄関前までお見送りをしてくださいと、パパさんとママさんからお願いされていました。
どうやら近くの大学内のプールで、子どもたちを受け入れた「スイミング教室」が開かれるようですね。
そこで、時間となっていざ出かけようとしましたら、なーちゃん(9歳)が、「たーくん(5歳)も一緒だよ」というではないですか。
「聞いてないよー」byコロちゃん
急いで、アイパッドの連絡メールを再確認しても、なーちゃん(9歳)の名前はあってもたーくん(5歳)の名前は出てきません。
コロちゃんは、急いでパパさんとママさんにメールで聞きましたよ。
「今日のプールはなーちゃん+たーくんなの?」byコロちゃん

長男一家パパさん
そだよ。
だったら、最初から言えよー。コロちゃんは慌てちゃったじゃないですか。
コロちゃんは、午後の時間になったので、2人の子どもたちを急き立てて水着に着替えさせたのですが、こんどは2人は「プールの場所の地図」をどちらが持つかで大騒ぎです。
私が持つと言うなーちゃん(9歳)。地図を自分が持たないと「いかない!」と泣きわめくたーちゃん(5歳)。
コロちゃんは、もう時間が迫っているのでたーくん(5歳)を、強引に立たせて外に出ます。そしたら、なーちゃん(9歳)が気を回して地図をたーちゃん(5歳)に渡してくれました。
泣き顔が打って変わったたーくん(5歳)は、「今泣いたカラスがもうわーらーった※」ですよ。
(※変わりやすい子ども心を言う:出典:門三味線:1895年:斎藤緑雨)
いやいや、笑っている顔は実に可愛いんですけどね。思わずコロちゃんは、ホッと息を漏らしましたよ。
ε-(´∀`*)ホッ

6.「ママさん&子どもたちが帰宅しました」
子どもたちのお迎えは、お仕事を終えたママさんが行くとのことで、コロちゃんはそのまま「長男宅で留守番」をしながら、このブログ原稿をカキコキしています。
そして、原稿が書き終わった頃にちょうどプールを楽しんだ子どもたちとママさんが帰ってきましたよ。
「ただいまー!」by子どもたち
これでコロちゃんの今日のミッションは終了です。
家の中で留守番して、午後には近くの「水泳教室」を開くという建物の入り口まで見送りをしただけなのですが、なんか疲れましたね。
まあ普段のコロちゃんは、ブログをカキコキするか、それとも読書しているかの物静かな生活ばかりですからね。子どもたちとの一時は「楽しくもあり疲れもあり」の時間でしたよ。

7.「5歳児と9歳児とコロちゃん」
上記のような「たのしくもあり疲れもあり」の時間を過ごしたコロちゃんでしたが、ここで終わっては、ちょっと物足りませんね。
今日子どもたちと遊んだコロちゃんが、感じた事をいくつか調べながら書いてみましょう。
コロちゃんが子どもの頃は、身の回りに同年齢の子どもたちはワサワサと居ました。学校が終わってから家に帰っても、直ぐ外に出れば遊び相手はウジャウジャいる時代でした。
今の子どもたちは多分そうではないでしょうね。
そこで「5歳児のたーちゃん」と「9歳児のなーちゃん」の同年齢の子どもたちがどのくらいの人数がいるのかを調べて、コロちゃん世代とどのくらい違っているのかを見て見ましょう。
最初に、有名な「団塊の世代(1947~1949年生まれ:現在75~77歳)」を書いておきますね。
◎「出生数」
➀「団塊の世代:1947年:267.9万人」
➁「団塊の世代:1948年:268.2万人」
➂「団塊の世代:1949年:269.7万人」
➃「コロちゃん年代出生数:186.8万人」
⑤「なーちゃん年代出生数:100.3万人」
⑥「たーくん年代出生数 :86.5万人」
上記の「①~➂の団塊の世代」は凄いですね。何しろ「日本史上最大の人口ボリュームゾーン」ですからね。
なんと「年間260万人台が3年間」も続きました。
そして「➃コロちゃん年代:186.8万人」も、「団塊の世代」よりは少ないですが、それでも180万人台もいましたよ。
少年コロちゃんが外に出ると、ウジャウジャと子どもがいたのも当然ですね。
それと比べると、「⑤なーちゃん年代:100.3万人」と「⑥たーくん年代:86.5万人」は、ずいぶん少なくなりましたね。
それも年齢層が下がるほど出生数は減少しています。これでは、友達と遊ぶのもなかなか難しい時代になっているのではないかと、コロちゃんは懸念をしましたよ。
ただなーちゃん(9歳)は、今日お友達が遊びにきていましたから、社交的なのかな?
たーくん(5歳)も、友達をたくさんつくるんだぞー。

8.「孫のいる高齢者」
次に「孫のいる高齢者の割合」を見て見ましょう。このような設問の調査は、公的な調査では見つかりませんでしたが、ネット内にはいくつか調査結果が出ていましたね。
下に書きますね。最初は「55歳以上の女性」を対象とした調査です。
◎「55歳以上の女性で孫のいる割合」
○「全体:孫あり62.7%:孫なし37.3%」
うーむ、孫がいるいないで6:4の割合となっていますね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
もう一つの調査は「子どもがいる60代の高齢者」を対象としたものです。
◎「子どもがいる60代の高齢者」
○「孫がいる59.0%:孫の人数の平均値2.58人」
うーむ、こちらの調査でも「孫がいる60%」ですね。これらを見ると、だいたい6割の高齢者には孫がいるようですね。
(〃σ。σ)o_彡 ナルホド
この6割という数字が小さいのか大きいのかは、人によって感じ方は違うでしょうけれど、少し前までの「日本」では、ほとんどの高齢者に孫がいたと思われますね。
なにしろコロちゃんの青年時代の1970年には、生涯未婚率が「男性1.70%:女性3.33%」という皆婚社会だったのです。
それよりも前の1960年の生涯未婚率は、「男性:1.26:女性1.78」と更に低い数値になっています。
1世帯あたりの子どもの数も、今より大分多い時代ですから、多くの高齢者は孫の顔を見れたと思われますね。
コロちゃんは、結婚も孫もそれぞれが人生で選んできた道ですから、「子どもがいるいない」ことや「孫がいるいない」ことはあれこれ言うものではないと考えていますよ。
ただ、コロちゃんの場合は「子育て」は苦労も多かったですけれど、それを上回る喜びを得られていましたよ。
そして「孫の世話」は、苦労はあまりありませんね。
何よりも「子育て」の時のような「重い責任」がありません。ただ「可愛がる」だけで済んでしまいます。その気楽な分だけ、喜びも小さいのかも知れませんね。

9.「コロちゃんと時代によって変わる価値観」
上記でコロちゃんは、「お義父さん」という言葉に「権威主義の価値観の残渣」を未だに感じているという話を書きました。
その「お義父さんという言葉の権威主義ニュアンス」は、今ではすっかり無くなっていると思われます。
それと同じように変わった価値観に「高齢の親の介護は嫁の仕事」というものがあると思います。
1960~1970年代では、高齢になった親の介護は自宅で長男の嫁が行ない、自宅で看取るのが当然とされていたのです。
その頃にベストセラーとなった本に「恍惚の人※」という小説がありました。当時194万部の大ベストセラーになりました。
(※恍惚の人:1972年:有吉佐和子:新潮社)
あらすじは、「高齢になった認知症の男性に振り回される家族の物語」ですが、時代は「高度成長の真っただ中」の1970年代(※)です。
(※1970年の平均寿命は男性69.31歳・女性74.6歳)
この小説の中にもありましたが、この時代の思考が衰えた高齢者は病院や施設から「家に帰りたいよ」と叫ぶのですよ。
この時代の常識では、家で介護されて家で亡くなるのが大多数でしたから、「家に帰りたいよ」という高齢者の言葉が出るのですが、家で介護する嫁さんはたまったものではありません。
そこで家庭内の悲喜劇のドラマが進行するわけですが、1970年代にはそのような小説がベストセラーになる社会的背景があったと思われますね。
その後2000年になって「介護保険制度」が発足しました。それからもう24年間も過ぎています。社会の常識も、高齢者の介護は「介護保険」で行なうものだとすっかり変わりましたね。
コロちゃんも、自分の介護は「介護保険」は利用しても、間違っても子どもたちに介護されようとは考えていません。
このコロちゃんの考え方は、リベラルとか政治思想で生まれたものではありませんね。時代の変化が新しい考え方を作ったとコロちゃんは考えていますよ。
今日は、「コロちゃんと子どもたちのお留守番の日」のあれこれと、子どもたちのお世話をする中でコロちゃんが考えたことを、いくつか書いてみました。
どれか一つでも、お読みの皆さんの興味を引いた内容があれば嬉しいですよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。








コメント